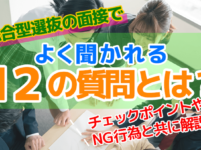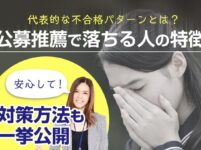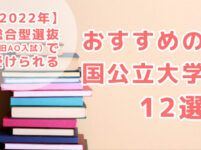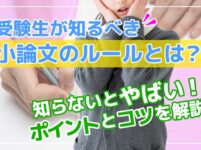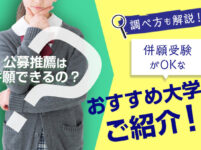BLOG

- 「総合型選抜って何?一般入試と何が違うの?」
- 「総合型選抜で受験してみたいけど、自分に向いているのかな?」
こんな疑問をもっている受験生は必見です!これを読めば、総合型選抜について抱いている疑問は軒並み解決されます。
なぜなら、当ページは総合型選抜対策の専門塾ホワイトアカデミーが作成した「総合型選抜のまとめガイド」だからです。
本文の中では、総合型選抜とは何か、選抜方法、選考スケジュール、具体的な対策方法といった、総合型選抜に関する情報を幅広く掲載しています。
各テーマをより詳しく解説したページも合わせて紹介しているので、総合型選抜について疑問や不安がある受験生はぜひ最後までチェックしてください。
この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。
自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。
高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。
倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。
目次
そもそも総合型選抜(旧AO入試)とは?
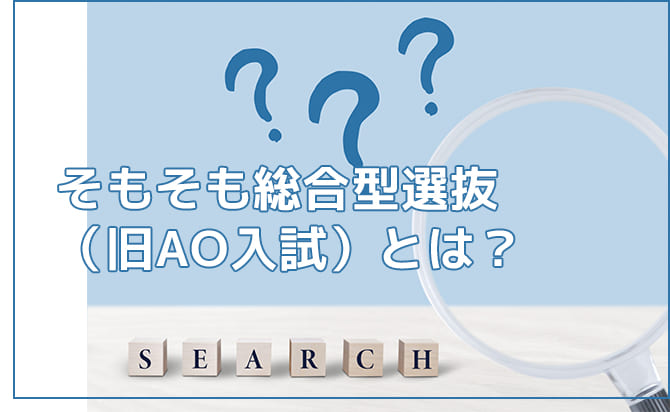
総合型選抜とは、2021年度入試から新たに導入された入試方法です。
もともとはAO入試と呼ばれる入試方法でしたが、総合型選抜に変わったことで名称だけでなく中身も変化しています。
まずはAO入試が総合型選抜になって何が変わったかを確認しましょう。
総合型選抜は大学が「求める学生」を選抜する入試制度
総合型選抜は、大学が掲げる「アドミッション・ポリシー」に合致した学生を選抜するための入試制度です。
「アドミッション・ポリシー」とは、各大学が示す入学者の受け入れ方針のこと。大学・学部・学科ごとに定めており、公式サイトや入試要項で公表されています。
総合型選抜の選抜方法は、面接・小論文・プレゼンテーションなど大学によってさまざまです。
複数の選抜方法を組み合わせて評価することで、大学が求める学生像に合致するかどうかを総合的に判断します。
旧AO入試より学力も重視される傾向がある
総合型選抜の一番の特徴は、AO入試では導入しない大学も多かった学力を問う選抜内容が導入される事になった点です。
そもそもの話になりますが、総合型選抜が導入されるきっかけとなったのは文部科学省が実施した大学入試改革です。
文部科学省が実施した大学入試改革では、すべての入試方法で学力を評価する方針が取られました。それにより総合型選抜では共通テストや大学が個別で準備した学力を問う課題が課されることになっているのです。
参考資料:大学入学者選抜関連基礎資料集
調査書や志望理由書といった書類で選抜していたAO入試と比較すると学力が合否判定に重要になる点は押さえておきましょう。
総合型選抜のアドミッション・ポリシーとは?
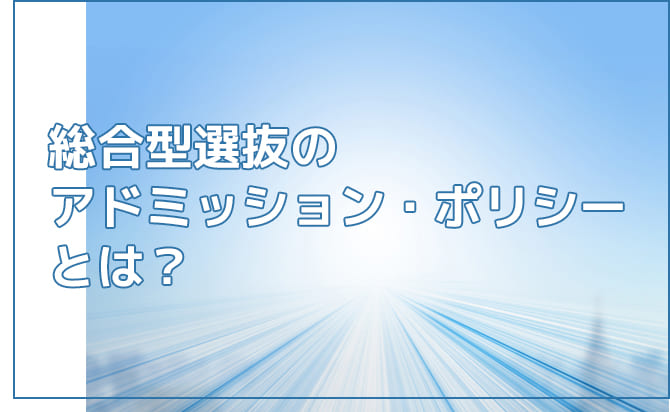
総合型選抜の評価基準となるのが、アドミッション・ポリシーです。
これは各大学・学部・学科で定めているもので、内容はそれぞれ異なります。
例として、早稲田大学商学部のアドミッション・ポリシーを見てみましょう。
早稲田大学の建学の理念である『進取の精神』の涵養を目指す、一定の高い基礎学力を持ちながら、かつ知的好奇心が旺盛で、自分で計画を立て、種々の課題に積極的に立ち向かう意欲に満ちた個性的な学生を、全国各地や世界中から多数迎え入れる。
「学識ある実業家」の養成を創設以来の教育理念に掲げる本学部は、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力等のビジネス・スキルを修得する場であるとともに、それ以上に広い視野に立って経済社会を質・量ともに豊かにすることを目指す「商学」の基本理念を理解し、自らの使命や役割を認識した上で判断・行動しようとする人々の学びの場である。そのために、論理的思考力や社会科学の基礎となる学力が必要不可欠である。国際感覚・倫理観を兼ね備えた企 (起)業家精神を養い、深い学識と教養に裏付けられた実業家を目指し、ビジネスリーダーとして地球社会に貢献しようと志す学生を受け入れたいと考えている。(早稲田大学商学部 公式サイトより抜粋)
早稲田大学商学部のアドミッション・ポリシーによると、学部が求めているのはこのような学生とわかります。
- 一定の高い基礎学力を持ち、知的好奇心が旺盛で、自分で計画を立ててさまざまな課題に立ち向かう意欲に満ちた個性的な学生
- 論理的思考力や社会科学の基礎となる学力を持つ学生
- 国際感覚と倫理観を兼ね備えた企(起)業家精神を養い、深い学識と教養に裏付けられた実業家を目指す意志がある学生
- ビジネスリーダーとして地球社会に貢献しようと志す学生
アドミッション・ポリシーにはどのような学生を求めているかが明確に示されているので、総合型選抜での受験を考えている場合は念入りにチェックしましょう。
▶︎アドミッション・ポリシーとは?出願書類への反映方法まで解説
総合型選抜の選考方法

総合型選抜の主な選考方法はこちらです。
- 面接・面談
- 口頭試問
- 実技試験
- 教科・科目に係るテスト
- 大学入学共通テスト
- 小論文
- プレゼンテーション
- 資格・検定試験の成績
- 志望理由書
- 調査書(評定平均・課外活動・欠席数など)
これまでのAO入試では調査書や志望理由書、面接によって選抜していましたが、総合型選抜では共通テスト・特定の教科のテスト・資格試験の成績も重視されます。
さらに詳しく総合型選抜の選抜方法や合格のポイントを知りたい場合は、以下の記事をチェックしてみてください。
他の大学入試の選抜方法との違い
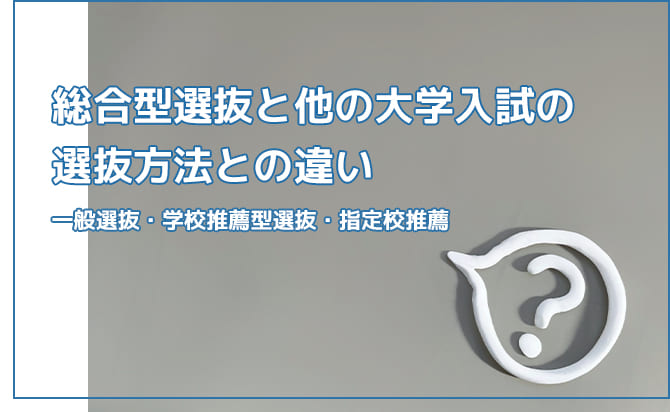
ここからは、総合型選抜と一般入選抜・学校推薦型選抜(公募推薦)・指定校推薦との違いをそれぞれ見ていきましょう。
一般選抜との違い
一般選抜は、学力試験の結果のみで選抜されます。
総合型選抜は学力をはかる選考方法もありますが、面接や小論文なども含めて総合的に判断します。
またもう一つの違いは、試験の時期です。
一般選抜は年明けの1〜3月に実施される大学がほとんどですが、総合型選抜の試験が行われるのは9〜11月となっています。
ちなみに総合型選抜でも、選考方法に共通テストがある場合は1月に試験を行うこともあるので要チェックです。
学校推薦型選抜(公募推薦)との違い
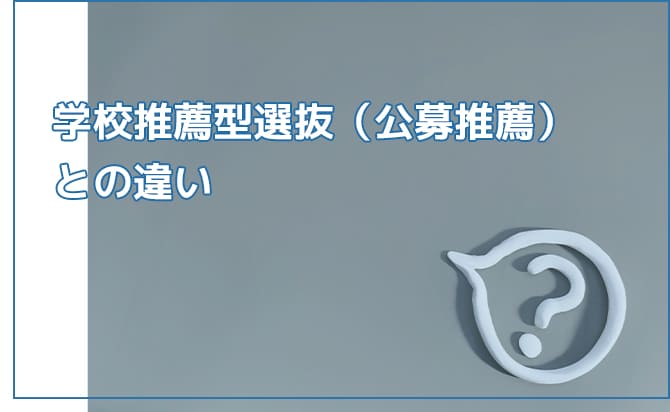
学校推薦型選抜と総合型選抜の違いは、主に4つです。
| 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 |
|---|---|
| 学校の推薦が必要 | 学校の推薦は不要 |
| 出願時に一定の評定平均が求められる事がほとんど | 評定平均は出願条件に含まれないケースも少なくない |
| 小論文・面接中心の選抜 | 小論文・面接・プレゼン・共通テストなど、大学によって選抜方法が異なる |
学校推薦型選抜と総合型選抜を比較すると、総合型選抜の方が受験生側からみても大学側からみても自由度が高いことがわかります。
「高校の成績にとらわれず受験する大学を決めたい」「テスト以外の得意な選抜方法で受験したい」という方には総合型選抜がおすすめです。
指定校推薦との違い
指定校推薦は、大学が提示した枠に対して高校側が校内選考をして推薦者を決める選抜方法です。
決められた人数だけが指定校推薦を利用でき、高校の推薦を受けて受験した場合は必ず入学しなければなりません。
総合型選抜との違いは、校内選考に通れば基本的に合格が見込まれる事です。そのため、志望大学・志望学部の推薦枠が高校にあるのでしたら出願する価値は大いにあります。
利用するメリットとデメリットの一覧
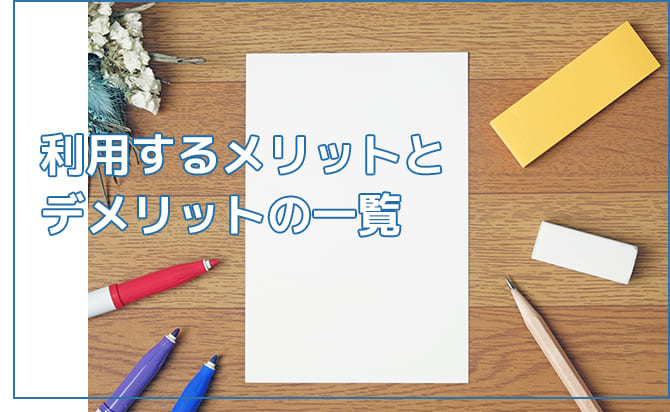
では、総合型選抜を利用するメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
それぞれ簡単に表にまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 学力に自信がなくても入学できる | 一般選抜よりも自力での対策が難しい |
| 模試の偏差値以上の大学に入学できる可能性がある | 一般選抜の勉強にかけられる時間が減る |
| 評定が低くても受験できる | 併願できないことが多い |
| 課外活動や部活での頑張りをアピールできる | 実は入学後に苦労するケースが多い |
総合型選抜は、学力だけでなくさまざまな選抜方法で大学が求める学生を選抜します。そのため偏差値にとらわれずレベルの高い大学にチャレンジできるのが大きなメリットです。
総合型選抜のメリット・デメリットについては以下のページでより詳しくまとめていますので是非ご覧ください。
どんな人に向いている入試なのか?
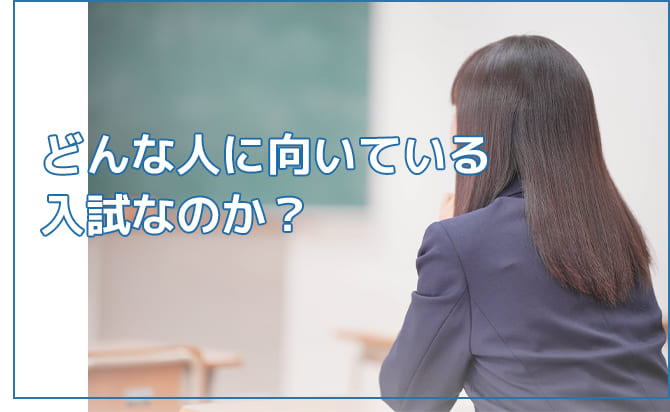
総合型選抜は学力だけでなく、論理的思考力やプレゼン力、課外活動・部活などの実績が求められます。
したがって、「高校の成績がいい」や「模試の偏差値が高い」だけでは総合型選抜での合格は難しいでしょう。
ここでは総合型選抜で合格した人に共通する特徴をいくつか紹介します。
総合型選抜で志望大学に合格した人に見られた特徴
- 受験する大学や学部が求める学生像に合っている
- 部活等の課外活動の活動実績がある
- 完成度の高い出願書類を作り上げる準備力がある
- 大学入学後の確固たるビジョンがある
- 面接で好印象を与えるだけの魅力的な個性がある
- 2級以上の英検を取得している
- 評定平均が高い
ここで挙げた特徴に複数当てはまっている方は、総合型選抜で合格できる可能性が高いです。しかしどれも当てはまらないからといって、総合型選抜が全く向いていないとは限りません。
「自分は総合型選抜に向いているのかな?」と気になった方は、こちらの記事をチェックしてみてください。
▶︎総合型選抜入試(旧AO入試)に受かりやすい人の特徴を大公開
総合型選抜による入学者数は国公立大学・私立大学ともに増加している
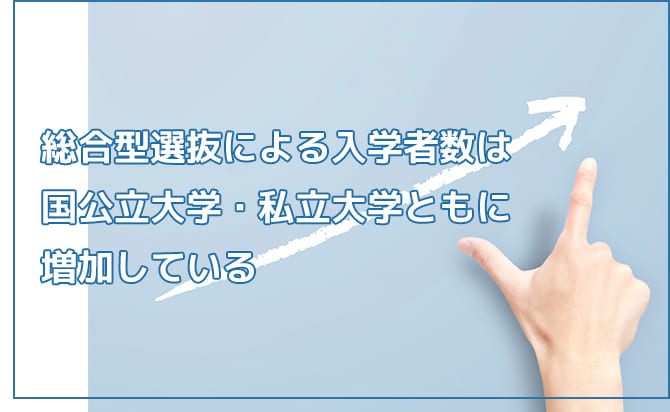
少子化により大学の入学志願者数は減少していますが、総合型選抜による入学者は増加傾向にあります。
| 年度 | 国立 | 公立 | 私立 | 全体 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年度 | 4,016 | 927 | 56,184 | 61,127 |
| 令和2年度 | 4,106 | 1,089 | 59,846 | 65,041 |
| 令和3年度 | 5,342 | 1,287 | 71,292 | 77,921 |
引用元:文部科学省「令和3年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」
まだまだ一般選抜や学校推薦型選抜と比べると利用者が少ない入試ですが、総合型選抜を導入する大学や利用する受験生はこれからどんどん増えていく事が見込まれます。
総合型選抜のスケジュール

総合型選抜の出願は通常9月ごろ、選考と合格発表は10〜11月ごろに行われます。
大学・学部・学科ごとにスケジュールは異なるため、総合型選抜の利用を考えている方は志望校のスケジュールをしっかり確認しておきましょう。
ここでは一般的な総合型選抜のスケジュールを紹介します。

エントリーと出願の時期の違いは押さえよう
総合型選抜には、ほかの選抜方法であまり聞くことがない「エントリー」というものがあります。
これは簡単に言うと「総合型選抜を受験するための予約」のことです。
総合型選抜では出願前にエントリーが必要な場合があるため、出願とエントリーの違いやそれぞれの時期はしっかり把握しておきましょう。
総合型選抜は年内に合格が決まるケースが多い
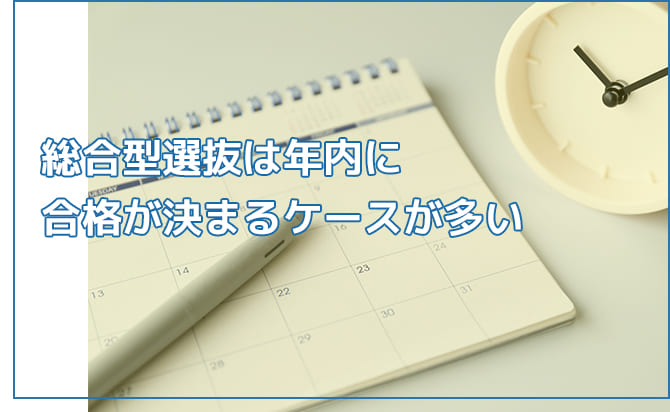
総合型絵選抜は9月1日以降に開始、11月1日以降に合格発表、と文部科学省により決められています。
そのため、大体どの大学でも夏休み明けに試験が始まり、年内までには合格が決まります。
いつから対策をするのが良いのか?
総合型選抜の対策は、できるだけ早く始めたほうが良いです。
総合型選抜で求められる能力は大学によって多少異なりますが、一定以上の学力や部活・課外活動の実績、論理的思考力、プレゼン力は基本どの大学でも求められます。
これらは対策してすぐに身につくものではなく、練習の積み重ねで身につけられるものです。
そのため総合型選抜の対策は、できれば2年の夏休みまでに始めたほうがいいでしょう。
いつから対策すべきかより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
志望大学の合格を勝ち取るための対策方法
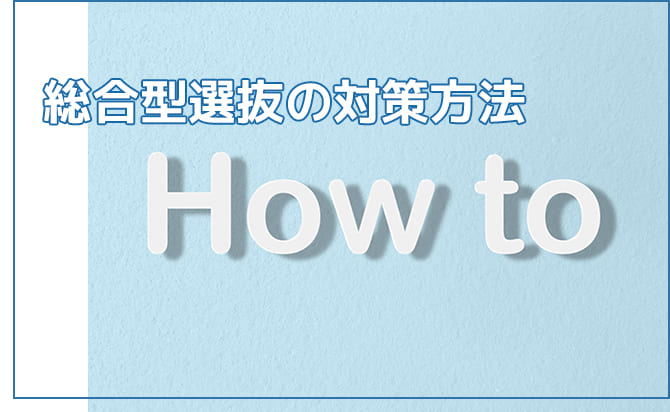
ここからは総合型選抜を受験する上で、具体的にどのような対策を行うべきか解説していきます。
高校の勉強で優秀な成績を修める
総合型選抜はAO入試と違い、学力面の審査も行われます。
独自試験として学力テストがあるケースや出願条件に評定平均値が設定されているケースもあるので、日頃からしっかり勉強しておくことが大切です。
早めに大学の情報収集を行いアドミッション・ポリシーを理解する
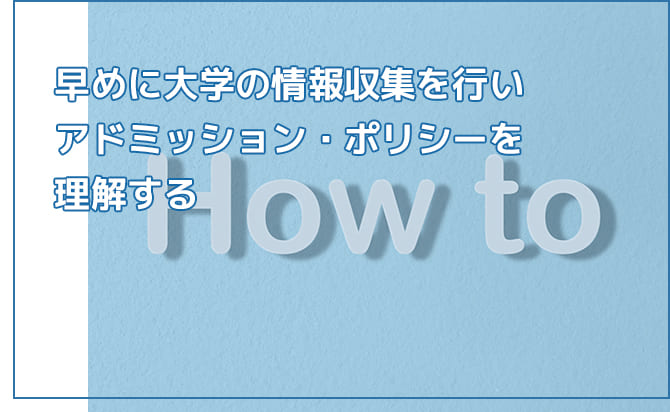
総合型選抜では、各大学・学部・学科が示す「アドミッション・ポリシー」に沿った学力・学習意欲・志が求められます。
総合型選抜を受験する場合は、なるべく早く各大学・学部のアドミッション・ポリシーを読み込み、大学ごとの研究や教育の特徴を理解した上で志望校を決めましょう。
ちなみに総合型選抜を受験するなら、志望校のオープンキャンパスには行ったほうがいいです。
「なぜオープンキャンパスに行ったほうがいいのか?」、「オープンキャンパスに行くことでどんなメリットがあるのか?」、という点にが気になる方は以下の記事をチェックしてみてください。
▶︎意外と知らない総合型選抜の合否とオープンキャンパスの関係性
面接・面談対策を行う
総合型選抜の試験で必ずといっていいほど行われるのが、面接・面談です。
これは1人で対策することが難しいため、学校や塾で面接対策を行ってもらい、面接に対応できる論理的思考力を養いましょう。
総合型選抜の面接・面談対策については以下の記事で詳しくまとめています。総合型選抜を受験する予定の方は必ず目を通しておきましょう。
▶︎総合型選抜(旧AO入試)の試験当日の服装と髪型を解説
▶︎口頭試問の特徴を評価ポイントや対処方法と共に解説
▶︎総合型選抜の面接でよく聞かれる質問を大公開
高校で取り組んだ活動を記録しておく
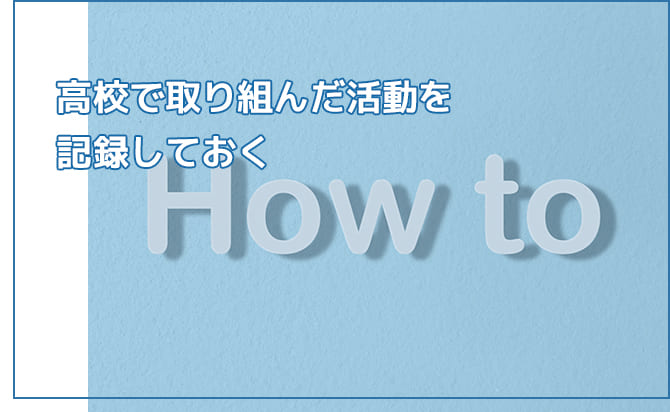
総合型選抜の出願時には、志望理由書や学習計画書を書いて提出する必要があります。
学習計画書とは、あなたが入学後何を学び、どんな学生生活を送りたいかをまとめた計画書です。
これらの書類をスムーズに書けるよう、高校で取り組んだ中でエピソードとして使えそうな活動は記録を残しておきましょう。
具体的な活動の例としてはボランティア活動や部活が挙げられます。どうやって書類に書くべきかは以下の記事で詳しく解説しているので要チェックです。
▶︎ボランティア活動は総合型選抜(旧AO入試)の実績になるのか?
▶︎活動報告書に部活の内容を書くコツと記述した例文を大公開
英検・漢検・簿記など資格を取得する
高校での実績や評定平均値に不安がある場合は、資格を取得しておくのもおすすめです。
総合型選抜に活かせる資格にはこのようなものがあります。
- 英検(2級以上)
- TOEIC(550点以上)
- TOFEL(40~50点以上)
- 中国語検定
- 独語検定
- 漢検(2級以上)
- 簿記(2級以上)
- 数字検定(準1級以上)
- 情報セキュリティマネジメント
- 基本情報技術者
各資格の内容や受験情報についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
▶︎総合型選抜(旧AO入試)に役立つ資格の名前と取得メリット
総合型選抜に強い塾に通う
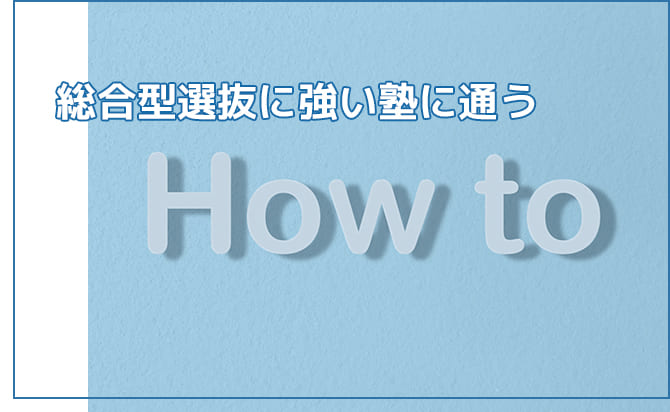
「受験のために塾に通ってもいい」という家庭なら、ぜひ総合型選抜の受験対策に特化した塾に通いましょう。
以下の5つの塾は総合型選抜の対策に特化しており、合格実績もしっかりあるのでおすすめです。
- ホワイトアカデミー高等部
- Loohcs志塾
- AOI
- 洋々
- 早稲田塾
それぞれの塾の特徴や塾を選ぶポイントについて知りたい方はこちらをチェックしましょう。
▶︎おすすめの総合型選抜(旧AO入試)の対策塾と塾選びのコツ
総合型選抜を利用する際の注意点

次に総合型選抜の注意点について解説します。
総合型選抜を受験する予定の方や受験するか迷っている方は必ずおさえておきましょう。
毎年入試の新設・廃止・内容変更がある
総合型選抜は、毎年どの大学・学部でも必ず行われているわけではありません。
大学は毎年入試制度の検討・変更をしており、それによって総合型選抜の廃止・新設や学校推薦への移行が行われます。
そのため「去年あったから今年もあるだろう」と判断するのではなく、常に最新の情報を確認して「今年は本当に利用できるのか」を調べるようにしましょう。
志望学部・志望大学選びに制約が生じる
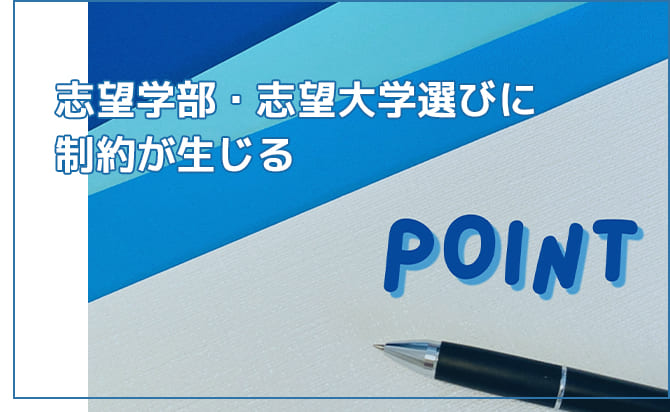
総合型選抜は導入からまだ日が浅く、学力試験による一般選抜などと比べると実施している大学・学部は少ないのが現状です。
志望する大学・学部が総合型選抜をやっていない場合は、総合型選抜での受験はもちろんできません。
総合型選抜を実施している大学・学部の中から選ぶ必要があるため、受験先の選択肢が狭くなる点は押さえておきましょう。
大学によって合格者に入学前教育が行われる
総合型選抜は基本12月までに合格が決まるため、大学によっては入学までに課題が出される場合があります。
課題の内容としては、専攻分野の課題や基礎的な学習課題、課題図書の読書感想文などが多いようです。
不合格になる可能性も十分にある
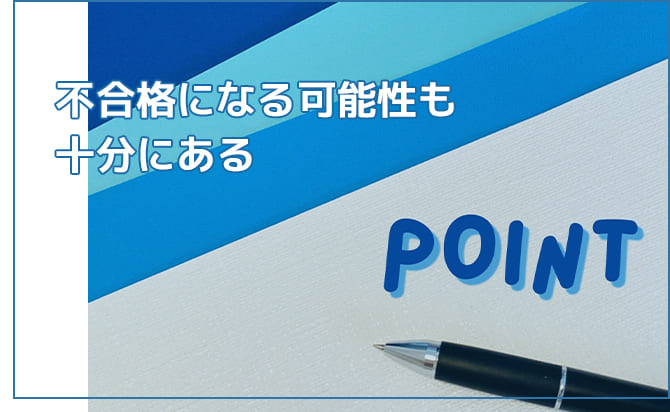
総合型選抜は学校の推薦を受けるわけではないので、不合格になる可能性も十分にあります。
特にアドミッション・ポリシーとの合致度が低い学生は、総合型選抜では落ちることが多いです。
不合格になった場合も想定して、一般選抜の勉強もしっかりしておきましょう。
併願できないケースがあり、合格後は辞退できないケースが多い
一般選抜と総合型選抜の併願は可能ですし、併願受験が可能な総合型選抜を実施している大学もあるのは事実です。
しかし、大学の中には総合型選抜の併願を認めていないケースもあります。併願受験を認めない大学では総合型選抜で合格した受験生に必ず入学する事を求めてきます。
そのため、総合型選抜では併願が認めなられない大学に合格した時点で入学が必須になる事を把握しておきましょう。
ただし、合格した際に併願を認めない大学への入学を確約できる前提であれば複数の大学に出願する事は不可能ではありません。それに総合型選抜と一般選抜の併願受験も可能です。
そのため、総合型選抜を利用した上で複数の大学の併願受験をお考えでしたら、以下のやり方が有効です。
- 合格後の入学が必須の大学を第一志望にする。
- 併願受験が可能な大学を複数受ける。
- 第一志望の大学に受かった場合は、きちんと入学をする
- 他の大学の入学は第一志望に受かった時は辞退し、落ちた時のみ受け入れる。
上記のようなスタンスであれば、「合格後の入学が確約できる」ので併願は可能です。
多くの受験生が抱く主な疑問点
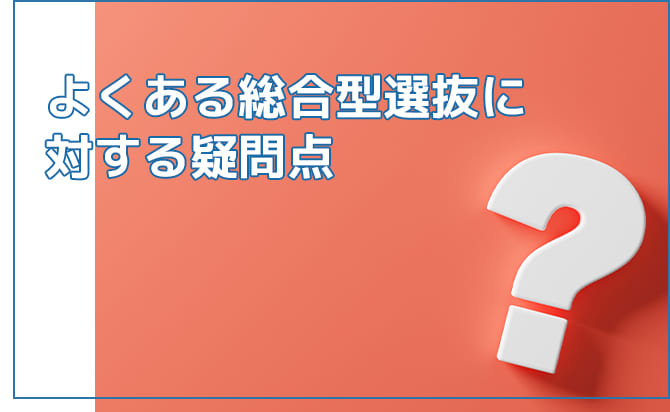
最後に総合型選抜についてよく挙げられる疑問点をまとめて紹介します。
それぞれの疑問についてより詳しく解説している記事も紹介しているので、総合型選抜のことをもっと知りたい方はぜひ目を通してみてください。
一般選抜とどちらが受かりやすいの?
一般選抜と総合型選抜は、選抜方法が大きく異なります。そのため、受かりやすさは人によって違うと考えるべきでしょう。
一般選抜が向いている人と総合型選抜が向いている人の特徴はこのように分けられます。
| 一般選抜向き | 総合型選抜向き |
|---|---|
| 基礎学力が高い | 大学のアドミッション・ポリシーに合致している |
| 自分で受験までの学習計画を立てられる | 選考でアピールできる強みがある |
| 将来の目標は大学で見つけたい | 将来やりたいことがはっきりしている |
自分が総合型選抜に向いているかどうかさらに知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
▶︎一般選抜と総合型選抜(旧AO入試)ではどっちが難しいの?
欠席数はどの程度影響するのか
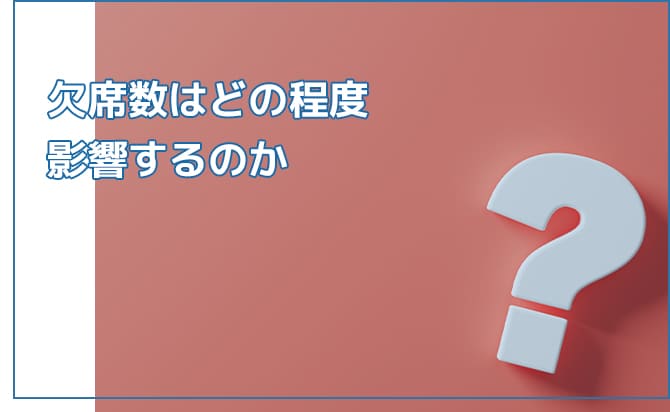
選考する上で大きな要素ではないものの、欠席数はしっかりチェックされます。
例えば、合否ラインに同じような学力・実績の受験生が2人並んだ場合は、欠席数がより少ないほうが合格をもらえるでしょう。
受験ではこうした微々たる差が合否を分けるため、欠席数は少ないに越したことはありません。欠席数と合否の結果についてより詳しく知りたい方はこちらの記事がおすすめです。
浪人生でも受けられるの?
浪人生が総合型選抜を受けられるかどうかは、大学・学部によって異なります。
最新の募集要項を確認し、出願条件を満たしているかどうかチェックしましょう。浪人生の総合型選抜との相性や受けられる大学の一例については以下のページで紹介しているので是非ご覧ください。
受かりやすい狙い目の大学はどこ?
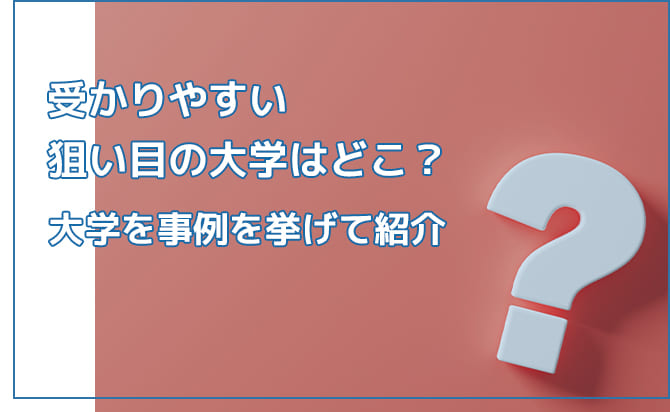
総合型選抜で受かりやすい狙い目の大学はこちらです。
- 青山学院大学 文学部史学科
- 明治大学 電子生命学科
- 法政大学 文学部地理学科
難関大とされるGMARCHも、総合型選抜で狙えばより楽に合格できる可能性があります。
今取り上げた大学がなぜ狙い目なのかを知りたい方は、以下の記事でポイントを紹介しているのでぜひチェックしてください。
万が一落ちたらどうするのか?
総合型選抜で不合格だった場合、2つのパターンがあります。
- 総合型選抜の第Ⅱ期を募集している大学を受験する
- 一般選抜で受験する
総合型選抜の第Ⅱ期は11月下旬〜12月上旬が出願期間であり、12月中に試験が行われることが多いです。そのため、総合型選抜の第Ⅰ期に落ちた人でも出願は可能です。
第Ⅱ期の総合型選抜を実施している大学・学部の一例は以下の通りです。
【総合型選抜第2期の募集例】
ちなみに第Ⅱ期で不合格だった場合は第Ⅲ期の総合型選抜を実施している大学を受ける事が出来ます。もちろん、一般選抜に切りかえて同じ大学・学部または他の大学を受験するという選択肢もあります。
万が一、総合型選抜に落ちた際の選択肢については以下のページでより詳しくまとめているので是非ご覧ください。
一般選抜との併願は可能?
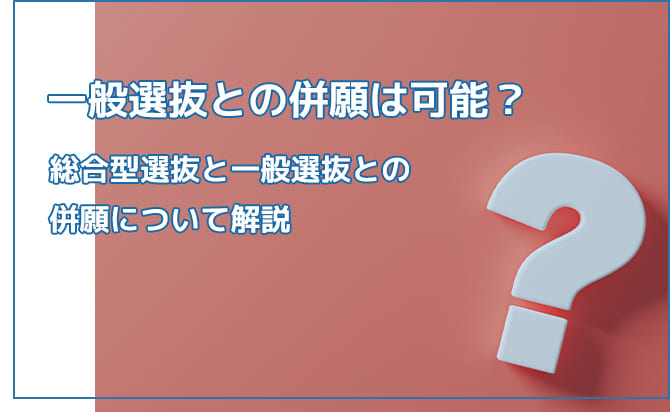
総合型選抜は一般選抜と併願できます。
総合型選抜の合格率は決して高いわけではないため、一般選抜との併願を前提に受験する人も多いです。
ちなみに総合型選抜で併願を認めている大学は少なくありません。併願を認めている大学は合格後の辞退も可能です。
そのため、一般選抜との併願を考えているのでしたら併願受験が可能な総合型選抜を実施している大学に目をつけましょう。併願が可能かどうかは最新の募集要項をチェックすれば分かります。
部活をやめたり、やっていなくても出願できるの?
部活の経験がない、または少ない場合でも、総合型選抜の出願は可能です。
ただし、合格するためには部活以外にアピールできる活動実績を積む事が求められます。なぜなら、部活という課外活動を行っている他の受験生よりも不利になるためです。
そのため、大学のアドミッション・ポリシーに合致していることをアピールできるような課外活動に積極的に取り組み、その経験を選考で活用しましょう。
十分な活動実績が無くても受かるの?
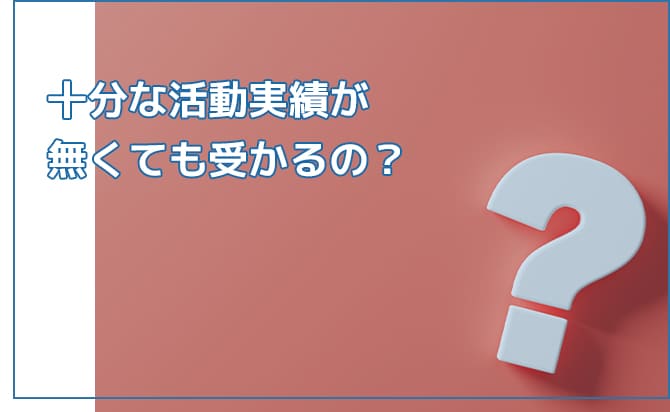
総合型選抜は、すごい実績を持っている人だけが合格するものではありません。
大学側はアドミッション・ポリシーをよく理解し、それに合致している学生を総合型選抜で獲得したいと思っています。
そのためアドミッション・ポリシーにあなたが合致していることをアピールできれば、経験が乏しくても合格できます。
「活動実績がないのにどうアピールしたらいいの?」とお悩みの方は以下の記事を参考にしてみましょう。
評定平均ってどれくらい必要なの?
合格に必要な評定平均は、狙う大学のレベルとどのような活動実績があるかによって異なります。
参考ですが、以下は当スクール生徒の評定平均値です。
- 早慶・上智に合格した生徒…4.5以上
- MARCH・関関同立に合格した生徒…4.3程度
- 日東駒専に合格した生徒…4.0前後
当然ながら、受験する大学のレベルが高ければ高いほど5.0に近い評定平均が求められます。
できれば4.5以上、少なくとも4.0以上の評定平均が取れるよう日頃から努力を積み重ねましょう。
おすすめの本や参考書はないの?
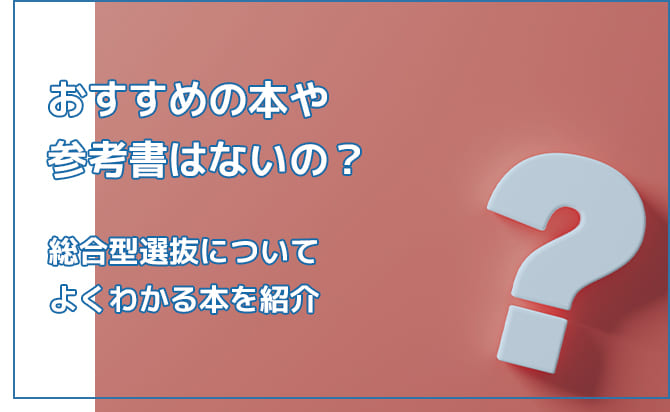
総合型選抜で役立つ本は以下の記事で紹介しています。
対策のポイントや具体的に何をしたらいいのかを知りたい方は、ぜひ目を通してみてください。
専門学校にも総合型選抜はあるの?
専門学校では、ほとんどの学校で総合型選抜を導入しています。
ただし一般的な4年制大学とは選考スケジュールや内容が異なるケースがあるので注意しましょう。
専門学校の総合型選抜の特徴
- 出願前のエントリー必須なケースがほとんど
- 学校説明会やオープンキャンパス参加が求められる事が多い
- 選考は6〜8月が多い
専門学校の総合型選抜については以下のページでより詳しくまとめていますので是非ご覧ください。
英検や英語の資格がないと受からないの?
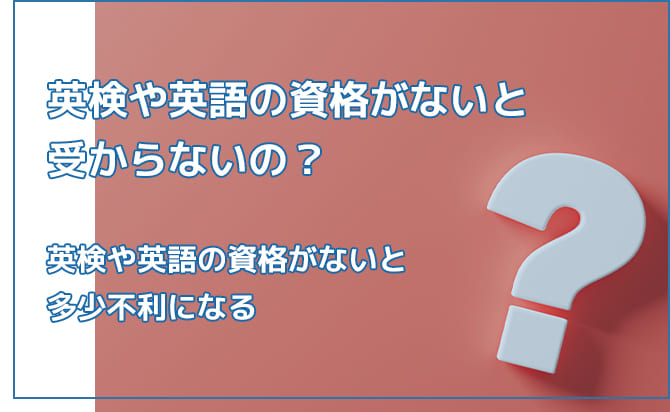
英検などの資格がないと総合型選抜で合格できないわけではありませんが、持っている人よりは不利になります。
なぜなら、多くの大学は英検をはじめとする英語の資格の保有を評価対象にしているためです。
例えば、一定以上の資格があれば試験が一部免除になったり、加点がもらえたりするケースがあります。
英検の影響や取得しておきたい英語資格についてさらに知りたい場合は、以下の記事をチェックしてみてください。
まとめ
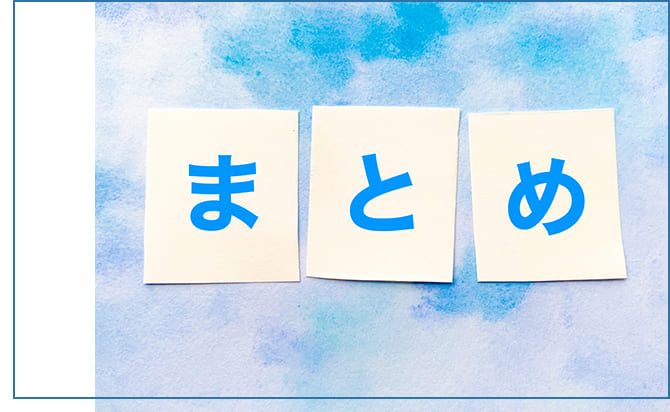
ここまで総合型選抜の概要や選考方法、スケジュール、対策方法をはじめとした幅広い情報をまとめて解説してきました。
最後にここまでの内容で特におさえてほしいポイントをまとめます。
特におさえておきたいポイント
- 総合型選抜はさまざまな選抜方法で受験生の能力を総合的に評価する入試
- 選抜方法は面接や書類審査だけでなく、学力試験や小論文、プレゼンなどもある
- 強みや将来の目標がある・大学が求める学生像に合致している人に向いている
- 総合型選抜の対策を始めるのは早ければ早いほどいい
- 志望校で総合型選抜が実施されているかは必ず募集要項でチェックする
今回の記事で総合型選抜の内容やどのように対策すべきかはしっかり把握できたと思います。
総合型選抜は一般選抜と比べるとまだまだマイナーな入試ですが、課外活動を頑張っていたり、将来やりたい事がある人にはチャンスが大きい入試です。ぜひ積極的に利用を考えてみてください。

ホワイトアカデミー高等部とは?
総合型選抜・公募推薦入試に特化した専門塾。
プロ講師が活動実績作りから小論文・面接まで、
マンツーマンで徹底サポート。
- カリキュラム修了者の合格率98%※1
- 上智大学合格率83%(2025年度)※2
- 小論文・書類すべて添削無制限
- 全授業が社会人のプロ講師による1対1形式
- カリキュラム修了者には合格保証制度を提供

※2 上智大学合格率83%は2025年度入試における上智大学受験者が母数です。
この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。
過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。
昨年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。