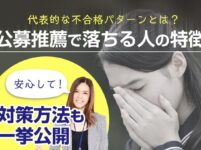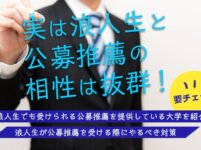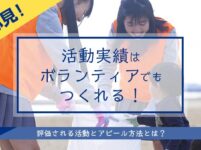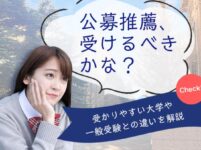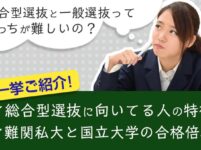BLOG

- 「学力に不安があるから総合型選抜(旧AO入試)で合格を目指そう」
- 「総合型選抜(旧AO入試)にはどんなメリットとデメリットがあるの?」
今のあなたはこんなお悩みを持っていませんか?
学力のみで合否を決定していた従来の大学入試ではなく、受験生の適性や大学側が求める理想の学生にどれだけ近いかで合否が決まるのが総合型選抜(旧AO入試)の特徴です。
合否の判断基準や対策方法は一般選抜とは明らかに異なるので、合格を勝ち取るために何をすればよいかについてはあまり知られていません。
また他の入試形式と比較して、総合型選抜(旧AO入試)が受かりやすいのかについても正しく理解している人は決して多くありません。
そこで今回は、総合型選抜(旧AO入試)は他の入試形式と何が違うのか、そして他の入試形式と比較した上でのメリットやデメリットについてご紹介します。
この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。
自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。
高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。
倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。
目次
総合型選抜(旧AO入試)のメリットとデメリット
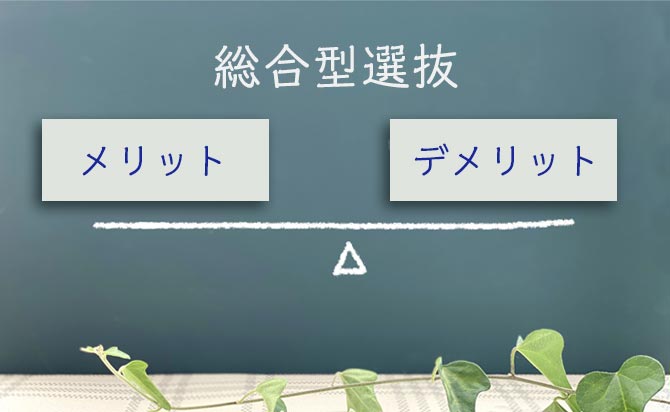
総合型選抜(旧AO入試)を利用するかどうかを考える際にはメリットとデメリットの両面を把握することが欠かせません。
以下にメリット・デメリットを一覧にしてまとめました。
| メリット |
|---|
| ・学力に自信がない人でも大学に入学できる可能性がある ・模試の偏差値や判定以上の大学に入学するチャンスがある ・指定校推薦と違い、評定が低くても受けられることが多い ・課外活動やクラブ活動の頑張りをアピールできる ・年内に受験から解放される |
| デメリット |
| ・明確な正解がないので対策が難しい ・時間が有限である以上、一般受験の勉強に割ける時間が減る ・受験する学校によっては専願受験が求められる ・入学後に苦労することが実は多い |
総合型選抜(旧AO入試)のメリットとデメリットを正しく把握するためには、総合型選抜(旧AO入試)について正しく理解することが必須です。
そこで総合型選抜(旧AO入試)のメリットとデメリットの詳細をご紹介する前に、総合型選抜(旧AO入試)がどのような試験なのかについて取り上げます。
総合型選抜(旧AO入試)と他の受験形式の特徴一覧
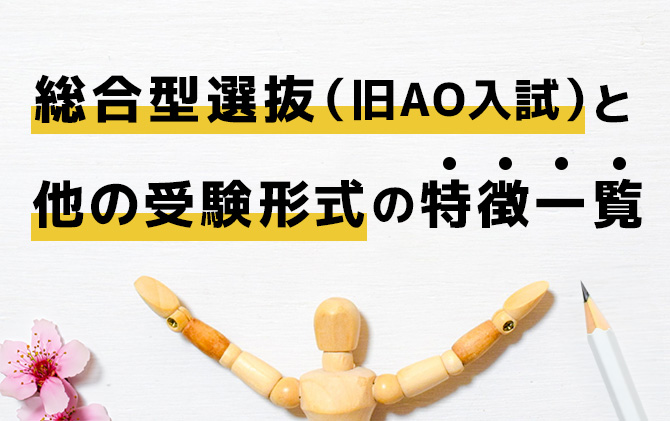
総合型選抜
総合型選抜(旧AO入試)とは「アドミッションズ・オフィス(入学許可事務局)」の頭文字を取って作られた名称です。
大学の狙いと合否判断で見られるポイント
総合型選抜(旧AO入試)では、テストの点数だけでは把握できない出願者の能力をさまざまな角度から評価した上で合否を決定します。
総合型選抜を実施する大学側の狙いは「求めている理想的な学生を確保すること」。総合型選抜(旧AO入試)では各大学が「理想の学生像の基準(アドミッションポリシー)」を自由に定めており、そのポリシーに合う学生を求めています。
合格基準は各大学によって異なりますが、多くの大学において以下の項目を合格基準にしています。
- 入学したい大学が行なっているカリキュラムを学ぶ強い意志があるか
- 学生生活の活動は十分か
- アドミッションポリシーを理解した上で出願しているか
選考で求められることとは?
総合型選抜(旧AO入試)を受ける時には「志望理由書」、「調査書」、「活動報告書」などの書類を出願時に大学に提出しなければいけません。
そのため、志望した理由や高校時代に行なった活動実績などを事前にまとめておくとよいでしょう。
なかには、オープンキャンパスへの参加を出願条件としている、面接を複数回行なう、グループディスカッションやプレゼンテーションを課題にする、といった大学もあります。
一般選抜とは問われる内容が明らかに異なるため、総合型選抜の利用を考えている場合は、出願前に応募書類や試験内容を必ず確認するようにしてください。
指定校推薦
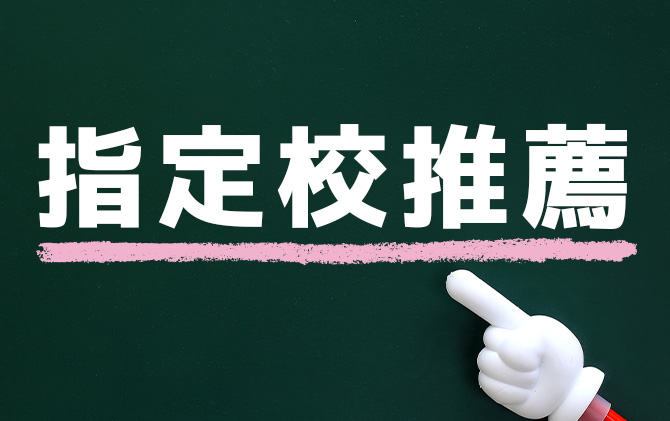
指定校推薦は「大学が定めた指定校の生徒だけ」が出願できる試験制度です。
大学側は今までの進学実績に応じて高校を指定するので、自分が通っている高校が指定されていないと、どれだけ成績が優秀でも出願できません。
併せて、募集枠は1つの高校から1~3人程度が大半。まずは募集枠に入るための校内選考を通過することが第1条件ですが、出願条件がかなり厳しいため「狭き門」といわれています。
公募推薦
公募推薦は、大学が求める出願条件を満たした上で学校長の推薦があれば出願できる試験形式です。
公募推薦には、「一般選抜」・「特別推薦選抜」という2種類の選抜方法があります。前者の一般選抜は成績基準が設定されていることが多く、募集定員が比較的多い選抜方式です。
一方の特別推薦選抜は、スポーツや芸術活動で優秀な成績を収めたことや委員会活動やボランティア、または地域活動などに真摯に取り組んだことがアピールできる選抜方式です。
公募推薦は全国各地の高校から広く出願可能。また既卒生(浪人生)の出願も可能にしている大学もあるので、浪人生でも受験が認められるケースもあります。
ただし大学の中には、専門学校や総合学科高校出身者の定員枠を設けていたり、非常に高い成績基準を設定したりしている場合もあります。そのため公募推薦の利用を考えている場合は、出願前に出願条件をしっかりとチェックしましょう。
公募推薦をはじめとした推薦入試と総合型選抜(旧AO入試)の違いについては以下のページでもまとめているので、参考にしてください。
⇒推薦入試と総合型選抜(旧AO入試)の違いを大公開
一般選抜

一般選抜は「学力一発勝負」の受験方法。大学入試では最も定番の選抜方法です。
多くの受験生が一般入試を経験するので、受験までに入学に必要な学力を身につけておくことが必要です。
国語・数学・英語などの主要科目を、筆記試験またはマークシート方式で問題を解くのが基本。高校で勉強した知識を入試時に問われます。
ただし一般入試の方法は国公立大・私立大で大きく異なるので注意が必要です。
⇒一般選抜と総合型選抜(旧AO入試)はどちらが難しいのか?
共通テスト利用方式入試(共通テストのスコアで出願できる入試)
なお私立大学の一般選抜では、共通テストの成績で合否判定する方式を取っているところもあります。これが「共通テスト利用方式入試」です。
共通テスト利用入試は、「単独型」と「併用型」の2パターン。試験科目や配点比率は大学・学部学科により異なります。
<単独型>
「単独型」は大学入学共通テストの成績だけで合否が決定します。併用型に比べて導入している学校の割合が多めです。
<併用型>
「併用型」では、大学入学共通テストに加えて個別試験が課され、それらの両方の結果で評価します。
合計点で判断する場合もあれば、点数の高い方を採用する場合もあり、評価方法は大学によってまちまちです。
5種類の受験形態を比較してみる

先程ご紹介した総合型選抜(旧AO入試)を含めた大学受験における主な5種類の受験形態をまとめてみました。
| 総合型選抜(旧AO入試) | |
|---|---|
| 特徴 | 対策すべきこと |
| ・学力だけで判断されない
・審査書類の提出が必要 ・面接がほぼ必須 |
・プレゼンテーション
・出願書類の準備 ・面接練習 ・小論文の対策 |
| 指定校推薦 | |
| 特徴 | 対策すべきこと |
| ・所属する高校に募集枠がある大学しか受けられない
・募集枠が少なく出願基準も厳しい |
・厳しい出願基準をクリアするための対策が必須 |
| 公募推薦 | |
| 特徴 | 対策すべきこと |
| ・学校長の推薦が必要
・既卒生(浪人生)の出願を可としている大学もある ・一般選抜は募集定員が比較的多く、特別推薦選抜はスポーツや文化活動などをアピールできる |
・学校長から推薦を受けるため、日頃から勉強やクラブ活動などに積極的に参加すること |
| 一般受験 | |
| 特徴 | 対策すべきこと |
|
・学力で合否が判断される
・高校で学習した知識が入試で問われる ・国公立大と私立大で受験内容が大きく異なる場合もある。 ・共通テストのスコアで出願できる「共通テスト利用方式」を導入している私立大学もある |
・日頃からしっかり勉強して高得点が取れるように対策する |
他の受験方式と比較した上での総合型選抜(旧AO入試)のメリット

次に先程の比較を用いた総合型選抜(旧AO入試)のメリットを5つご紹介します。
学力に自信がない人でも大学に入学ができる
学力だけで判断されない総合型選抜(旧AO入試)は、学力に自信がない受験生でも大学に合格ができるチャンスがあります。
というのも総合型選抜(AO入試)は合否の評価項目の中には学力以外のポイントも数多くあり、学力の不足分を他の評価項目でカバーできる可能性があるためです。特に、
- 高校時代は部活に全てを捧げてきた
- 文章力なら誰にも負けない
- 人前で話すことが全く苦しくない
など、学力以外でアピールできるポイントがある受験生にとっては、総合型選抜(旧AO入試)は非常に大きなチャンスといえるでしょう。
模試の偏差値や判定以上の大学に入学するチャンスがある
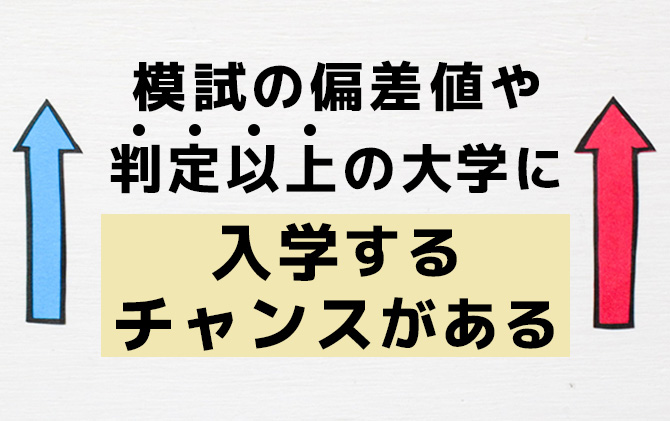
総合型選抜(旧AO入試)なら、模試の偏差値や判定以上の大学に入学できる可能性があります。
総合型選抜(旧AO入試)は学力だけで合否が決まらず、小論文や面接、活動報告書等の総合的な結果から合否判定が出るためです。
面接や小論文、日頃の活動において高い評価を受ければ、不足していた学力をカバーすることも可能です。特に、
- 今の学力では入学できないけど面接に自信がある
- 誰にも書けない濃密な小論文が書ける
といった得意分野を持っている場合は、総合型選抜(旧AO入試)は積極的に利用するとよいでしょう。
ただし基礎学力が求められることが多い
総合型選抜では、大学が定める「アドミッション・ポリシー」に当てはまる人物を選考します。
例えば神戸大学文学部では、アドミッションポリシーとして「基礎学力」を掲げています。
- みずみずしい感受性と想像力を持っている学生
〔求める要素:思考力・判断力・表現力、関心・意欲〕- 言葉や文化、人間の行動、歴史や社会に対する幅広い関心と好奇心を持っている学生
〔求める要素:知識・技能、思考力・判断力・表現力、関心・意欲〕- 基礎学力、とりわけ論理的思考力、日本語および外国語の読解力・表現力、情報リテラシーをそなえている学生
〔求める要素:知識・技能、思考力・判断力・表現力〕- 既成の価値観にとらわれることなく、自分で問題を発見し、探求していくことができる学生
〔求める要素:思考力・判断力・表現力、主体性・協働性、関心・意欲〕
※神戸大学が求める学生像 (アドミッション・ポリシー) [学部]より引用
また帝京大学においては「基礎能力適性検査」を実施していて、小論文や面接に加えて1〜3科目の学科試験が実施されています。(試験科目は学部によって異なる)
このようなことから、総合型選抜学力(旧AO入試)では学力は重視されないものの、「基礎的な学力」を求められることは多いと考えておいた方がよいでしょう。
指定校推薦と違って評定が低くても受けられる
総合型選抜(旧AO入試)は、指定校推薦と違って評定が低くても受験できるケースが多いとされています。
総合型選抜(旧AO入試)は、出願する強い意志がある、入学を希望する大学が設定する理想の学生像に近い場合に受験できる選抜方式であるためです。
- 「評定が基準に達しているか微妙だけど受験したい」
- 「少しでも入学できる可能性があるなら挑戦したい」
といった考えを持つ受験生にとって、総合型選抜(旧AO入試)は追い風になるでしょう。
しかし大学や学部によって、評定平均値の基準を定めている・いないが異なります。志望大学の募集要項を必ず見て、評定平均が出願条件に入っているかどうかをチェックしてください。
課外活動や部活の頑張りをアピールできる
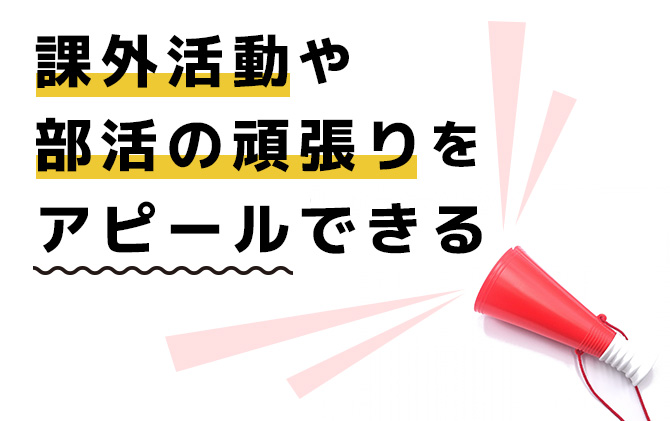
総合型選抜(旧AO入試)は学力だけでは合否が決まらないため、課外活動や部活の頑張りを堂々とアピールできます。
特に、
- 「留学して語学向上に努めてきた」
- 「ボランティア活動を頑張ってきた」
といった形で一芸に秀でた受験生は、総合型選抜(旧AO入試)での受験を活用するとよいでしょう。
倍率が低め
総合型選抜(旧AO入試)は一般選抜に比べると倍率が低めです。
以下の表では、複数の私立大学の一般選抜と総合型選抜(旧AO入試)の倍率を比較してみました。
<2023年度入試結果>
| 大学(学部・学科) | 一般選抜倍率 | 総合型選抜倍率 |
|---|---|---|
| 帝京大学経済学部経済学科 | 1.4 | 3.0 |
| 駒澤大学文学部英米文学科 | 3.7 | 1.4 |
| 東海大学文学部文明学科 | 1.8 | 1.2 |
| 明治学院大学心理学部心理学科 | 10.5 | 5.2 |
参照元:「2023年度入試結果」帝京大学、「前年度(2023年度)入学者選抜データ」駒澤大学、「2023年度 一般選抜」東海大学、「 2023年度 総合型選抜 学科課題型 2023.4.25改訂」東海大学、「全学部日程【3教科型】 データ[過去3ヵ年]」明治学院大学、「自己推薦AO入学試験データ[過去3ヵ年]」明治学院大学
総合型選抜(旧AO入試)の倍率が低い大学が多いですが、なかには競争率が高い大学もあります。
年内に受験から解放される

総合型選抜(旧AO入試)は出願期間が早いので、年内に受験から解放されるのもメリットのひとつです。早い大学では6月から出願が始まります。
加えて大学によっては8月の頭には出願を締め切り、9月中に選考を進めるケースも。選考スケジュールが早いため、10月末~年明けにかけて合格発表が行なわれます。
以下は駒澤大学の総合型選抜(旧AO入試)の試験日程です。
<2025年度入試>
| 出願期間 | 9/27〜10/4 |
|---|---|
| 試験日 | 10/20 |
| 合格発表日 | 11/8 |
無事に合格を勝ち取れば、年内には辛い受験から解放されます。総合型選抜(旧AO入試)のスケジュール感については理想的な対策時期と併せて以下のページでまとめています。
⇒理想的な対策時期と大まかなスケジュールを大公開
合格のチャンスが広がる
試験日程が早いので、万が一総合型選抜(旧AO入試)に落ちた場合でも受験のチャンスがまだあります。
落ちた場合は、一般選抜へ切り替える、もしくは他の総合型選抜(旧AO入試)を受験するなどしましょう。
また併願するのもひとつの手です。併願可能な大学を選んで総合型選抜で受験することで、合格のチャンスを広げられます。
就職活動につなげられる

就職活動で陥りがちなのが、「自分は一体何がやりたいのか」です。
しかし総合型選抜を受験している人であれば、高校生の段階で自分の将来ややりたいことについて考えるため、就職活動のタイミングで改めて考えたり悩んだりすることが少ないでしょう。
他の形式との比較で分かるデメリット

ここでは、総合型選抜(旧AO入試)のデメリットを4つご紹介します。
正解がないので対策が難しい
総合型選抜(旧AO入試)では、一般入試のような過去問題がほとんど販売されていないため対策が難しいとされています。
加えて、総合型選抜(旧AO入試)に確実に合格する対策が取りにくい側面も。総合型選抜(旧AO入試)の合否が、各受験生のこれまでの高校生活の過ごし方や当日の面接官との相性で決まる要素が多分にあるためです。
なお、一般選抜入試のような明確な合格基準がない総合型選抜(旧AO入試)に合格するためには、塾に通う事も有効な選択の1つです。
総合型選抜(旧AO入試)に特化した塾であれば、対策の仕方を教えてもらえます。個別指導の塾なら個々に合わせて対策してもらえるので、自分がやるべきことが具体的に分かるでしょう。
一般受験の勉強に割ける時間が減る
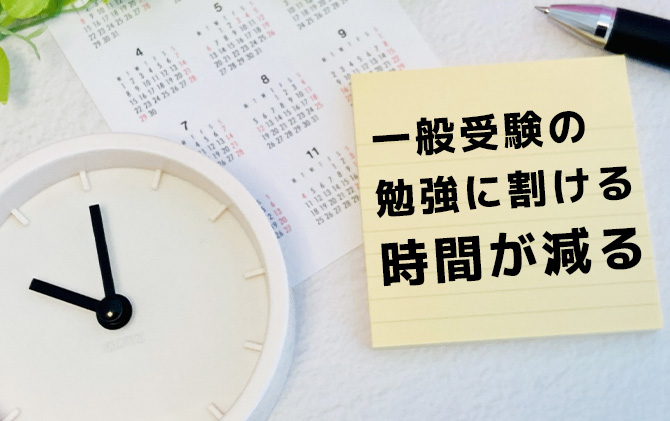
総合型選抜(旧AO入試)を受けた場合は、一般受験の合格率が明らかに下がります。
面接対策や志望理由書の準備には意外に時間がかかるもの。その分一般受験への対策に遅れが生じるのです。
また総合型選抜(旧AO入試)の対策は、一般選抜に活かせない小論文や面接といった試験内容であるケースがほとんどです。
そのため総合型選抜に絞って対策していると、万が一落ちた時に一般選抜に切り替えようと思っても、一般選抜に絞って対策していた人との差が出てしまいます。
総合型選抜(旧AO入試)のみで受験する場合は問題ありませんが、一般選抜と並行して対策する場合は、準備と勉強のバランスを意識したスケジュール調整が欠かせません。
学校によっては専願受験が求められる
総合型選抜(旧AO入試)においては、併願可能な大学が多く見られます。しかし中には専願を求めている大学があるので、募集要項を注意して見ることが大切です。
受験校を選ぶ際は、募集要項に以下のような記載がないか確認してください。
- 「専願」
- 「他大学の受験不可」
そもそも併願とは、「他の大学に出願すること」を意味しています。募集要項に「合格後の辞退ができない」と書かれていた場合であっても、合格して入学さえすれば、他大学に出願しても問題ありません。
入学後に苦労することが実は多い
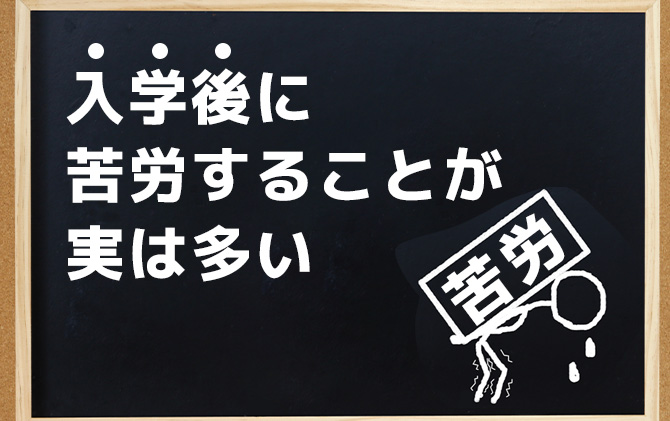
総合型選抜(旧AO入試)は、運よく合格した後に苦労することが実は多いです。
総合型選抜(旧AO入試)で模試の偏差値や判定以上の大学に合格してしまうと、カリキュラムに付いて行けず学力不足に陥ることも。そうなると入学後の勉強に苦労してしまいます。
大学入学だけがゴールではありません。入学後に苦労しないためにも、合格したからといって何もしないのではなく、高校の授業内容の復習や一般選抜の対策をする、といった学力の差を埋める努力をしましょう。
向いている人と向いていない人について
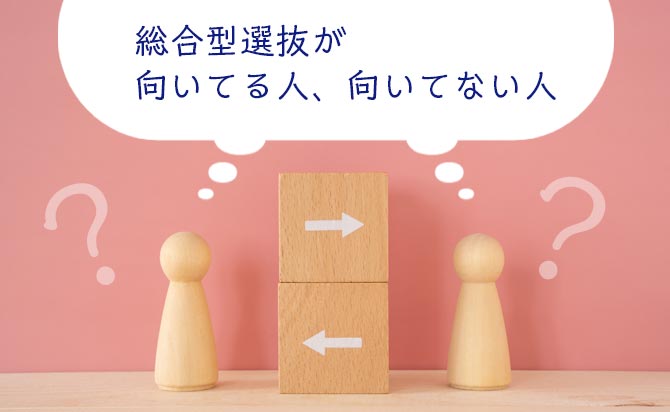
ここまで総合型選抜(旧AO入試)の特徴やメリットデメリットをご紹介してきました。ここからは、総合型選抜(旧AO入試)に向いている人・向いていない人をご紹介します。
| 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|
| 〇「この大学で勉強したい」と熱意を持っている人 〇クラブ活動や課外活動など勉強以外の分野を頑張った人 〇語学など高等学校以上のレベルを有している人 |
▲自分の気持ちを言語化できない人 ▲将来について明確なビジョンがない人 ▲強い興味や関心を持っていない人 |
総合型選抜に向いている人と向いていない人のより詳しい詳細について、以下でそれぞれ紹介します。
向いている人
実は総合型選抜(旧AO入試)に向いている人には、意思が強いという一面が共通しています。特に、
- 「入学したい大学には学びたい分野があるので、是が非でも入学したい」
- 「将来は○○になりたいので、ぜひ大学で学びたい」
といった形で志望大学で学びたい強い意志がある人は、総合型選抜(旧AO入試)に向いています。また大学側も熱意を持った受験生に入学してほしいので、相思相愛になれば入学にグッと近づけるでしょう。
向いていない人
総合型選抜(旧AO入試)に向いていない人は、自分の気持ちがよく分かっていない、大学入学後のプランが定まっていない、という共通点が見られます。
よくあるケースとしては、
- 「やりたいことはないけど大学には行きたい」
- 「学力には自信がないけど大学に合格したい」
などです。
前向きな姿勢ではない人には、総合型選抜(旧AO入試)は不向きといえるでしょう。
一般入試との併願について

次に総合型選抜(旧AO入試)は一般入試との併願についてご紹介します。
併願は可能である
結論からいうと、総合型選抜(旧AO入試)と一般入試は併願可能です。なぜなら総合型選抜で合格を勝ち取れば一般入試の受験をしなければよく、また不合格ならば専願のルールも適用されないためです。
総合型選抜(旧AO入試)で合格できなかった場合は、求められる学力を身につけた上で、一般入試にチャレンジしてみましょう。
安易な併願はリスクもある
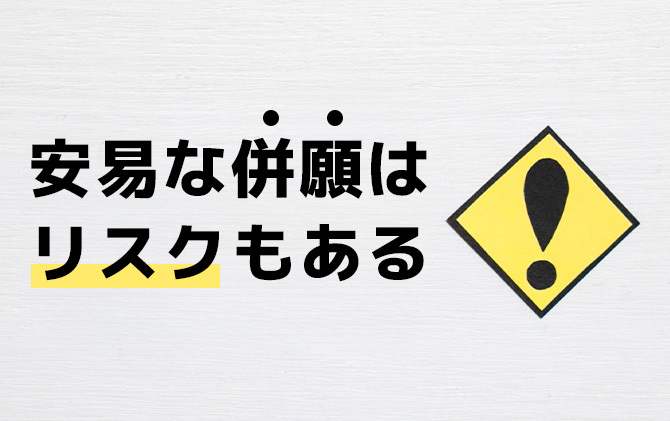
総合型選抜(旧AO入試)と一般入試は併願できますが、安易な併願はリスクもあります。
なぜなら総合型選抜(旧AO入試)対策と一般入試対策は全くの別物だからです。
一般入試の場合は学力だけで合否が決まる試験。そのため、総合型選抜で合格を勝ち取るための出願書類の作成などの努力は、基本的には一般入試の役には立ちません。
あまり深く考えず両方の対策をしてしまうと、どちらの試験の準備にも十分な力を注ぎこめず、両方とも中途半端な対策になってしまう恐れがあります。
軸足をどちらかに置くのが無難
総合型選抜(旧AO入試)と一般入試のどちらかに軸足を置くのが無難な判断です。
そしてどちらに軸足を置くかを考える際に重要になるのは、自分自身と受験形式との相性。併願受験ができるとはいえ自分との受験形式との相性を考え、どちらに軸足を置くかを明確にした上で対策を進めていく方が合格率が上がります。
英語が得意・学力に自信がある受験生は一般選抜に軸足を置く
特別な活動をしておらず学力に自信がある人は、一般選抜に比重を置くのが向いています。
また英語ができる・得意な場合は、総合型選抜でも一般選抜でも有利。英検やTOEIC®などの検定試験結果に応じて、英語の試験の免除や点数の加算が行われる場合があるためです。
平日は一般選抜の対策、土日は総合型選抜の対策などと、一般選抜に重きを置いたスケジュールで対策を進めるのもよいでしょう。
クラブ活動や部活動に力を入れている人は総合型選抜に軸足を置く
クラブ活動や部活動、特にスポーツに力を入れていた人は総合型選抜で有利です。特に「スポーツ枠」が狙い目。小論文や面接で合否判定されることが多い傾向にあります。
そのため併願する一般選抜の大学として小論文を取り入れているところを選ぶと、総合型選抜の対策を活かせるでしょう。
理系の大学・学部を志望する人は一般選抜に軸足を置く
そもそも理系を志望する場合は、学力が重視される傾向にあります。中学高校で習う理系科目の基礎がしっかり身についているかどうかが大切です。
そして理系の場合は、総合型選抜の枠がそもそも少なめです。そのため一般選抜メインで進め、総合型選抜で募集があるところにも出願してみるのがよいでしょう。
参考記事:理系の総合型選抜の特集ページはこちら
まとめ:総合型選抜(旧AO入試)はリスクもあるがチャンスが大きい
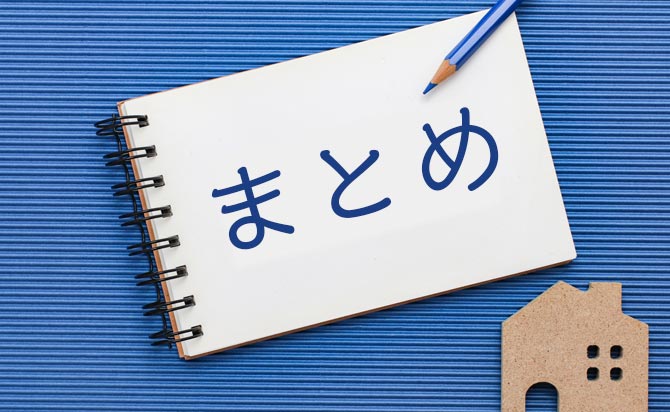
今回は、総合型選抜(旧AO入試)について他の入試形式との違いやメリットやデメリットなどについてご紹介してきました。以下は、ここまでの内容の中で特に重要な点を一覧にしたものです。
特に重要なポイント一覧
- 総合型選抜(旧AO入試)は大学側と受験生との適性を図る試験形態
- 学力に自信がない受験生にとって総合型選抜(旧AO入試)は便利
- クラブ活動など勉強以外でもアピールできる
- 明確な合格基準はない
- 一般入試との併願可能
- 安易な併願はリスクも伴う
改めての話になりますが、総合型選抜(旧AO入試)は面接や小論文などが実施され、学力だけで合否は決まりません。
そのため基礎学力に不安を持っている、もしくは学力以外のポイントをアピールしたい受験生にとって合格のチャンスといえるでしょう。
一般入試と違って明確な合格基準がないのは悩みどころですが、非常にチャンスが大きな入試形態であることは間違いありません。
もしここまでの内容に目を通す中で総合型選抜(旧AO入試)に関心を持った場合は、ぜひ積極的に利用を検討することをおすすめします。
この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。
過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。
昨年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。
総合型選抜と公募推薦の対策ガイドを無料でプレゼント
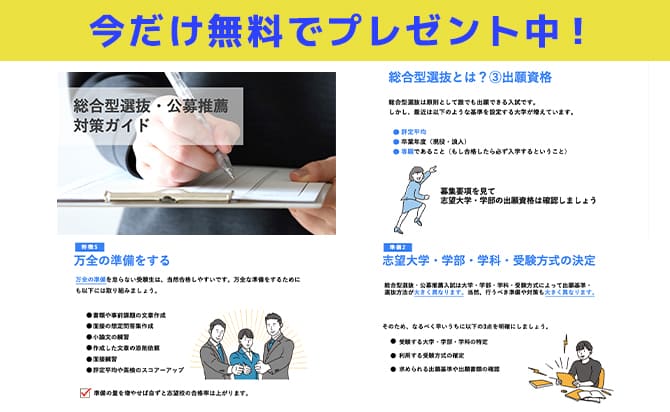
「総合型選抜や公募推薦の利用を考えているけど、何をすれば良いか分からない・・・・」 といった高校生や高校生の親御様のお役に立てればと思い、総合型選抜と公募推薦の対策ガイドを作成しました。
今だけ無料でプレゼントをしているのでぜひお受け取り下さいませ。↓