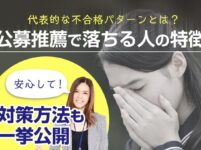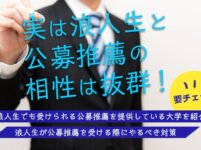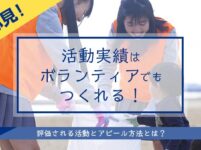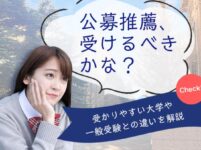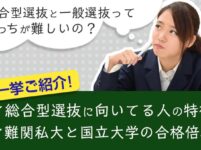BLOG

大学受験の学校推薦型選抜や総合型選抜では一部の大学で口頭試問が採用されています。
口頭試問は総合型選抜や学校推薦型選抜の合否項目の一つであるため、一人ひとりが志望校に適した対策を行うことが必要です。
しかし口頭試問の概要や対策の仕方について、よくわからない受験生は少なくありません。
そこで今回は、口頭試問がどのような試験でどのように対策をすればよいのかについて解説します。最後まで目を通せば入試本番に試験会場で面接官にチェックされるポイントやよく聞かれる質問の種類や答え方のポイントまでわかります。
この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。
自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。
高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。
倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。
目次
そもそも口頭試問とは?

口頭試問とは学部・学科に関する専門知識の有無や理解度を口頭で問う形の質問のことを指します。
志望動機や自己PRといった決まりきった質問ではなく、志望の学部・学科に沿った専門的な知識が問われるのが特徴です。
そのため、志望する学部・学科に関連した基礎知識の習得に加えて、聞かれた内容に対して論理的な説明をするための論理的思考力や伝達能力が求められます。
口頭試問の出題形式
上記のような特徴を持つ口頭試問で問われる出題形式の一例としては以下のようなものがあります。
-
面接(口頭試問)もしくは口頭試問(面接)
口頭試問の時間
口頭試問の時間は大学によって異なりますが10〜15分のところが多く見られます。しかしなかには、質疑応答を含めて1時間近く行うところもあるようです。
面接との違いとは?
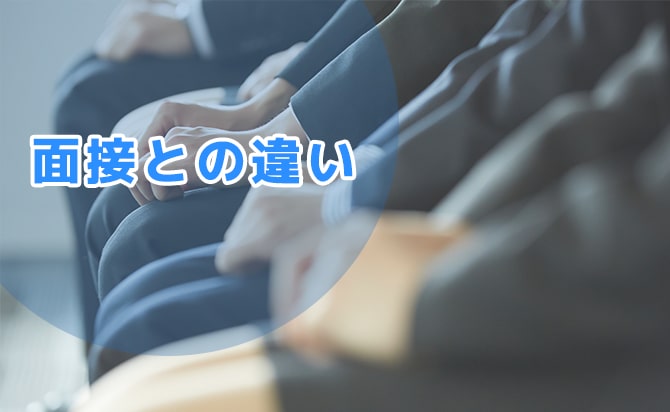
面接と口頭試問は、口頭で試験官からの質問に答える選考であることから、混同する人が少なくありません。以下では両者の違いを簡単に解説します。
まず面接は自己PRや志望動機などが問われるものであり、面接官は受験生の話し方や雰囲気、考えなどの人となりを見ています。
一方で口頭試問は、専門分野に関する知識の有無や自分の意見が問われるものです。そのため、大学で学ぶ分野への学習意欲や理解力が受験生にあるのか、また論理的に話せるかなどが見られます。
つまり口頭試問と面接では、見られているポイントが明らかに異なるのです。
そのため入学後に学ぶ分野についての知識や、自分なりの考えをしっかり持ち、論理的な話し方を身に付けることが重要といえるでしょう。
また、「大学入学後に意欲的に学習してくれるだろう」と期待を抱かせることも大切です。
口頭試問で評価されるポイント
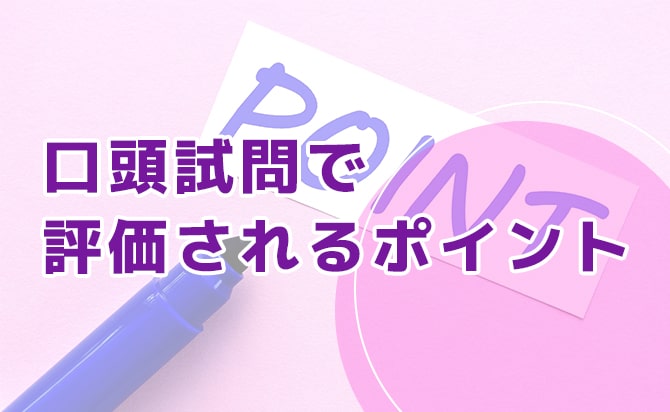
次に口頭試問で主に評価される4つのポイントをご紹介します。
学習意欲や情報感度の高さ
口頭試問では受験生の学習意欲や情報感度の高さは必ず見られます。そのため、学習意欲がないと答えられない以下のような質問がほとんどです。
- 学部・学科で学ぶ○○に関してどの程度知識がありますか?
- ○○という事柄に対してどのような問題意識を持っていますか?
- ○○という問題を改善するためにはどんな解決策があると思いますか?
上記のような質問に対しては、きちんとした学習意欲がないと答えることは難しいもの。「口頭試問では、質問を通して学習意欲の高さが見られている」といった点を理解しておきましょう。
また、高い学習意欲を持っていることを大学側に示すためにも、学部・学科で学ぶ内容と関連しているニュースなどの情報を日常的に集めることも意識してみてください。
そして集めた情報に対して、自分なりの問題点や解決策を考えることを習慣化するとよいでしょう。
受験生の基礎学力

口頭試問では、大学での学びや研究に必要な学力があるかどうかも見られるでしょう。
例えば英語力が求められる学部の場合は語学力を問う質問、理系の学部では数学力を問う質問をされることがあります。
以下は例題の一つです。
- a+b=1の時にabの最大値って何だと思いますか?
- この英文を音読した上で日本語に訳してもらえませんか?
ただし質問は口頭でされるため、それほど難易度の高い問題が出題されることはありません。
学部・学科に必要な教科の参考書や教科書、基本的な関連書籍等を読めば、求められる知識を補えるでしょう。
まずは過去問や募集要項を確認し、どのような出題傾向があるのか分析することが大切です。出題傾向がわかったら、求められる内容の学習に取り組みましょう。
論理的な思考力・伝達能力
口頭試問では、ただ無難に答える、いいたいことを述べればいいというわけではありません。
質問に対する結論に加えて結論を裏付ける根拠や理由、また、自分の伝えたいことをわかりやすく簡潔に伝える力が求められます。
また大学や学部によっては、プレゼンテーションや黒板を使って説明しなければいけないケースもあります。
そのため質問に対する答えが正解かどうかよりも、回答にいたるまでを論理的に説明できるかが重要になるといえるでしょう。
答え方の態度を通しての人となり
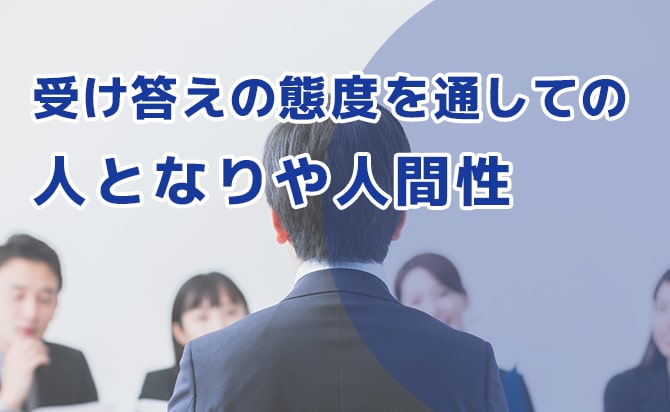
総合型選抜や公募推薦で行われる口頭試問ではあなたの受け答えの態度を通して人となりも見られます。
なぜなら話し方や表情などからは、受験生の性格や醸し出す雰囲気が垣間見えるためです。緊張したり自信がなかったりしても、最後まで堂々話しましょう。
また明るい表情やはっきりと落ち着いた話し方を心がけることも大切です。
柔軟な受け答え
面接官がその時に突然質問をしてくる場合も考えられます。突然出された質問に対しても柔軟に受け答えする力があれば、好印象を与えられるでしょう。
自分が話す内容をまとめておくのもよいですが、その時に自分の言葉で伝えたいことを話すのも大切です。
口頭試問でよく聞かれる4種類の質問
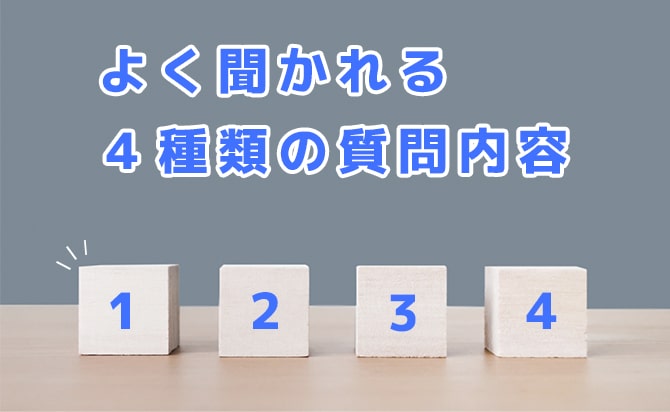
次に口頭試問の場でよく聞かれる4種類の質問をご紹介しますのでぜひご覧ください。
気になるニュースに関する質問
口頭試問の場では「最近の気になるニュース」を聞かれるケースがあります。基本的な質問の形式としては、以下の通りです。
- 気になっているニュースを聞かれる
- あなたが気になったニュースの内容を答える
- 答えたニュースに対してどのような意見を持っているか等の深掘り
持ち出すニュースは、自分の志望学部と関係のあるものにするのがおすすめです。そうすることで、自分の興味ややる気を面接官に見せられます。
一方面接官は「気になるニュース」を確認することで、受験生がどのようなことに興味があり、関心のある事柄についてどれだけ勉強しているかを確認します。
また受験生の回答を通して、しっかりとした考えを持っているのかについても判断するでしょう。
そのためその事柄について勉強して理解を深めた上で、自分なりの考えを持つことが必要です。
試験当日、自分の考えを裏付ける論文や本などを使いながら説明できるとより良い解答になるでしょう。
なおニュースに対する考えをいったつもりが、「ただの感想になってしまった」といったことのないように注意しましょう。
一般教養を問う質問
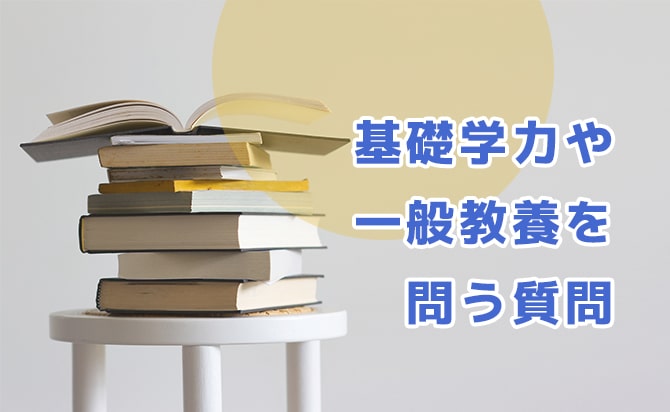
一般教養を確認する質問もされる場合があります。一例としては以下のようなものです。
- ボイルの法則について簡潔にご説明ください。
- 消費税が上がるとどうなると思いますか?
- 日本国憲法の3大原則ってご存じですか?
- ソ連が崩壊した原因をご説明ください。
- 少子化って何が問題だと思いますか?
聞かれる質問は志望する学部・学科によって異なります。
まずは募集要項をよく読み、どんな内容が問われるのかを把握しましょう。また可能であれば、先生や進学した先輩に相談しながら情報収集に取り組むとよいでしょう。
問われる内容がわかった後は、専門書を読んだりインターネットで調べたりして、知識を増やしてください。
基礎学力に関する質問
高校で学ぶ5教科に関する質問をされる場合があります。
基本的な問題である場合がほとんど。国文系の学部なら国語、物理系の学部であれば理科…など、志望する大学の受験科目について勉強しておけばOKです。
基本的には、教科書に書かれているような問題が回答できればよいですが、ときどき応用問題が出されることもあるので注意が必要です。
また数Ⅲまでが必要な学部の場合は、計算問題が出るケースが多く見られます。正しい答えを導き出せているかはもちろん、論理的に説明できているかもチェックされます。
以下では科目によって出される内容について簡単にまとめました。
数学
数学は、一般的に理系の学部で出題されることが多いもの。
ホワイトボードや黒板などを使いながら問題を解答する、という形式の口頭試問が一般的です。
一例としては以下の通りです。
- この数式の解答を黒板に書いてもらえないかな?
- ヤング係数について説明してもらえませんか?
質問内容に答えられるだけの学力に加えて、端的に説明するプレゼンテーション能力も求められます。
そのため過去問や募集要項をよく読み、まずは求められる知識を押さえましょう。求められる知識がわかった後は知識の習得に加えて、他人に簡潔に説明する練習に取り組むのがおすすめです。
国語
国語は質問の幅が広い傾向にあります。以下がその一例です。
- 文章を読んで質問に回答する
- 著名な作家の文学作品に関する質問、文学史など
- 漢字や四字熟語といった語彙力の確認
一般的な国語の問題がまとめられた問題集で対策するとよいでしょう。
英語
英語で出される質問例は以下の通りです。
- 英語での質問に英語で答える
- 英文の音読
- 英訳・和訳
- 英語での自己紹介やPR
口頭試問自体、すべて英語でやりとりされる場合もあります。文脈やニュアンスを意識して、相手に伝わるような翻訳を心がけましょう。
また英語の語学力はもちろんのこと、自分の意見を論理的に伝える力も求められることがあります。
そのため学部・学科に関する分野の基礎知識を学び、「なぜそう思うのか」といった理由も含めて、簡潔に英語で話せるように練習するとよいでしょう。
参考記事:推薦入試や総合型選抜における英検の重要性
社会(日本史・世界史・政治経済)
歴史で聞かれる質問内容の一例は以下の通りです。
- 出来事が起こった経緯や背景
- 歴史上の人物に関する質問
経済学部や法学部では政治経済に関する質問が出される場合もあります。
理科
理科は数学と同様、ホワイトボードを使って説明させるケースが多く見られます。公式・定理を理解しているか・論理的に説明できるか、などがチェックされるでしょう。
なかには、実験の方法やデータ分析にまつわる質問をされるケースもあります。
岩手大学理工学部の令和5年度の口頭試問においては、以下のような問題が出されたようです。
混合物の分離について出題した。
原子の構成粒子について出題した。
電子配置とイオン,周期表について出題した。
分子の極性について出題した。
化学式と物質量について出題した。
化学反応の量的関係について出題した。
中和反応の量的関係について出題した。
塩の水溶液の性質について出題した。
酸化還元反応と酸化数について出題した。
※岩手大学より引用
大学入学後の生活に関する質問
上記のほかにも、「大学に入ったら何を学びたいか」「やりたいことは何か」といった質問がされる場合もあります。
受験生が、大学入学後の自分について具体的にイメージできているか、また大学でしっかり学びたいという意欲があるかを評価するでしょう。
【学部別】口頭試問の例題・内容
受験する学部によっても質問される内容がまちまちです。以下ではいくつかの学部をピックアップし、質問内容の例を挙げました。
教育学部
- 教育において大切なことは何か
- どのような子どもを育てたいと思うか
- 特定の年齢の乳幼児に対する表現力についての問題
- 子どものいじめ、貧困にまつわること
- 教育において大切なこと
- 生きる力とは何か など
理工学部
- 微分などの公式を使った問題
- 高校で習得した理科・数学の基礎
- 特定の実験に関する内容や基礎的な知識など
- 生物の基礎内容
参照元:岩手大学
農学部
- SDGs
- 環境に対する考え方
- 化学・生物学の基礎学力を問うもの
理学部
- 物理・化学・生物の基礎問題
- 自由落下する物体の運動について
- 日本のバイオームの水平分布について
法学部
- リーガルマインドとは何か
- 法律とは何か
- グローバル化が進む中で生じている、法による統治の矛盾
医学部
- 患者へのインフォームドコンセント
薬学部
- 化学基礎、生物基礎、物理基礎に関する質問
- 数学(関数とグラフ,指数対数)
- 化学(分子の構造と性質,mol 計算)
本番日に高評価をもらうために行いたい5つの対策

口頭試問で高評価をもらうためには、他の科目と同じようにしっかりと対策する必要があります。ここからは口頭試問の対策として行っておきたい5つの対策内容をご紹介します。
志望大学・志望学部の出題内容を調べる
一口に口頭試問といっても出題される内容は志望大学・志望学部・志望学科によってまちまちです。
志望する大学・学部・学科で問われる質問項目の概要については、募集要項に書かれています。
募集要項でよく見られる記述例としては、「当日は○○に対する理解度について確認をする」「○○に関する理解力を確認することを目的に行う」といったものです。
そのため志望大学・学部の募集要項をよく読み、どのようなことを問われるのかを把握しましょう。
また学校の先生や通っている塾の先生に、これまでの出題傾向を尋ねるのも一つです。
過去に聞かれた内容・過去問などの情報収集をする
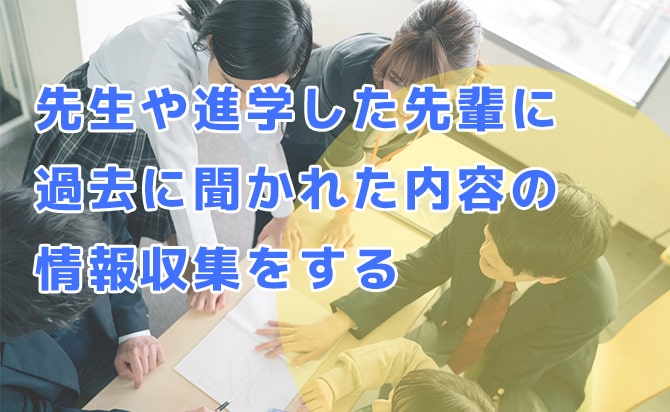
志望大学・学部の口頭試問で問われる内容を知りたければ、学校の先生や塾の先生に相談をするのが有効。
なぜなら学校や塾では、過去に口頭試問を受けた生徒がいた場合、報告書を記録しているケースが少なくないためです。
自分自身で過去問を探してみるのもよいでしょう。もし志望大学の過去問が見つからなければ、他校のものでも構いません。
SNSなどを利用して、進学した先輩と連絡を取ってみるのもおすすめです。連絡が取れれば個別に相談できます。
そのほか、オープンキャンパスの参加も有効です。オープンキャンパスに参加すると、大学の先生や先輩方から有益な情報や学習方法、受験時の体験談といった生の情報を手に入れられます。
オープンキャンパスに参加する際に意識しておきたいポイントや当日の心得については以下のページでまとめております。
問われるであろう分野の基本知識を押さえる・理解を深める
口頭試問で問われる分野がわかった後は、専門書や新書、論文を読むことをおすすめします。なぜなら、口頭試問対策に必要不可欠な基礎知識が身に付くためです。
ただし本を読みなれていない人や受験勉強を始めたばかりの人は、専門書や論文を読むのが難しいと感じるかもしれません。その場合はまずは新書から読むのがおすすめです。
新書は専門書に比べて薄く、価格も低め。また幅広い年代を読者対象にしているため、比較的読みやすいものが多いです。
まずは目指す分野の新書を何冊か読み、専門用語や基礎知識を身に付けましょう。その上で関心のある論文や専門書も読み、無理なく知識量を増やすのが理想的です。
また、志望する学部に必要とされる知識を伸ばすことも考えましょう。ただし教科書の内容を丸暗記しただけではいけません。
自分の言葉で論理的に話せるようになるまで、内容をしっかり理解することが大切です。
ニュースや時事問題については適宜チェックする
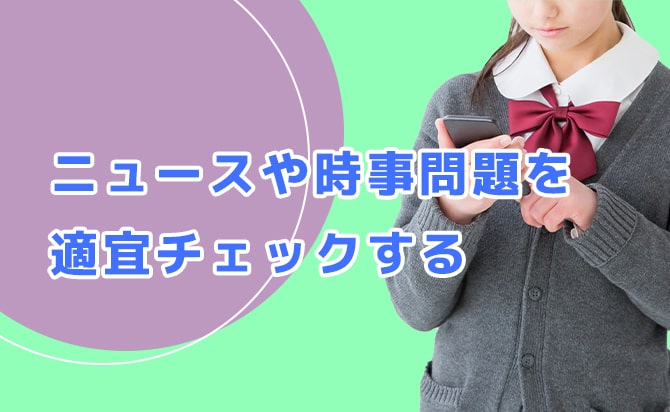
ニュースや時事問題は、口頭試問で聞かれる定番の質問です。
面接官は、受験者が世の中で起こっている事柄を知っているか、またその事柄について自分なりの意見を持っているか、を確認します。
日々の生活の中で、ニュースや新聞にはなるべく目を通すよう意識することが大切です。
ただし、ただ記事を読むだけでは不十分です。目にした話題に関して、自分が賛成か反対かを考えたり、新たな問題提起や解決策を自分の言葉で説明できるようにしたりしましょう。
提出書類の内容を把握しておく
提出した書類の内容から質問されることがあります。その場合に備えて、自分の書いた内容をしっかり把握しておくことが大切です。
提出する前にできればコピーをとっておくとよいでしょう。さらに、自分が出した書類に対してどのような質問がされるかを予測して、回答できるように準備しておくのもポイントです。
事前に本番を想定した練習をする
募集要項や先生・先輩から集めた情報をもとに、予想質問集を作ってみましょう。
作った質問集をもとに、学校の先生をはじめとした信頼できる人に本番を想定した練習を手伝ってもらえば、万全の状態で本番を迎えられるでしょう。
実際に練習をすることで、自分の話し方や表情を客観的に見てもらえ、さらに改善点を指摘してもらえます。
自分の話し方のクセや自分の説明が論理的かどうかは、自分でチェックするのは難しいもの。他人に見てもらう練習は、口頭試問の対策としては非常に有効といえるでしょう。
友達同士で練習を行うのもおすすめ。自分が面接官側に立つことで、受験生の受け答えを客観的に見られるためです。それによって自分が回答する時に注意すべき点を押さえられます。
練習では、話している内容はもちろん、姿勢や表情、動作など気になるところはどんどん指摘してもらいましょう。
練習の際は、ビデオカメラやスマホで撮影しておくのもおすすめです。受け答えしている自分の姿を改めて見られ、普段あまり気にしていなかった話し方や動作のクセに気付けます。
ほとんどの高校では口頭試問の対策授業はありません。そのため口頭試問に対して不安を感じる人も多いでしょう。しかし何度も練習して慣れることで、緊張した状態でもしっかりと受け答えできるようになるはずです。
口頭試問の答え方で配慮するべき5つのポイント
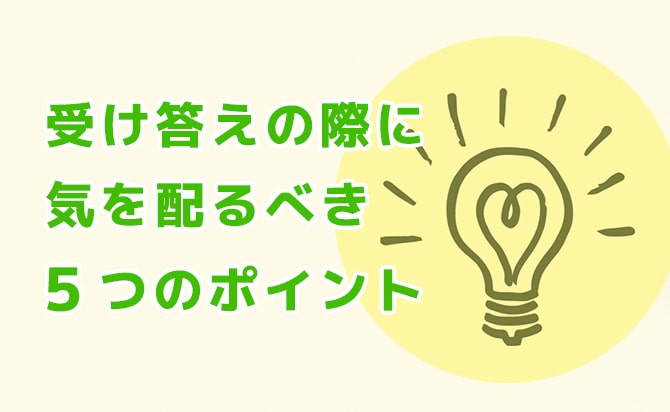
次に口頭試問で受け答えをする際に心がけたい5つのポイントをご紹介しますのでぜひご覧ください。
自分の言葉で伝えるようにする
口頭試問では、回答の正解・不正解よりも、回答にいたる思考プロセスが見られることが多いです。なぜなら、多くの面接官は回答にいたる経緯を確認することで、回答者の論理的な思考力や人間性を確認して大学・学部にマッチするかを判断するためです。
参考書や本の内容をそのまま暗記するのではなく、自分の言葉でわかりやすく伝えるトレーニングをしましょう。
特に避けたいのは難しい言葉を理解せずに使ったり、人の意見をそのままいったりすることです。どちらの場合も「学習意欲がない」と判断され、マイナス評価になる可能性が非常に高いでしょう。
しっかりと知識を蓄えて理解を深め、その上で自分の言葉で説明することが重要です
答えられないことは「わからない」という

口頭試問では学部・学科に特化した内容の質問をされるため、時には高校生では答えるのが難しい難解な質問をされる場合もあります。以下のような質問がその一例です。
- 少子高齢化が起こった根本的な原因とは?
- デフレスパイラルを端的に説明してください。
- 消費税を上げることで起こりえる問題を5個以上上げてください。
上記のような明らかに難解な質問を投げかけられて答えられない場合は、「わからない」と素直に答えたり、言葉の意味を面接官に聞き返したりしましょう。
意味がわからないまま何となくで答えるのは絶対に避けてください。大きく的外れな回答は評価の対象になりません。
ただし質問されているので、すぐに「わからない」と答えるのではなく、しばらく考えてもわからない場合にのみ、「わからない」と答えるようにしましょう。
「わからない」と答えて終わるのではなく、「試験が終わったらしっかり調べます」といった自分がこれからやるべきことに関する内容をいうのもおすすめです。「意欲がある」とみなされ、プラスの印象を与えられる可能性があります
結論から答えるようにする
口頭試問の場で何かを聞かれた場合は、聞かれた問いに対する回答を最初に答えましょう。さらにいえば、結論→そう考える理由や根拠→再び結論という形で答えることが望ましいです。
なぜなら面接官が一番聞きたいのは、質問に対する回答と回答にいたった理由だからです。
高校生は社会経験が少ないため、結論から話す話し方よりも時系列順や起承転結型の話し方が身に付いてしまっている人が多いです。
しかし時系列や起承転結の説明は結論が最後になるので、面接官の質問に端的に答えられておらず、また論理的な話し方になっていません。
なるべくリラックスして落ち着いて話すようにする

本番はどうしても緊張してしまい、早口になることが予想されます。しかし落ち着いてゆっくりと話すように心がけましょう。
リラックスしてゆっくりと話す方が、聞き手は聞き間違いをしません。また自分自身も言葉を選びながら話を進められます。
また面接官は基本的にメモを取りながら話を聞いているため、話し手が早く話しすぎるとメモが追い付かないことも。面接官の書くスピードに合わせること、目を見て話すことを心がけてみてください。
話す内容だけではなく、態度やマナーが見られている
口頭試問では直接面接官と接するため、マナーも非常に重要です。清潔感のある髪型、服装で臨み、しっかりと元気よく挨拶するなど、まずは基本的なことに気を配りましょう。
そして言葉遣いも重要です。高校生は敬語がまだ身に付いていない場合が多く、話し方が難しいと感じるかもしれません。しかし最低限の言葉遣いは意識しましょう。
よい雰囲気の中で口頭試問が進み、「少しの気の緩みからため口で話してしまう」のは言語道断です。一方、言葉遣いばかりを意識しすぎて、他の対策がおろそかにならないようにも気を付ける必要があります。
参考記事:選考当日の髪型や身だしなみの注意点
今回のまとめ
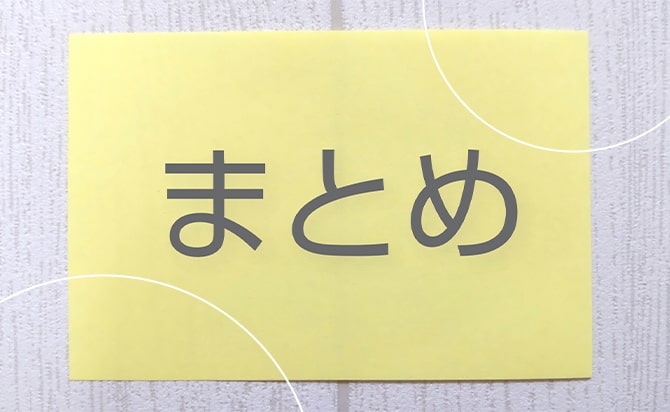
ここまで、口頭試問において面接官から評価されるポイントや対策方法について解説してきました。最後に今回の内容の中で特に重要な点をまとめたのでご覧ください。
特に重要なポイント一覧
- 志望校を決め、募集要項や過去問などをよく確認して出題傾向を掴むことが重要である。
- 先生や進学した先輩などに相談し、体験談や勉強法などを教えてもらう。
- 参考書や関連書籍などを用いながら志望する学科・学部に関する基礎知識を得る。
- 結論から話す論理的な話し方を身に付ける。
- 時事問題やニュースに関して自分の意見も含めて説明できるようにする。
- 本番を想定した練習を繰り返し行う。
- わからないことはわからないと素直にいう。
- 言葉遣いやマナーなどの態度に十分気を付ける。
口頭試問は高校生にとって経験がなく不安に感じる受験方法であるため、緊張してしまう受験生は少なくありません。
しかし逆にいえば全員が同じ状態であるため、十分な準備をして練習を重ねれば他の受験生よりも際立てます。
また口頭試問は筆記試験とは違い、明確な正解があるわけでないので大学側に自分の学習意欲や思いをアピールできる機会です。対策次第では合否判定において大きなアドバンテージを獲得するチャンスになりえます。
ぜひこの記事の内容を参考に何度も口頭試問の練習を重ねてリラックスして当日を迎えてください。
最後に今回の内容と併せて目を通しておきたいページをご紹介します。
⇒大学の特別入試の面接でよく聞かれる質問を大公開
この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。
過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。
昨年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。

ホワイトアカデミー高等部とは?
総合型選抜・公募推薦入試に特化した専門塾。
プロ講師が活動実績作りから小論文・面接まで、
マンツーマンで徹底サポート。
- カリキュラム修了者の合格率98%※1
- 上智大学合格率83%(2025年度)※2
- 小論文・書類すべて添削無制限
- 全授業が社会人のプロ講師による1対1形式
- カリキュラム修了者には合格保証制度を提供

※2 上智大学合格率83%は2025年度入試における上智大学受験者が母数です。