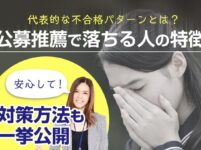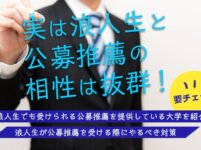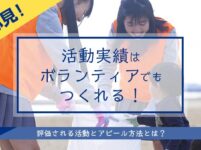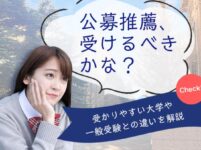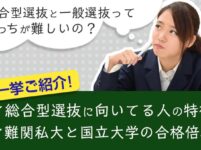BLOG

- 「総合型選抜(旧AO入試)に挑みたいけど実績がない」
- 「総合型選抜(旧AO入試)の活動実績は部活だけ?」
- 「総合型選抜(旧AO入試)の活動実績を増やしたい」
こんなことを思っている受験生も多いと思います。
学力以外の側面も合否材料になる総合型選抜(旧AO入試)は、これまでやってきたことがアピールできる試験形式です。
しかし、総合型選抜(旧AO入試)に臨む上で活動実績がなかったり、実績が十分かどうか不安になる受験生もいるのも事実。
そこで今回は、総合型選抜(旧AO入試)で評価される活動実績や活動実績がない場合の対策方法、活動報告書の正しい書き方等についてご紹介します。
この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。
自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。
高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。
倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。
目次
活動実績が無い人は受けられないのか?受けられるにしても受かるのか?

結論から言えば、総合型選抜(旧AO入試)は活動実績がなくても受験できますし受かる可能性もあります。
なぜなら、総合型選抜(旧AO入試)を実施している大学の中には受験資格に「部活・ボランティアをはじめとした課外活動を有する事」を明記していないケースもあるためです。
加えて合否に関しては受験する大学が定めている『アドミッションポリシー※学生像』にマッチしているか、志望理由書や小論文、面接の印象等の総合評価で決まります。
そのため、活動実績だけで合否が決まるわけではないので実績がなくても逆転できるチャンスはあります。
しかし、合格を勝ち取る際には活動実績がないとかなり不利になるのは事実です。
というのも活動実績がないと志望理由書や自己推薦書や面接でアピールするポイントが無くなるので選考で不利になるからです。
そのため、総合型選抜(旧AO入試)を受験する前にある程度の活動実績を作っておくことは重要です。
そもそも総合型選抜(旧AO入試)で評価される活動実績とは?
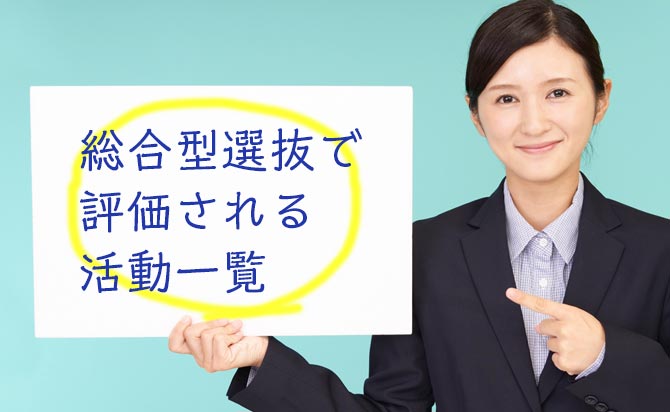
総合型選抜(旧AO入試)では活動実績が重要になるといってもどんなことが活動実績になるのかわからないですよね。そこでここでは総合型選抜(旧AO入試)において活動実績と評価される4種類の活動内容と効果的に実績をアピールする方法をご紹介します。
部活やサークルなどの課外活動
部活やサークルなどの課外活動も、総合型選抜(旧AO入試)では活動実績として報告できます。
部活では全国大会や県大会優勝、文科系サークルなら優秀賞などの実績を書きます。
その時に頑張ったことや苦しかったことも書いて、そうした状況でどのように行動したかも書くとさらに良いでしょう。
活動内容をできるだけ詳しく書くこともポイント。何チームや何校出場した中での順位を加えると信憑性が増すので活動報告書を見た人にインパクトを与えるように書きたいですね。
加えて「実績を書く際にはあなたがやった事やあなたが考えた動機」を伝える事も考えたいですね。あなたの個性や役割が伝わるエピソードの場合は実績だけ淡々と書く文章よりもあなたの魅力が伝わるので質の高いエピソードになります。
留学やボランティア活動

留学やボランティア活動も立派な活動実績です。
留学した理由や留学を経験して学んだこと、ボランティア活動で得た経験を書くと良いでしょう。例えば、
- 「将来は海外で働きたいので英語経験を積むために留学した」
- 「災害に苦しむ人達を助けたいと思ってボランティア活動に参加した」
といった形で理由や状況を詳しく書くと評価が上がります。ボランティア活動の中で総合型選抜(旧AO入試)の合否判定において評価される活動については以下のページでまとめているのでよろしければどうぞ。
生徒会や文化祭の実行委員
生徒会や学園祭の文化祭の実行委員も活動実績として書くことが出来ます。
特にどういった気持ちで活動に取り組み、どういった工夫をしたのかという点を具体的に伝えられれば高い評価が期待できます。例えば生徒会で書記をしていたとします。
その際に、どんな思いで書記の役割に取り組んだのか。また書記の仕事をする中でどんな点に注意したり、気を配ったのかを伝えられればあなたの人間性や性格をアピールできます。
生徒会や学園祭の実行委員は部活などと比べると華やかさはないかもしれませんが、取り組みの姿勢や実施した工夫をアピールすれば十分に高い評価を受ける事が出来ます。
資格取得
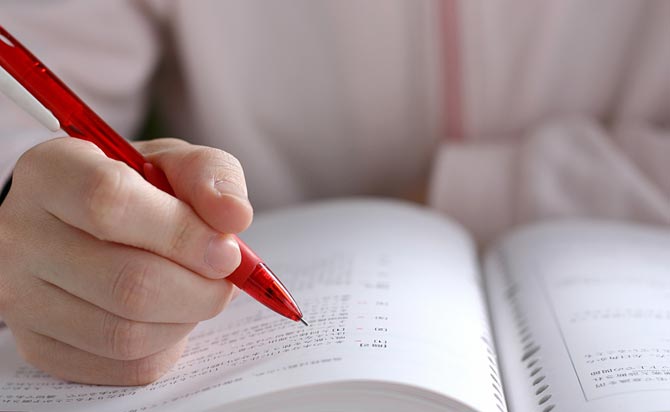
資格の取得も立派な活動実績です。中でも受験する大学で求められる資格を取得したエピソードは非常に高い評価を受けます。
これまでに取得した資格名だけではなく、資格勉強で得たことも併せて書くといいでしょう。併せて資格勉強に取り組んだ時の経験や苦労(どんな状況で勉強した・時間のやりくりが大変だったなど)等も記載すると評価が上がります。
目立った実績が無い時の対策方法

次に目立った活動実績がない場合の対策方法を解説します。今からでもできる対策ばかりなので、活動実績に不安を持つ受験生は必見です。
持っている活動を最大限活用する
現時点で持っている活動を最大限活用しましょう。
「生徒会に加入した」「クラブではお世話係として部員をサポートした」など、どんな些細な活動でも構いません。その上で「その活動でどんな役割を果たしどんなことを学んだのか」等についても説明できるように準備しておくと安心です。
前向きな態度をアピールすることで総合型選抜(旧AO入試)の合格が近づくのです。
志望理由と関係がある活動を新たに始める
志望理由と関係ある活動を始める事も重要です。
というのも志望理由書では「入学して学びたいこと」や「やりたいこと」の記載が求められる以上、書いた理由と関係性がある活動を積んでいれば高い評価を受けられるからです。
例えば入学してフランス語を学びたい場合は、フランス料理店でアルバイトをしたり、フランス語の勉強をして仏検を受けるなどですね。
志願した理由と関連した活動をすることで大きなアピールポイントになります。
大学が求めている活動を確認する
受験する大学がどんな活動を求めているかも確認しておきましょう。特に鍵になるのがアドミッションポリシーと募集要項の確認です。
アドミッションポリシーと募集要項には求める人物像や活動歴が記載されていることが多いです。そのため、2つの内容を確認すればどんな活動をどういった切り口でアピールすれば大学から高い評価を受けられるのかの予測が出来ます。
そこで受験する大学が決まった時点で、「どんな人物像が求められるのか」、「どんな活動をすれば高い評価を受けるか」については調べておきたいですね。
本気なら3年生の夏休みに短期留学や長期ボランティアに行く
高校3年生の夏休みに短期留学や長期ボランティアに行くことも対策方法の一つです。
まず大前提として公募推薦や総合型選抜の出願締め切りは8月末~10月の頭が多いです。そのため、高校3年生の夏休みに活動実績を積めば出願書類に実績を記載できます。
特に短期留学や長期のボランティア経験は大学にアピールできる活動実績なので経験をすれば一定の評価を受ける事が期待できます。
簡単な選択ではないかもしれませんが、本当に活動実績がないのでしたら夏休みに駆け込みで活動実績を作る事も検討したいですね。
総合型選抜(旧AO入試)で大切な活動報告書の書き方
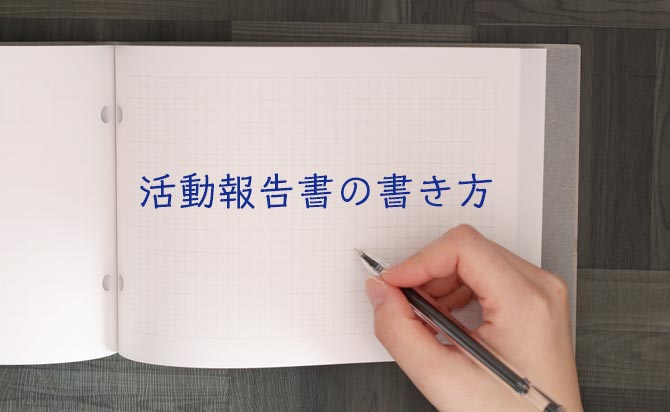
最後に、活動報告書の書き方を解説します。これからご紹介する5つのステップを行えば質の高い活動報告書の作成が可能です。
今までの活動を分析する
活動報告書を書く前に、今までの活動を分析する必要があります。分析を行う際に気を配りたいのがこれからご紹介する2つです。
- 今までやってきたことを箇条書きする
- どんな些細な活動も全て列挙する
前者の「今までやってきたことを箇条書きする」を行えば活動実績がハッキリと分かります。それに複数の箇条書きの内容を組み合わせることが出来ればより詳細に活動実績を伝えられます。
また、後者の「どんな些細な活動も全て列挙する」を行えば、些細な活動であっても大学が求めている活動にマッチする経験を見つける事も出来ます。
活動を列挙する際には勉強やスポーツなどジャンルに分けた上で箇条書きをしたいですね。こちらを行えば各ジャンルのエピソードの整理がしやすくなります。
一気に下書きを作成する
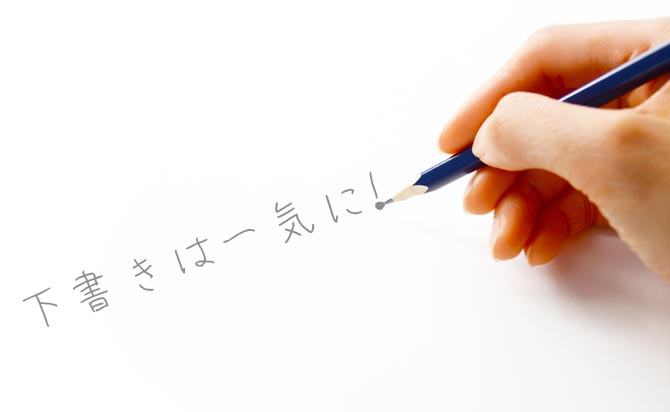
箇条書きが完了したら内容を繋いで文章にします。
文章をつなげる順番としては、「実績⇒詳細⇒経験や向上した能力」がおすすめです。なぜなら、実績(結論)から掘り下げていくとスムーズに書けるからです。
併せて、「文章の論点はどこにあるのか」も意識しておくと安心です。最も見て欲しい部分が明確になるような文章の流れも意識しておくと読みやすくなるので評価の高い文章になります。
下書きの完成後に仮完成版を作成する
下書きを書いた後には大学側が求める字数に直した仮完成版の文章を作成しましょう。
理想としては大学側が求める文字数の95%~98%程度の文字数で書き上げることです。例えば大学側が指定した文字数が1,000字数ならば950字~980字程度の文字数になります。
明らかに下書きの文字数が足りないようでしたらアピールするべきポイントを重点的に追加しましょう。逆に明らかに下書きの文字数が少ない時はカットしても問題のない部位を大きくカットして文字数を減らしたいですね。
文章に誤字脱字などないか添削してもらう
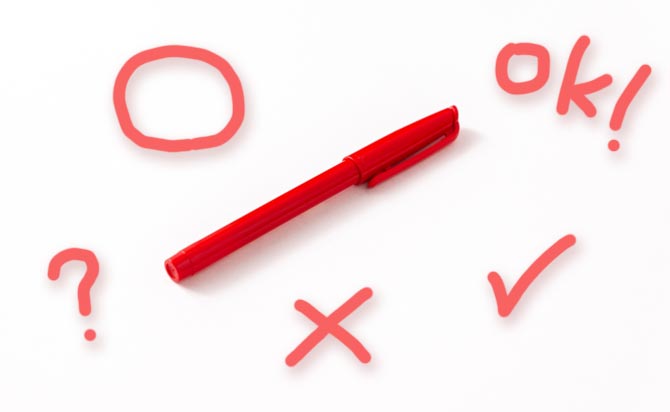
仮完成版が完成したら誤字脱字がないか確認しましょう。時間を掛けて制作した活動報告書に誤字脱字があると、大学からの評価が下がります。
誤字脱字のチェックは自分だけではなく、親や友人、先生など「第三者」に確認してもらいたいですね。
客観的な視点で活動報告書を読んでもらうと、自分では気付かない誤字や脱字の発見の期待が出来ます。
また、「第三者」に読んでもらって内容が薄かったり、内容が伝わりにくいといった指摘を受けた場合は改めて下書きの作成に戻るようにしましょう。
添削完了したら清書する
添削が完了したら清書に入ります。大学によっては紙ではなくWordなどパソコン上で記入するなどまちまちです。
指定された様式に沿って丁寧に記入していきます。記入が終わったら再度誤字脱字がないか確認して提出です。
このページのまとめ
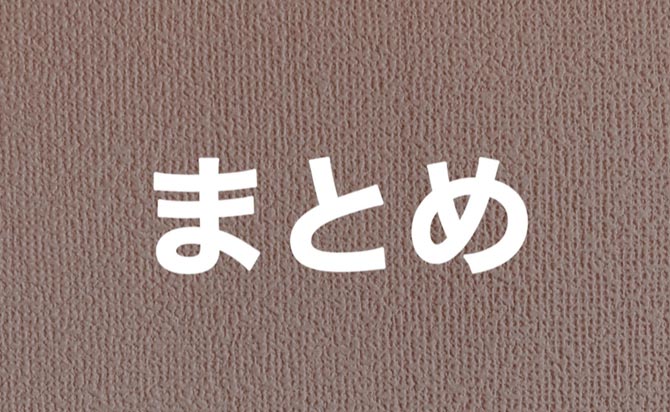
最後にこれまでご紹介してきた内容の中で特に重要なポイントをピックアップしましたので是非ご覧ください。
おさらいポイント!
- 総合型選抜(旧AO入試)は活動実績がなくても受験できるが不利になる
- 活動実績がないと合格する可能性が低くなる
- クラブやサークル、留学やボランティアなどの課外活動は活動実績になる
- 持っている資格や資格勉強も活動実績になる
- 目立った活動実績がない時は以下を心がけるべき
- 活動報告書を書く際には以下の4つが重要になる
①:今持っている活動を最大限に活用する工夫をする
②:大学への志望理由と関連性がある活動をする
③:大学が求めている活動内容を確認してアピールの切り口を考える
④:高校3年生の夏休みを利用して集中的に活動実績を作る
①:今までの活動を分析して箇条書きにする
②:箇条書きが終わった後に下書きを作る
③:下書きを作った後に仮完成版を作る
④:仮完成版を作成した後は添削を依頼する
最後に当ページと併せて目を通しておきたいページをご紹介してこのページを終えようと思います。
⇒合格を勝ち取るための理想的な対策時期を大公開
⇒合格を勝ち取りやすい人と勝ち取りにくい人の違い
この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。
過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。
2020年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。
総合型選抜
総合型選抜と公募推薦の対策ガイドを無料でプレゼント
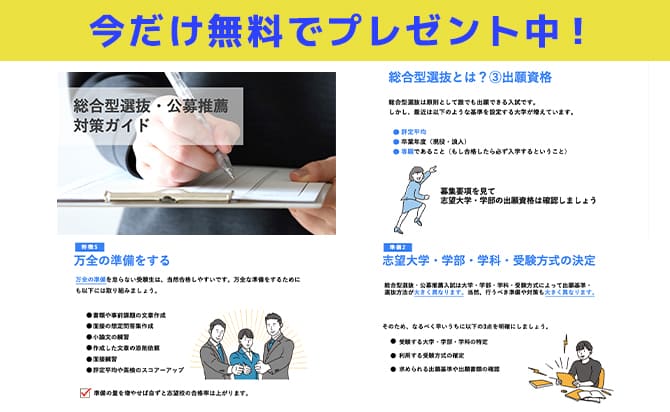
「総合型選抜や公募推薦の利用を考えているけど、何をすれば良いか分からない・・・・」 といった高校生や高校生の親御様のお役に立てればと思い、総合型選抜と公募推薦の対策ガイドを作成しました。
今だけ無料でプレゼントをしているのでぜひお受け取り下さいませ。↓