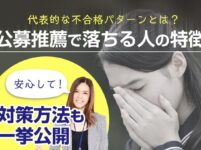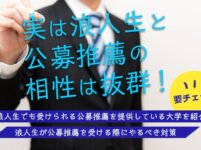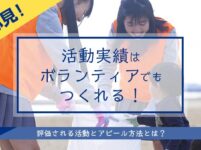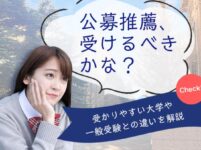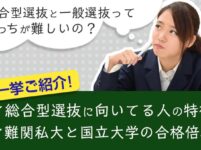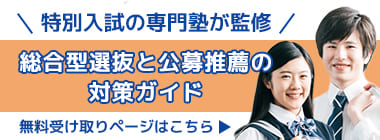BLOG

大学側が指定した受験条件を満たし、所属する学校の学校長から推薦をもらえば誰でも出願が可能な「公募推薦」。
最近では公募推薦を採用する大学が増えたこともあり、注目を集めています。
しかし、いくら注目を集めているとはいえ、公募推薦を利用して大学に進学する高校生は一般受験で入学する数と比べるとまだまだ少数。
それに公募推薦は総合型選抜(旧AO入試)と比べてもマイナーな入試形態なのでどんな人が受かるのかはあまり情報が出回っておりません。
そこで今回は、公募推薦で受かる人の特徴や落ちる可能性が高い人の特徴、そして公募推薦で受かるためにやるべきことなどを詳しくご紹介します。
この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。
自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。
高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。
倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。
目次
公募推薦に受かる人の7つの特徴
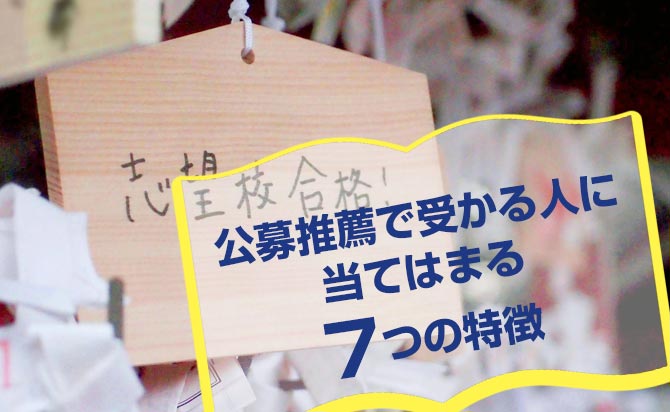
まず公募推薦に受かる人に見受けられる7つの特徴をご紹介します。
評定平均が募集条件より明らかに高い
評定平均の高さは公募推薦において非常に重要です。なぜな大多数の大学が公募推薦で評定平均の足切りラインを設けているためです。
そのため評定平均が高い人は、それだけで公募推薦において有利と言えます。なかでもあなたの評定平均が大学側が募集要項で定めている評定平均よりも大幅に高ければ、合格にぐっと近づくでしょう。
例えば出願条件に「評点平均が3.5以上」と定めている大学を受けるとします。このケースであなたの評定平均が4.0以上ならば、明らかに基準値を大幅に満たしており、評定平均という評価項目においては非常に大きなアドバンテージになります。
逆に出願条件が3.5以上のケースであなたの評定平均が3.6ならばどうでしょうか?
3.6だと基準値ギリギリのため、他の受験生よりも評定平均が悪いとも考えられます。結果として評定平均では高い評価を得られないため、合格のハードルは上がるでしょう。
大学に提出する資料(志望理由書や自己推薦書)の完成度が高い
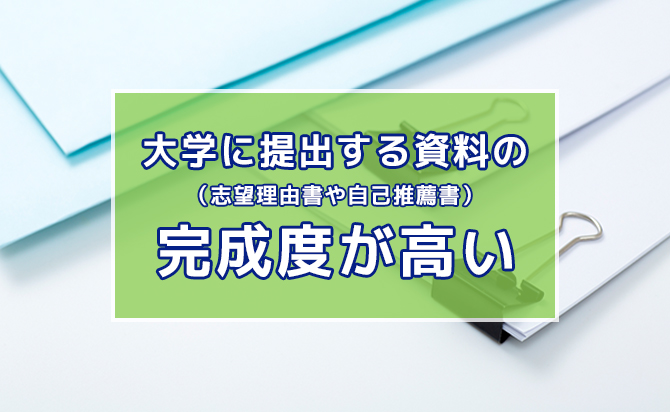
公募推薦では「志願理由書」や「自己推薦書」の提出を大学側から求められます。
「上手に書けない」「長い文章を書くのは面倒」と敬遠する高校生も多いですが、丁寧に取り組むだけでライバルとの差を付けられるでしょう。
これらの書類を通じて、大学側は受験生本人の思いや思考力、人間力を判断します。
何より最初に大学側の目に留まる「志願理由書」並びに「自己推薦書」は、合否を決める評価対象項目のひとつです。完成度が高ければ一次選抜の段階で高評価を受けられ、完成度が低ければ書類選考で落ちることも考えられます。
試験日に実施される小論文やテストの出来が良い
公募推薦は複数の基準の総合評価で合否が決まりますが、試験当日の小論文や筆記テストは合否に大きく影響します。
試験当日の小論文やテストは時間が決められているため、きちんと対策をしたかどうかで結果が大きく変わるでしょう。
大学側は当日の小論文やテストの出来で受験生の学力や能力の高さをチェックします。当然、出来が悪ければ不合格に直結し、出来が良ければそれだけ合格に近づくでしょう。
面接での受け答えとマナーがしっかりしている
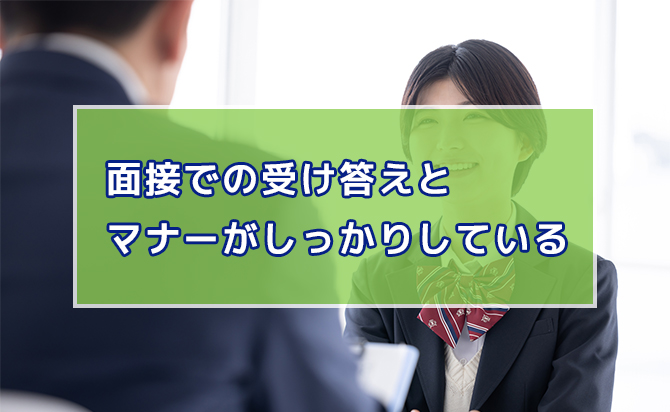
面接時のマナーや質問に対する受け答えの雰囲気は、あなたの魅力を面接官に伝える上で非常に重要。
なぜなら面接の場でマナーや受け答えに問題があれば「この子には来てほしくない」と思われ、一気に不合格に近づく可能性があるためです。
加えて、質問に対する受け答えの態度や相手への配慮といったマナーは、コミュニケーション力のアピールになるだけではありません。
本番の面接に対して入念に準備をした熱意を面接官に伝えられます。当然、準備をしていない高校生と比べると高い評価を受けるため、おのずと合格に近づくと言えるでしょう。
志望する大学のことをよく理解している人
志望する大学についてしっかり調べて理解しておくことは、公募推薦における合格に欠かせません。
毎年何十人と受験生を見ている大学側は、「各受験生が本心からその大学に入りたいと思っているか」をすぐに見抜きます。
また面接では、基本的に大学を志望する理由や「他の大学ではなく、なぜうちの大学なのか」といった質問もされます。
受ける大学のことを本気で調べ上げ、明確な理由を説明できるようにしておくのが合格に近づくポイントです。
志望大学のことを深く知り志望度を伝えられれば、おのずと面接の印象が良くなります。大学に関する情報はインターネットやオープンキャンパス、先輩のクチコミも利用してよく調べておきましょう。
頑張りや結果をアピールできる課外活動がある人
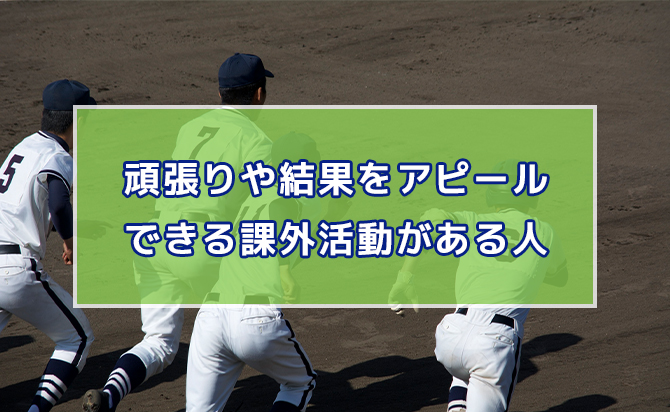
部活や生徒会、学校以外の活動などでの実績は大きなアピールポイントなので、面接の場で高く評価されます。
実績に関しては「全国大会出場」のような大きなものではなくても構いません。
例えば「チームで○○を成し遂げ、その中で私は△△をした」といったような、チームの中での実績でも十分に評価されます。
小さな実績であっても伝え方次第で面接官から高評価を受けられるので、何か1つでも自信を持って語れる実績を作りましょう。
皆勤賞に近い出席率がある人
高校から大学に提出する書類には欠席数や遅刻数が記載されます。当然、遅刻や欠席の数が多い人よりも皆勤賞または皆勤賞に準ずる出席率がある人の方が好印象を持たれます。
なぜなら、皆勤賞に近い出席率が意味するのは「毎日きちんと学校に通っていた」ことの証明であり、受験生の真面目さや勤勉さの現れであるからです。
皆勤賞を獲ったからといって必ず公募推薦で合格するわけではありませんが、評価項目のひとつであることは認識しておくと良いでしょう。
逆に落ちる人はどんな人なのか?
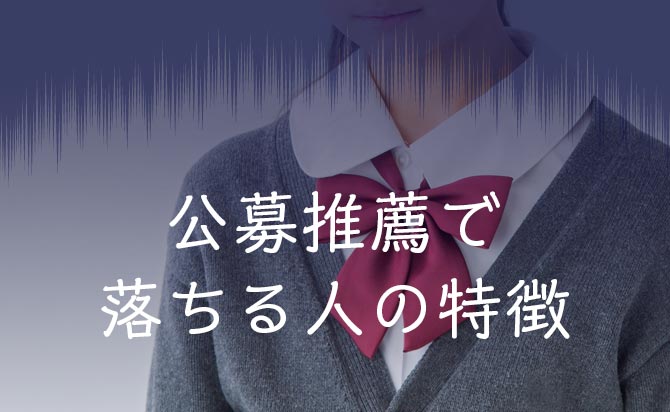
公募推薦で不合格になりやすい受験生には以下のような特徴が見受けられます。
- 提出書類の仕上がりが雑
- 小論文やテストの対策が不十分のまま受験する
- 基本的なコミュニケーションスキルがない
- 面接の受け答えが模範解答の丸暗記である
- 大学について調べていない
- 評定平均が他の受験生よりも低い
- 出願時の動機が不明瞭(*有名だからとりあえず受ける、など)
上記で取り上げた7つの項目の中に該当するものがあれば、合格を勝ち取る際の足かせになる恐れがあります。
今からでも対策をしてマイナスポイントをなくすのがおすすめです。
公募推薦に落ちる人の特徴に関するより詳しい情報は、不合格にならないための対策方法と併せて以下のページでまとめているのでご興味があればどうぞ。
そもそも合格率はどの程度なのか?

公募推薦の合格率は大学・受験年度によって変動します。
1倍台の大学もあれば5倍を超える大学もある
大学全体を見ると1倍を切る、あるいは1.2倍程度と「受験すればほぼ合格する」ケースもあります。しかし、一方で人気大学の場合は8倍~10倍と非常に狭き門になる場合もあります。
一般的には有名大学や上位・難関大学の方が倍率が高い傾向にあります。
有名大学・難関大学であるほど、どうしてもその大学に入りたい受験生は増え、1回でも多くの受験機会を活かしたいという心理が働くためです。
また、特色ある大学・学部学科も受験生が集中するため、倍率は高くなりがちです。
2倍~5倍が多い
例年の入試結果から、MARCH以上の上位大学の公募推薦倍率は2.5~5倍程度。中堅大学で2倍前後となることが多く見られます。
以下に主な大学の公募推薦合格率と合格者数をまとめましたのでご覧ください。
(※倍率=志願者/合格者で算出)
| 大学名 | 2023年度の倍率 |
|---|---|
| 上智大学 (経済学部・経済学科) |
2.6倍 (募集24人・志願者50人・合格者19人) 参照元:2023年度の上智大学の入学試験データ |
| 同志社大学 (文学部・英文学科) |
1.6倍 (募集10人・志願者26人・合格者16人) 参照元:2023年度の同志社大学の推薦入試の結果 |
| 学習院大学 (経済学部) |
3.2倍 (募集非公開・志願者36人・合格者11人) 参照元:2023年度の学習院大学の学校推薦入試・総合型選抜の結果 |
| 日本大学 (商学部) |
1.6倍 (募集23名・受験者70名・合格者44名) 参照元:2023年度の日本大学の学校推薦型選抜の結果 |
今回取り上げなかった一般選抜と公募推薦の倍率の違いについては、以下のページでまとめているのでご興味があればどうぞ。
志望校に受かるためにやるべきこと
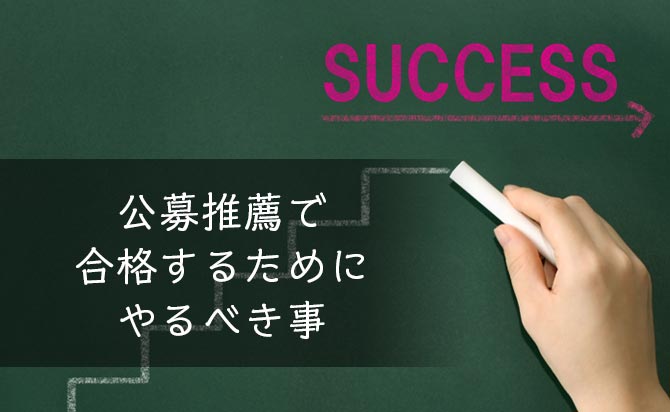
次に公募推薦で志望校に受かるためにやっておきたい8つのアクションをご紹介します。
評定平均を可能な限り上げる
最優先は、評定平均を可能な限り高めておくことです。
志望大学の評定基準ギリギリで出願するよりも、少しでも上回っていた方が選考で有利なためです。高校の評定は学校の定期テストの成績で決まるので、学校のテストで点数を取れるよう対策しましょう。
評定平均の対象になる時期と科目について
ちなみに評定平均の算出の際の対象となるのは1年生の1学期〜3年生の1学期までの評定です。そのため1年生のうちから評定を意識しておくことが大切です。
また5教科7科目のような主要科目だけではなく、音楽や体育のような副教科も含まれます。
副教科は一般受験とは関係ない科目である以上、多くの高校生は力を入れません。しかし評定平均が重要になる公募推薦において、副教科は主要5教科と同じように大切な科目です。
評定平均の向上につながる以上、音楽・体育・家庭科・美術といった科目も主要科目と同様に頑張りましょう。
テストだけの頑張りでは不十分
評定平均には、学校のテストの点数に加えて授業態度や課題への取り組み方も影響するので注意が必要です。授業態度については、主に以下の点において評価されています。
- 授業中に眠っていないか
- 携帯を触るなど他のことをしていないか
- 提出物をしっかり提出しているか
どのように授業態度を評価しているかは学校によってもまちまちではありますが、意欲的に授業に取り組むことが大切です。
受験する大学の調査や自己分析によって志望理由を明確にする
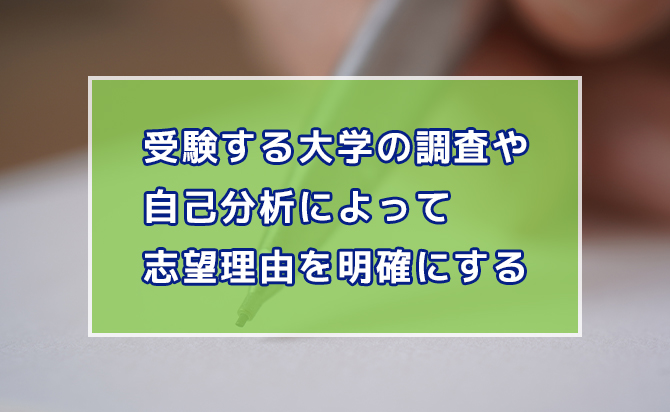
志望理由が自分の言葉で情熱を持って語れるかどうかによっても評価が分かれます。
そのため、まずは大学について詳細に調べることから始めましょう。
その上であなたの将来像と志望する大学の関連性、そして他の大学ではダメな理由まで語れるようになれば言うことはありません。
また明確な志望動機を話せるようになるためには、自己分析することも大切です。
自己分析をし、自分がどのような人物なのかを客観視してみましょう。自分の将来のビジョンを明確にして、将来のために大学で何を学びどのように成長していきたいのかを導き出し、それを面接でアピールすることが必要です。
オープンキャンパスに参加する
オープンキャンパスに行って実際に体験することも大切です。
なかには、公募推薦の受験資格のひとつに「オープンキャンパスへの参加」を義務付けている大学もあります。
なお、志望大学がオープンキャンパスへの参加を義務付けていない場合であっても、足を運ぶ価値はあるでしょう。
なぜならオープンキャンパスに足を運べば、ネット上だけでは知り得ない大学の魅力を実感できるためです。大学の魅力が分かればおのずと志望動機の深みが増すので、面接の場でも自然に熱意を伝えられるでしょう。
小論文の練習を始めて先生に添削を頼む
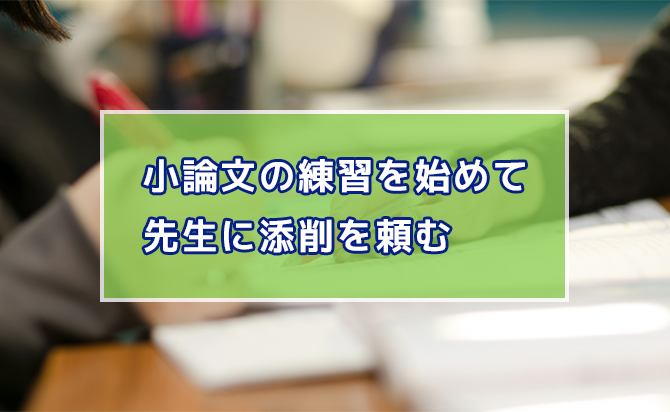
小論文練習は早めに始めましょう。もし可能であれば、練習で書いた小論文を先生に適宜チェックしてもらうのがおすすめです。
実際に書いてみると分かりますが、まとまった分量を理路整然と時間内に書き上げることは、トレーニングなしには困難です。また、小論文の問題点や出来栄えを自分で客観的に評価するのも難しいでしょう。
まずは過去問や市販の問題集を買って何度も書いてみましょう。そして練習で書いた小論文に関しては完成次第、適宜高校の先生に添削してもらうことをおすすめします。
2級以上の英検を取得する
公募推薦に合格をするには、2級以上、できれば準1級の英検を持つことが非常に重要です。
大学によっては「2級以上の英検を取得していること」を出願時の条件にしているケースがあるためです。
当然「英検2級の縛りがある大学」は、2級以上の英検を保有していなければ受けられません。
もし出願時に英検の保持を求めない大学であっても、2級以上の英検資格があれば加点材料になるので、合格に近づけるでしょう。
学業以外の課外活動で語れる経験を積む
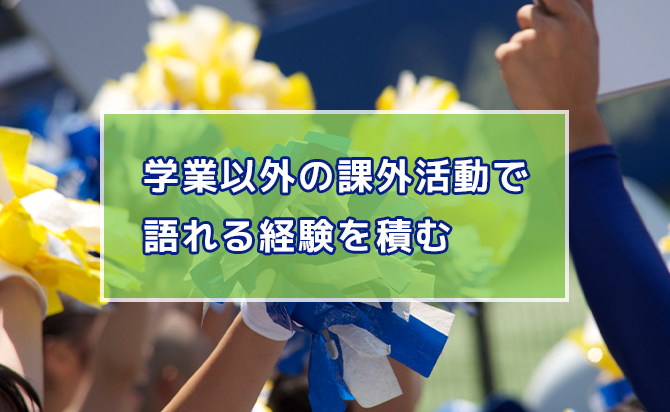
学業以外の活動経験を積むことも公募推薦突破には有効です。
というのも学業以外の課外活動の実績は、評定平均や出願書類の出来栄えと同様に公募推薦の合否を分ける評価項目のひとつであるためです。
ちなみに課外活動は部活が一般的ですが、例えば生徒会やボランティア活動も立派な課外活動と言えます。
何かしらの課外活動において語れるだけの経験を持てば、自己推薦書を書く際のネタや面接の自己PRに使えます。
おのずと公募推薦の合格率も高まるので、学業以外で誇れる経験を最低でも1つは積んでおきましょう。
志望理由書や自己推薦書の添削を依頼する
出願する大学が決まったら「志望理由書」「自己推薦書」を準備し、何度も学校の先生に添削を頼みましょう。
これらの書類はあなたの魅力やあなたの熱意を大学側に伝える意味合いを持つ、大切な提出書類です。
初めて書く際には何を書くべきか分からないかもしれませんが、まずは指定の形式に沿って一度書いてみましょう。
書いたものを高校の先生や塾の先生など経験豊富な大人に添削してもらえば、自分自身では気づけない文章の問題点や改善点が明確になり、書類の完成度が高まります。
一次選抜に通った後には面接の練習をする
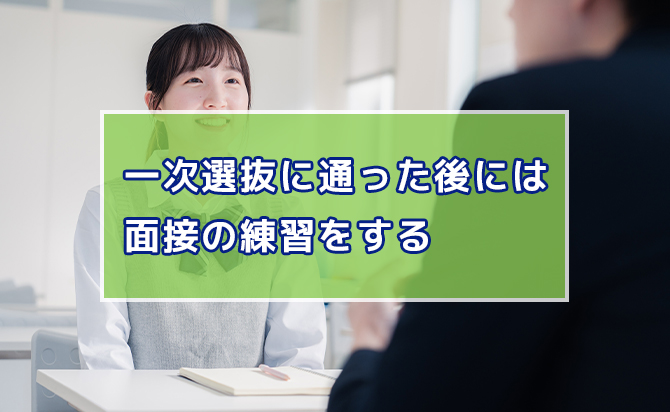
一次選抜の書類選考に通過したら、二次選抜でほぼ必ず行われる面接の練習をしましょう。面接練習で意識しておきたいポイントは以下の2つです。
- よくある質問集にそって自分の受け答えをまとめること
- 本番を想定した模擬面接を何度も重ねること
特に模擬面接に関しては高校の先生に時間を作ってもらい、不安な気持ちがなくなるまで練習を重ねると良いでしょう。事前にまとめた受け答えの丸暗記は不要ですが、十分な練習が本番の自信につながります。
早い段階から対策を進める
早くから公募推薦の対策をしておいた方が、合格により近づきます。早い人は高校1年生から対策をスタートするほどです。
特に小論文は早めの対策が合格の鍵になります。一般的には、2〜3ヶ月前からの対策が必要と言われていますが、あくまでも目安です。
志望校や自分のレベルに合わせて、対策開始時期を見極めましょう。
合格した人に話を聞く

実際に公募推薦に合格した人の経験談を聞くのもおすすめです。これまで知り得なかった勉強法などが知れる場合があるでしょう。
合格率をアップさせるには、対策塾に通うのも有効
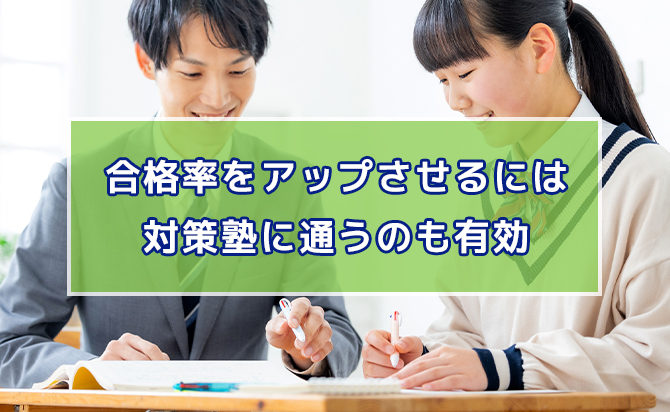
公募推薦に合格するためには、学校の指導だけでは不十分な場合があります。学校によっては公募推薦に向けた指導法が確立されていないところもあるようです。
そこでおすすめなのが専門の塾に通うこと。塾であれば個々に合わせて指導してもらえるところが多数あります。
大学によって選抜方法がまちまちですが、専門塾なら受験方式や志望大学に合わせた対策を進めてくれるでしょう。
さらに書類や小論文の添削や面接の練習ができるところや、特定の大学の入試対策をとっているところもあるので、しっかりと対策を練られるでしょう。
公募推薦の対策については当スクールホワイトアカデミー高等部でも行っておりますので、ご興味があればまずは無料の受験相談をどうぞ。
評定平均は公募推薦でどの程度重要?
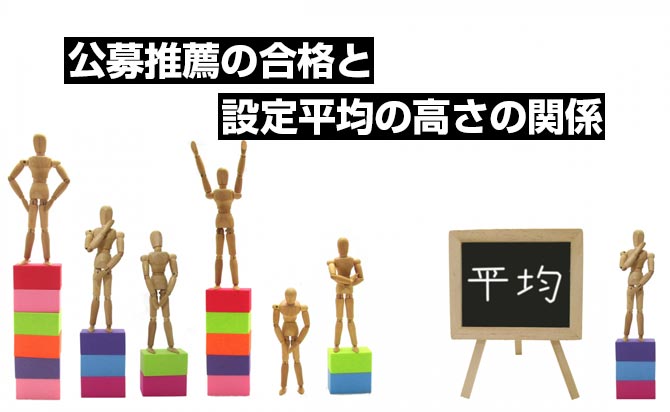
次に公募推薦において評定平均がどの程度重要視されているのかについて考えてみましょう。
基準評定よりも高ければ高いほど有利
公募推薦は、大学が定めている基準評定を満たしてさえいれば出願できます。
しかし最低基準をギリギリ満たす人とはるかに上回る人とでは、後者の方が高い評価を受けるため、評定平均は高ければ高いほど有利です。
また公募推薦に出願する受験生は、「生徒会で役員をしていた」「部活を3年間頑張ってきた」など特性がある程度似通っています。
そのため、同じ属性の受験生が集まる中で評定が高ければ際立ち、逆に評定が低いと明らかにマイナスになるでしょう。
評定平均がギリギリでも受かるの?
評定平均が基準ギリギリでは合格できない、というわけではありません。
公募推薦では、受験生の成績・高校時代の活動・当日の課題や面接の受け答えなどを総合的に評価。
評定平均が唯一絶対の合否基準ではないため、ギリギリでも合格できる場合があります。
ただし評定基準ギリギリで合格を狙うには、自分より評定が高い他の受験生を評定以外の項目で追い抜かないといけません。
部活の実績や面接・小論文に圧倒的に自信がある場合は別ですが、評定が高い受験生に比べて合格までの難易度が上がることは忘れないようにしましょう。
ギリギリの評定平均で公募推薦の合格を勝ち取る方法や、低い評定を埋めるためにやるべきことについては、以下のページで詳しくまとめているのでご興味があればどうぞ。
このページのまとめ
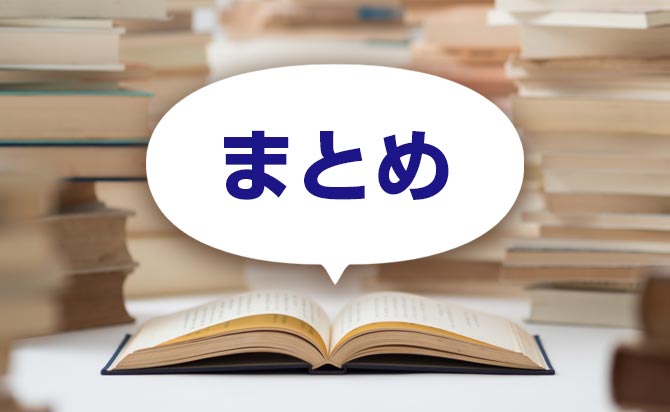
最後にここまでの内容の中で特に押さえておきたい公募推薦で合格するために欠かせないポイントを改めて一覧にしてみました。
特に重要なポイント一覧
- 出願基準を上回る評定平均を手に入れる
- 大学について調べる
- 志望理由を明確化する
- 出願書類は丁寧に仕上げる
- 小論文や面接の対策を積み重ねる
- 添削や面接は先生の力を借りる
いずれも自己努力が及ぶ範囲の事柄です。そのため公募推薦で合格を勝ち取りたければ、今取り上げたすべてに着手するのが良いでしょう。本記事を参考に合格に向けて取り組んでみてください。
最後に併願受験が可能な公募推薦を提供している、関東・関西の私立大学を紹介しているページをご紹介します。
この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。
過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。
2023年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。

ホワイトアカデミー高等部とは?
総合型選抜・公募推薦入試に特化した専門塾。
プロ講師が活動実績作りから小論文・面接まで、
マンツーマンで徹底サポート。
- カリキュラム修了者の合格率98%※1
- 上智大学合格率83%(2025年度)※2
- 小論文・書類すべて添削無制限
- 全授業が社会人のプロ講師による1対1形式
- カリキュラム修了者には合格保証制度を提供

※2 上智大学合格率83%は2025年度入試における上智大学受験者が母数です。