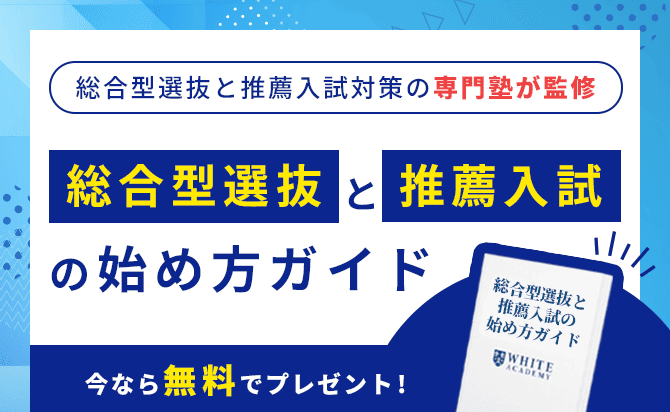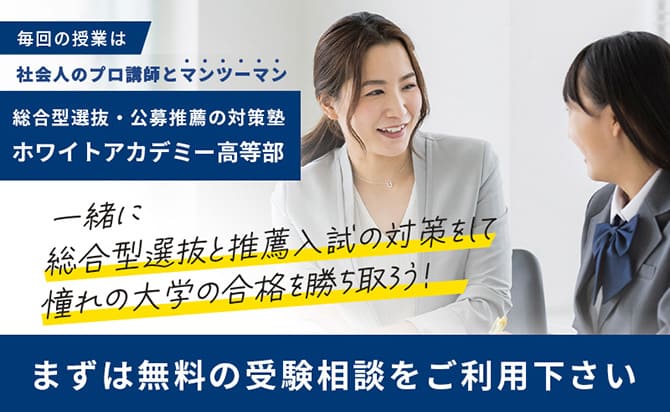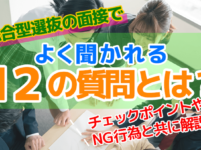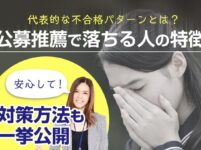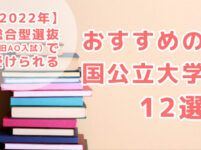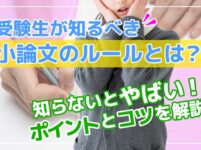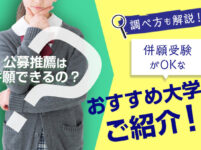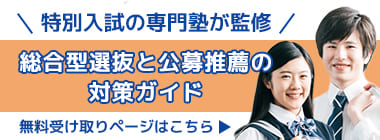BLOG

推薦入試の形式は、大きく分けて指定校推薦と公募推薦があります。
しかし、初めて受験する身となれば両者の違いを正しく理解し、どちらに向いているのかを考えるのは簡単ではありません。
何を隠そう私の生徒の女の子も、高校3年生で推薦入試の利用を考え始めた時には、違いを全く理解していませんでした。
その経験をもとに、今回の記事では推薦入試の中でも特に多くの受験生が利用する指定校推薦と公募推薦の違いについて解説します。
ざっとでも目を通せば指定校推薦と公募推薦の何が異なるのか、そしてどちらがあなたに合うのかが分かります。是非最後までお付き合いください。
本題に入る前に、ホワイトアカデミー高等部では、指定校推薦や公募推薦で志望大学の合格を勝ち取る秘訣をお話しする無料の受験相談会を開催しています。
ご参加頂ければ、指定校推薦と公募推薦の違いやどちらが向いているかを講師がご相談者様のご状況に即した上でお話しします。無料の受験相談会は以下からご予約をお取り頂けるので、ぜひご利用ください。
ホワイトアカデミー高等部の公式サイトと無料の受験相談会のご予約はこちら
この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。
自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。
高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。
倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。
目次
2種類の推薦入試の違い一覧表
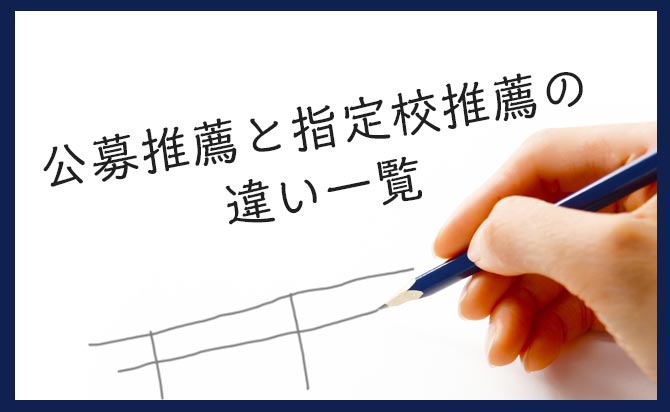
はじめに、公募推薦と指定校推薦はどちらも推薦入試でありながらも明確な違いがあることが分かるよう、両者の相違点を一覧にしてみました。
| 公募推薦 | 指定校推薦 |
|---|---|
| メリット | |
| 学力以外の面も評価対象になる | 校内選考に通れば合格が確実 |
| デメリット | |
| ・事前準備に時間を要する ・合格の保証がない |
推薦枠がある大学しか受けられない |
| 不合格の確率 (合格倍率) |
|
| 60%~80% (2.5倍~5倍の倍率が多い) |
落ちることはほぼ無い |
| 問われる項目 (試験内容) |
|
| ・自己推薦書 ・志望理由書 ・事前課題 ・小論文 ・学科試験 ・面接 ・その他 |
・志望理由書 ・自己推薦書 ・面接 ・大学によっては小論文もあり |
| 合否の鍵 | |
| ・評定平均 ・課外活動の実績 ・英検の有無 ・当日の面接の印象 ・当日の小論文の出来 ・提出書類の出来 ・大学とのマッチ度 |
・評定平均と学校生活態度 ・当日遅刻しない事 ・面接や提出書類で大きな失態をしない事 |
| 併願について | |
| 原則不可 (*一部の大学は認めている) |
不可 |
| その他の特記事項 | |
| 多く大学で小論文と面接が科される | 校内選考に受かれば基本的には合格する |
| 向いている人 | |
| ・学部学科に入りたいという強い意志のある人
・課外活動の実績がある人 ・人前で話すのが得意な人 |
定期テストの点数が高く、真面目に学校生活を送ってきた人 |
以下では、公募推薦と指定校推薦の特徴を詳しく見ていきましょう。
公募推薦とは
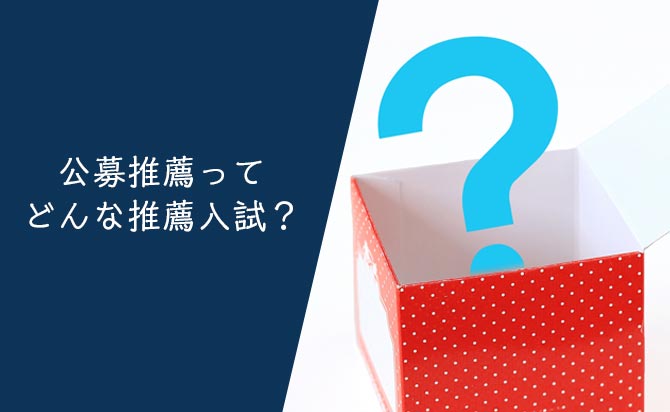
公募推薦は、大学の出願条件を満たし、学校長の推薦状があれば誰でも受けられる形式です。
公募推薦の種類
公募推薦は「公募制一般推薦」と「公募制特別推薦」の2つに分けられます。
公募制一般推薦
公募制一般推薦とは、大学の出願条件を満たし学校長の推薦状があれば応募できる推薦入試。私立、国立問わず多くの大学が取り入れています。
評定平均の提出、資格・検定のスコアの提出、調査書・自己推薦書や志望理由書の用意が必要で、さらに小論文や面接で合否判断が行われます。
公募制特別推薦
公募制特別推薦は、文化活動やスポーツにおいて優れた実績を残した人が出願できる推薦形態です。
評定平均の提出を求めない大学が多く、幅広い分野での実績が評価されます。
これらの公募推薦に向いている人は、将来具体的にやりたいことや学びたいことがきちんとある人です。
公募推薦に向いている人のより詳しい特徴については、以下のページでまとめているのでご興味があればどうぞ。
出願時に必要な提出書類

条件を満たしている人なら誰でも出願可能ですが、準備すべき課題や書類が多くあるため、出願には一定の準備が欠かせません。
提出が必要な主な書類は以下の通りです。
- 調査書
- 評定平均
- 資格
- 検定のスコア
- 自己推薦書
- 志望理由書 など
大体1,000~2,000字程度の書類提出を要求するため、準備には時間がかかります。これらの書類が一次審査となる場合が多いため、自分をアピールできるようしっかり作り込むことが必要です。
試験内容
試験内容は一次選抜・二次選抜の順で行われるケースが多く見られます。
一次選抜
前項でも触れたように、一次選抜では出願時に提出した書類と評定で審査されます。高い評定がポイントで、4.0程度が求められるようです。
志望する大学によっては語学力が求められ、英語の外部試験のスコアも合否の判断基準にしているところもあります。
二次選抜
二次選抜では、小論文や面接が行われるのが一般的です。
公募推薦では小論文の比重が大きいため、日頃から世の中の出来事に関心をもち、自分の意見を書けるよう練習しておくといいでしょう。
私の生徒の1人は、以下の本を読みながら毎日対策していました。
⇒株式会社新聞ダイジェスト社出版2020一年3月増刊号最新時事用語&問題
また公募推薦は、一般入試と違って学力試験が課されるケースはあまり見られません。
しかし、志望する大学によっては学科に特化した試験を科すケースもあります。そのため、学科試験がある大学を受ける場合は、過去問を入手して早めに準備に取り組むことが大切です。
公募推薦のメリット

次に公募推薦を利用する3つのメリットをご紹介します。
受験回数が増える
公募推薦入試を受けることで受験回数が増え、その分合格するチャンスが増えます。
一般入試しか考えていない人でも、合格チャンスを増やすという意味で公募推薦にエントリーする価値はあるでしょう。
学力以外の面も評価対象になる
公募推薦は、一般選抜では厳しいような大学にも合格できるチャンスがあります。
なぜなら公募推薦は一般選抜と異なり、高校生活の過ごし方や提出書類の質など複数の観点から合否を判定するためです。なかでも、部活動や生徒会活動を頑張ってきた人や、面接が得意な高校生にはチャンスがあります。
学びたい熱量が評価される
基本的に公募推薦では面接試験や事前課題等で志望理由が聞かれます。
志望理由を明確にすることで、大学に自分の熱意を伝えられるでしょう。一般入試では志望動機などを聞かれることはまずないため、学びたい意欲が評価されるのは公募推薦ならではのメリットと言えます。
公募推薦のデメリット
次に公募推薦のデメリットについてご紹介します。
事前準備に時間がかかる
ここまでの内容を読んでいても分かるように、提出書類が多いことが公募推薦の難点です。
書類作成は、順調に進んでも1〜2ヶ月ほど時間を要するため、一般受験に向けた対策の時間が十分に確保できません。早めに書類作成に取り掛かりましょう。
基本的に合格すれば進学しなくてはいけない
公募推薦を実施している大学は、基本的に「専願受験制」を採用しています。専願受験制とは、合格すると原則として入学が義務付けられることです。
つまり、ひとたび公募推薦に合格してしまうと、一般受験でより難易度が高い大学に受かったとしても進学できません。そのため、公募推薦を利用する場合は、合格したら入学を確約できる大学に出願することを心掛けたいですね。
対策が難しい
公募推薦で課される小論文や学科試験、面接などは、高校で学ぶ一般受験用の5教科7科目とは明らかに異なる一面があります。
加えて多くの高校では、推薦入試に特化した授業がない上に、小論文の授業がないことも。そのため、公募推薦を利用する場合は対策が非常に大変です。
自力での対策に自信がないのであれば、推薦入試対策の専門塾に入塾したり、担任の先生に小論文や提出書類の添削を自主的にお願いしたりするといいでしょう。特に、本気で合格したい場合は塾の利用を検討するのがおすすめです。
必ずしも合格するとは限らない
公募推薦の合格率は、20〜50%と決して高くはありません。例えば同志社大学の社会学部|社会福祉学科の20204年度の倍率は2.2倍です。
参照元:2024年度 推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験(公募制) 志願者・受験者・合格者数|同志社大学
29人が志願して13人が受かる計算なので合格率は45%。公募推薦で入りやすいと言われる上智大学でも、多くの学部の倍率が2倍以上なので、合格率は50%を切ります。
参照元:2024年度 入学試験データ|上智大学
公募推薦は推薦入試の一種とはいえ、必ず受かるわけではありません。
落ちる可能性もあり、落ちると公募推薦のために対策した提出書類の作成時間や、面接練習などの時間が無駄になってしまうのは見逃せないデメリットです。
また「不合格になったから」と一般選抜に切り替える場合、その対策が遅れてしまう点も懸念されます。
公募推薦の難易度や倍率については、以下のページでまとめているので、合格率や合格を勝ち取る難しさについてご興味があれば是非ご覧ください。
指定校推薦とは
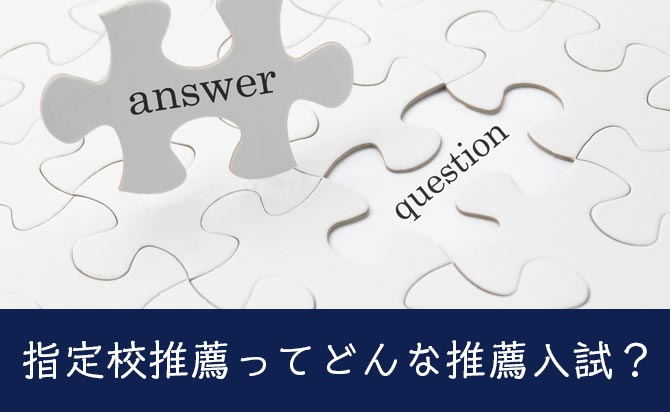
指定校推薦は、大学側から指定を受けた高校で、校内選考を突破した生徒のみが出願でき、定員が少数の推薦入試です。
先ほどご紹介した公募推薦は学校長からの推薦状があれば誰でも出願できますが、指定校推薦の場合は高校側に推薦枠がないと出願できません。
仮に志望大学の推薦枠が高校にあったとしても、校内選考に通過して高校側に推薦してもらえる人物として選ばれることも必要です。
校内審査が合格の鍵
校内選考が指定校推薦の合否を分けるといっても過言ではありません。理由は校内選考に通らないと推薦してもらえないためです。
そして校内選考では必ず評定平均が見られるので、評定平均が高い人が有利です。
評定平均は高校3年間が対象。3年生になってから対策し始めたのでは遅いので、1年生のうちから地道に対策していくことが合格につながるでしょう。
ただし、校内選考では課外活動の有無や課外活動の実績も見られるので、評定平均が一番高い人が選ばれるとは限りません。また欠席日数も合否に関係します。
そのため、勉強以外のことにも積極的に取り組んだり意識したりして、自分のアピールポイントを増やすことが大切です。評定平均が高くなくても校内選考に通るケースについては、以下のページでご紹介しているのでご興味があればどうぞ。
指定校推薦のスケジュール

まず校内選考は春から秋にかけて行われます。6〜8月にかけて校内で募集され、10月には校内選考が完了して推薦者が決定します。
その後、10〜11月頃に各大学での試験が行われ、12月には合否が出るので、合格すればかなり早い時期に受験から解放されるでしょう。
以下は上智大学の指定校推薦のスケジュールです。
| 出願期間 | 2024年11月1日〜2024年11月7日 |
|---|---|
| 試験日 | 2024年12月1日 |
| 合格発表 | 2024年12月12日 |
指定校推薦のメリット
次に指定校推薦の主な3つのメリットについてご紹介します。
合格する可能性が高い
指定校推薦は大学と高校の信頼関係によって枠が与えられているため、校内選考を通過すれば基本的に不合格になることはありません。
受験生が何より欲しいものは「合格」という2文字です。家庭の事情などで浪人できない場合は、指定校推薦を使って受験するのは理にかなった選択と言えるでしょう。
ただし、指定校推薦に合格した後に、学校で大きな問題を起こしたり高校の留年が決まったりすると、合格が取り消される場合があります。合格後の生活には気を配りましょう。
例外的に指定校推薦で落ちるケースについては、以下のページでまとめているのでご興味があればどうぞ。
自分の学力以上の大学に進学できる
指定校推薦では現状の学力に関わらず、校内選考に選ばれれば偏差値の高い難関大学に進学できます。
なぜなら、指定校推薦は高校と大学の信頼関係で成り立っている以上、高校側が推薦した生徒は、基本的には合格が保証されるためです。
そのため、全国模試の偏差値が45を切っている生徒であっても、評定平均が高く校内選考を勝ち抜けば、偏差値60を超えるMARCHのような難関大学に受かるチャンスがあるのです。
年内に合否が分かる
指定校推薦の場合、合否結果は12月中に発表されます。無事に合格を確認して入学手続きをすれば、翌年の4月までの時間を自分の好きなことに充てられるでしょう。
4月から一人暮らしを始める場合は、早い段階で物件探しができます。
受験料を抑えられる
指定校推薦を受ける場合は、1校のみの受験費用で済むのもメリットです。他の受験方式の場合は複数の大学を受験することが多いため、その分受験料がかかります。
指定校推薦のデメリット

次に指定校推薦の主な2つのデメリットをご紹介します。
校内選考に漏れることがある
指定校推薦の欠点は、募集定員が少ないことです。ライバルの中に評定平均が0.1高い人や活動実績が優れている人がいると、推薦枠が簡単に奪われてしまいます。
そのため、積極的に課外活動に参加したり、多くの先生に「絶対にこの大学に行きたい」と早めにアピールしたりするといいでしょう。
自分の行きたい学部が少ないことが多い
指定校推薦の募集枠の中に本当に行きたい大学がなかったり、行きたい大学の募集枠があっても興味がある学部の枠がなかったりすることも少なくありません。
そのため、指定校推薦を使って大学への進学を考えている場合は、高校側に案内が来ている大学の募集枠を全て確認しましょう。
もし第一志望の大学の募集枠がなければ、指定校推薦を使わず公募推薦に切り替えるのが無難です。
合格したら必ず入学しなければならない
指定校推薦は専願のため、合格を勝ち取った場合は必ず入学しなければならず、他の大学を受験できません。
万が一入学を辞退してしまうと、高校との信頼関係が崩れ、次年度の推薦枠に影響する場合もあります。
基礎学力に差が出やすい
指定校推薦は学力が重視される受験方式ではないため、一般で入学した人と基礎学力の差が出やすいとされています。
そのため入学後、「大学の授業に付いていけない」「周りの人と差ができている」と感じることがあるかもしれません。
各推薦入試で合格を勝ち取るための対策内容の違い
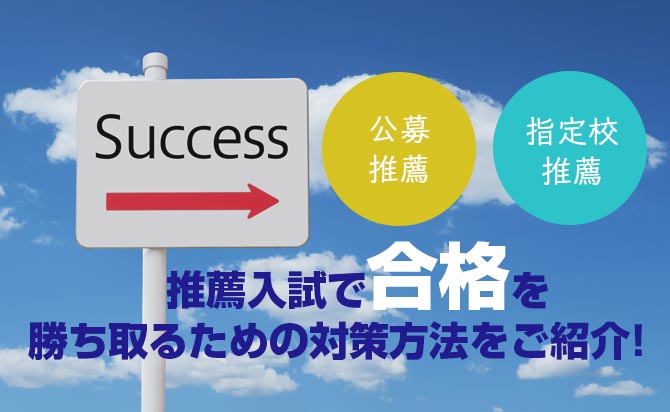
次に、公募推薦と指定校推薦で合格を目指す場合に実施したい対策内容を、公募推薦⇒指定校推薦の順番でそれぞれご紹介します。
公募推薦の合格のためにやるべきこと
公募推薦で志望大学の合格を目指す場合は、以下5つの対策を行うことをおすすめします。
日頃から自分の行きたい大学・学部に関する情報を取得する
推薦入試は、大学によって求めている学生像が異なります。同じ学部でも入学後のカリキュラムが異なれば自分が学びたい学問を学べません。
そのため、自分の行きたい大学・学部に関する情報は常に集めるようにしましょう。
完成度の高い出願書類を作る
公募推薦では多くの書類の提出が必要で、なかでも自分で文章を考える必要があるのが、「自己推薦書」や「志望理由書」です。
「この大学に入りたい」といった熱意や、長所をアピールするためのものなので、丁寧に書く必要があります。
これらの書類の内容で受験生の人となりを見られる他、書類の完成度そのものも合否に関わってくるため非常に重要です。
評定平均を上げる努力をする
志望大学の評定基準を上回っていた方が、合格には有利です。評定は、1年生の1学期から3年生の1学期の間に行われる定期テストの結果で決まります。
3年生になってからの対策では遅いので、早い段階から評定を意識して勉強に取り組むことが大切です。
自分と向き合う時間を多く持つ
公募推薦で合格するには志望大学で学びたい意欲や、大学が求めている人材と自分がどれだけマッチしているかのアピールが欠かせません。
そのため、なぜ自分がこの特定分野の勉強を行いたいのか、大学で学んだ後社会にどう活かしたいのか、という点について明確な理由を答えられるようにしましょう。
小論文・面接対策に力を入れる
公募推薦の合否は小論文の出来が非常に大きく関係します。そのため、何度も練習して本番当日に最大限の力が発揮できるように対策するといいでしょう。
どのような内容を提示されても対応できるよう、学部に関する議題のみならず、世界で起こっているさまざまな時事問題にも目を向けて、自らの意見を書けるようにしておくことも重要です。
なお小論文の練習は、過去問を上手に使って書き、先生に添削してもらうといいでしょう。
また面接の練習も大切です。志望大学の過去の面接でよく聞かれている内容をまとめたり、本番さながらの模擬面接を行ったりするのがおすすめです。
事前に練習を十分にしていれば、本番にその成果を発揮できるでしょう。
部活動や課外活動に積極的に取り組む
公募推薦では、学業以外の活動も評価されます。部活動はもちろん、学校外のボランティア活動などにも積極的に参加すれば、経験から学んだことをアピールできるでしょう。
指定校推薦の合格のためにやるべきこと
次に指定校推薦の合格を勝ち取るために行いたい対策をまとめました。
苦手科目を作らず、学校の定期テストの点数をしっかりと取る
評定平均を高くするためには定期テストの点数を上げることが欠かせません。
苦手科目であっても逃げずに勉強したり、先生に質問したりして不明な点を減らしましょう。最低でも5段階で4をもらえるくらいの点数を定期試験で取るのが理想です。
また評定平均を高めるためには、提出課題を期日通りに出すのはもちろん、授業態度に気を付けることも大切です。最終的には全教科平均で4.6以上を目指すといいでしょう。
提出課題や小論文・面接の対策をする
指定校推薦の場合、課題の提出や小論文が課されます。自分で勉強するのはもちろんですが、学校や塾の先生に内容を添削してもらうのもひとつです。練習と添削を繰り返せば、自ずと質がアップするでしょう。
また面接の練習も大切です。面接は受験生の人となりや話し方などを見られます。当日、自分の志望動機や熱意を自分の言葉でしっかり述べられるよう、事前に模擬面接を何度もして練習しておくのがおすすめです。
学校生活を真面目に過ごす
指定校推薦を狙っている人の多くは、評定平均が5段階評価のうち4.5以上はあると考えたほうがいいでしょう。
校内選考は、そもそも高い評定平均を取得している学生同士で競うため、評定平均の差はそこまで大きなポイントにはなりません。その一方で遅刻の回数が多い人や学校生活の態度に問題がある人は非常に不利です。
わずかなマイナス面が校内選考の合否に関わるので、学校生活を真面目に送りましょう。
公募推薦と指定校推薦の併用受験はできるのか
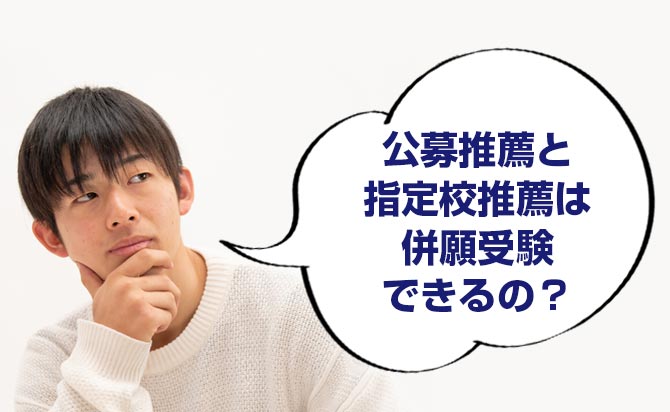
指定校推薦と公募推薦が別物であることは分かりましたが、両者の併用ができるのかについて気になる人もいるでしょう。
結論から言うと、基本的には公募推薦も指定校推薦も専願としている大学が多いため、併願受験はできません。
しかし例外もあります。
例えば指定校推薦の校内選考の結果が出た後に、まだ出願期限が閉め切られていない公募推薦を実施している大学があるとします。このケースでは校内選抜に落ちた後であれば、出願するチャンスはあります。
指定校推薦も同様、公募推薦で受験したものの、結果は不合格になった時にまだ推薦枠が残っていれば申し込めます。
つまり、同時に出願する形での併用受験は難しいものの、落ちた後であれば受験するチャンスはあるのです。
このページのまとめ

今回は公募推薦と指定校推薦の違いについて解説してきました。いろいろな情報をご紹介してきましたのでこれまでの内容の整理のためにも改めて両者の相違点をまとめてみました。
| 公募推薦 | 指定校推薦 |
|---|---|
| 合否のポイント | |
| 以下の総合点
・評定平均 |
校内選考に通る事 |
| 受験可能な大学 | |
| 学校長からの推薦をもらえば基本的にどこでも受けられる | 高校に来た募集枠の大学のみ |
| 合格のための対策 | |
| ・評定平均を高める ・小論文の対策をする ・英検を取得する ・課外活動の実績を作る ・面接の練習をする ・大学への志望度を高める |
・評定平均を高める ・課外活動も頑張る ・皆勤賞を目指す |
| 合否の倍率について | |
| 大学による 通常は20%~50% |
校内選考に通れば100% |
最後になりますが、公募推薦と指定校推薦のどちらを利用すべきかを考える際にポイントになるのが、評定平均と学内の推薦枠です。
評定平均に自信があり、行きたい大学の推薦枠があるなら、校内選考に通れば基本的には合格が確約されている指定校推薦がおすすめ。
逆に行きたい大学の推薦枠がない場合や、自分よりも評定平均の高い人と校内選考の枠を争うことになる場合は、公募推薦を利用するのが無難です。
以上の内容を押さえて、自分に合った推薦形態で入試に取り組んでみてください。この記事をきっかけに、選択の幅が広がれば嬉しいです。
最後に公募推薦の勉強や対策はいつから始めるべきかについてまとめているページをご紹介しますのでご興味があればどうぞ。
最後になりますが、当スクール、ホワイトアカデミー高等部では推薦入試や総合型選抜の対策に特化したマンツーマンの対策授業を実施しております。
一般入試ではなく、推薦入試や総合型選抜での合格を目指したい人は、まずホワイトアカデミー高等部の無料相談会に参加して不安な点や気になる点を相談してみてください。

ホワイトアカデミー高等部とは?
総合型選抜・公募推薦入試に特化した専門塾。
プロ講師が活動実績作りから小論文・面接まで、
マンツーマンで徹底サポート。
- カリキュラム修了者の合格率98%※1
- 上智大学合格率83%(2025年度)※2
- 小論文・書類すべて添削無制限
- 全授業が社会人のプロ講師による1対1形式
- カリキュラム修了者には合格保証制度を提供

※2 上智大学合格率83%は2025年度入試における上智大学受験者が母数です。
この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。
過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。
昨年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。