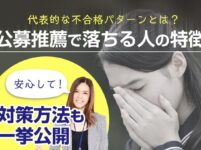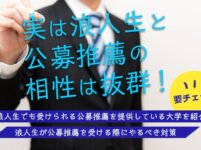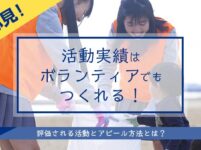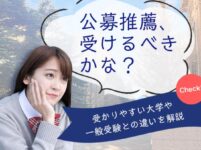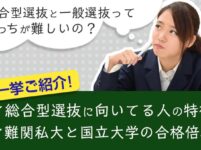BLOG

- 「指定校推薦を利用しての受験を考えているが、評定に不安がある…。」
- 「校内選考の基準はクリアしているけど、普段はまじめな方じゃないし…。」
このように、指定校推薦を使いたいけど評定がギリギリなため、どうしたらよいものかと困ってはいませんか?
そんなあなたのためにこの記事では、指定校推薦における評定平均の重要さの度合いや校内選考でチェックされるポイントを紹介します。
内容に目を通せば、ギリギリの評定平均でも校内選考を勝ち取れるケースや、ギリギリの評定平均が指定校推薦の合否においてどの程度不利になるのかまで分かります。
この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。
自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。
高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。
倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。
目次
指定校推薦の校内選考で評価される項目とは?
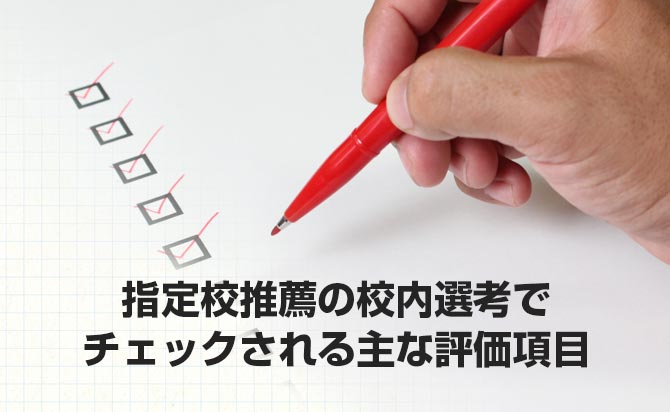
指定校推薦で大学を受験する場合は、校内選考を勝ち抜けることが必須です。校内選考では評定平均に加えて、以下のようなポイントが見られます。
- 学校側が安心して大学に推薦できること
- 課外活動の実績
- 出席具合や日々の素行
- 校内選考者向けの事前課題
校内選考では上記のポイントに加えて評定平均を確認し、学校の代表としてもっともふさわしい人が選出されます。
なかでも評定平均は、生徒の優秀さを見る際の客観的な指標になるので真っ先にチェックされると考えるべきです。
校内選考に通れば評定ギリギリでも指定校推薦で合格する
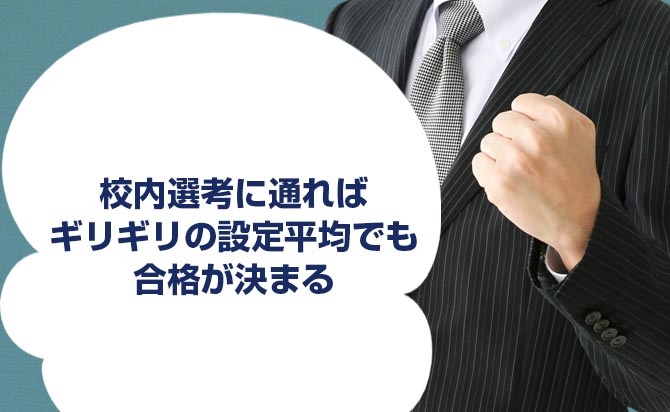
実は校内選考を無事に通過できれば、評定平均がギリギリでも本番の入試で落ちることは基本的にはあり得ません。
これは「指定校推薦」という入試システムの仕組みや意図に大きな理由があります。
高校と大学の信頼関係が前提にある
そもそも指定校推薦とは、大学側が特定の高校に対して推薦枠を与え、その枠数に応じて高校側が推薦するに値する学生を受験させる入試方式です。
高校側は「この子なら推薦しても学校の名に恥じない」という生徒を選びます。
逆に確実に入学する生徒を確保したい大学側は「高校がお墨付きを出している生徒は取った方がよい」という共通認識があるため、合格させるのが普通なのです。
つまり大学と高校との間に、ある程度の信頼関係があることを前提とした入試なので、高校側が推薦した生徒はほぼ確実に受かります。
問題を起こすことや当日の遅刻は厳禁
たとえ校内選考を通過しても、校内選考に通過した後に大きな問題を起こしたり、正当な理由以外で入試本番日に遅刻したりしていると、話は別です。
指定校推薦の合格通知が取り消されるほか、面接を受けた後に不合格が通知される可能性もあります。
そのため評定がギリギリとはいえ、校内選考に通った以上受かるのはほぼ確実ですが、高校の卒業日までは気を抜かないようにすることが大切です。
例外的に指定校推薦に落ちてしまう代表的なパターンについては、以下のページでより詳しくまとめています。
参考記事:例外的に不合格になる8つのパターン
校内選考における評定の重要性
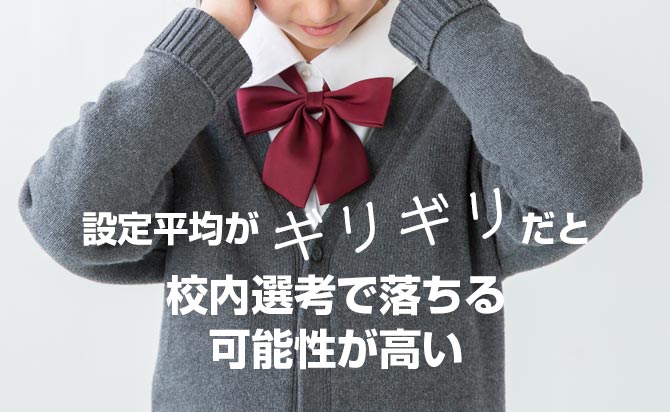
先ほど紹介したように、大学が定めた評定平均をギリギリでも超えていれば、入試の段階で落ちることはまずあり得ません。
しかし多くの高校では、希望すれば誰でも指定校推薦の枠を使えるというわけではなく、校内選考を実施した上で推薦する生徒を決めています。
そして、校内選考において評定平均が低いことはそれだけで不利になってしまうのです。
高校側が大学に推薦する「優秀な学生」を選ぶにあたって1番に重視するのは、学力と学習態度。この学力と学習態度をもっとも客観的に数値で表しているのが評定平均です。
評定平均は数値で表されるものなので、公平な形での順位付けや線引きがしやいという特徴があります。
しかも大学側も受験に必要な条件として評定平均を提示してくる以上、校内選考では非常に重視されるのです。
実は評定だけではない!校内選考で見られるポイント・受かるケースは?
評定平均がギリギリだと校内選考で不利になるのは事実です。
しかし校内選考は、評定だけではなく評定以外の部分も審査対象。つまり評定以外の部分が優れていれば、評定がギリギリであってもカバーできる可能性があるでしょう。
受験生の人間性・素行
校内選考では評定平均が高いことは有利に働きますが、評定平均以外のポイントも見られます。
よく見られるポイントはその人の人間性や素行です。なぜなら高校側の立場としては、安心して大学に送り出せる生徒を選ぶ必要があるためです。
高校側が安心して送り出せる生徒とは、何の問題も起こさずに4年で大学を卒業できそうな人。
つまり明らかに人間性に問題がある人や出席日数等に問題がある人は推薦されません。なぜなら高校側としても、不適切な生徒を推薦すると翌年度以降の指定校推薦枠が消える可能性があるためです。
課外活動の実績や事前課題の取り組み
校内選考では部活動やボランティアなどの経験や生徒会等の活動実績も考慮されます。
ライバルと評定平均が同じか、あるいは少し低い場合でも、それを挽回できるほどの実績があれば校内選考を通過できる可能性があるのです。
私が知る範囲でも、評定平均ではほかの候補者に見劣りしたものの、部活動で全国1位になったことが理由で選ばれたケースや、生徒会長だったことを評価されて選ばれたケースがありました。
もし何らかの実績を持っているのであれば、校内選考で積極的アピールするのがおすすめです。
このように、評定平均が高いだけでは校内選考で選ばれないこともあります。「校内選考では評定平均がもっとも重要であるとはいえ、評定がすべてではない」という点は押さえておきましょう。
なかには校内選考で課題を出すところも。内容は学校によって異なりますが、志望理由書や面接、小論文が代表的な課題です。
出欠状況
出席状況は学校の勉強に取り組む姿勢を判断する基準となります。
2022年以降、評価の項目として掲げられている「学びに向かう力、人間性など」はテストでは判断できない部分のため、出席・欠席日数で判断されるのです。
病気など理由のある欠席は配慮されますが、理由のない欠席や遅刻はマイナス評価になりかねないので注意が必要です。
校内選考者向けの課題の結果
校内選考のための課題の出来がよければ、それを決め手に選んでもらえる場合もあります。
課題は地頭を測られるだけではなく、その大学への志望度の高さややる気なども見られています。つまりあなたの本気度合いが伝われば評定平均の数字を覆すのも不可能ではないのです。
少しでも完成度を高めるために、課題を作成する際には親や周囲の大人に添削してもらうとよいでしょう。
出願者の人数
このケースはかなりラッキーですが、志望者が1人の場合は校内選考を行う必要はありません。つまり出願条件さえ満たしていれば、基本的にはその人が選ばれます。
そのため絶対に指定校推薦で大学進学を決めたいのであれば、人気のある大学を避け、少しレベルを落として確実に推薦枠が余りそうな大学を狙いに行くのも手です。
評定平均の計算方法と評価対象時期
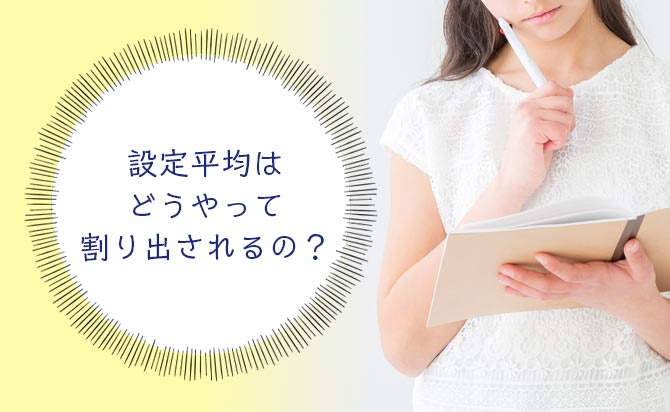
「評定平均がすごく重要なことは分かったけど、自分の評定平均はイマイチよく分かっていない」という人もいるでしょう。
そこでここからは、評定平均がどのように算出されるのかを理解いただくために計算式や計算の対象となる期間などを解説していきます。
基本的な計算方法
評定平均の計算方法はいたって単純です。
基本的には「これまでに履修したすべての科目の評定を合計したもの」÷「科目数」
で算出できます。
具体的なイメージをつかむために、実際の成績表でシミュレーションしてみましょう。
| 科目名 | 評定 |
|---|---|
| 国語 | 4 |
| 数学I | 3 |
| 数学A | 3 |
| 世界史A | 5 |
| 日本史A | 4 |
| 物理基礎 | 3 |
| 生物基礎 | 2 |
| 英語 | 3 |
| 英会話 | 4 |
| 音楽 | 3 |
| 体育 | 5 |
上記のような成績の場合、評定合計は4+3+3+5+4+3+2+3+4+3+5=39です。
これをすべての科目数で割るので39÷11=3.54…となり、評定平均は3.5と算出できます。
指定校推薦で利用する際の評定平均を調べるためには、高校1年生から3年生1学期までのすべての科目を足し合わせる形で、この計算をすればOKです。
また評定平均は担任の先生に聞けばすぐに教えてもらえるので、正確な成績を知りたい人は相談してみるとよいでしょう。
評価対象となる評定
指定校推薦の出願時期は、高校3年生の9~11月頃としている大学がほとんどです。そのため、基本的には高校3年生の1学期(前期)までの成績が評価の対象となります。
当然のごとく、高校3年生の前期だけ頑張っても評定平均を上げるのには限界があります。真剣に指定校推薦を狙うのならば、1・2年生のうちからテストを頑張っておくことが大切です。
大学側が定める評定平均をギリギリ下回ると…
大学が定める評定平均は、受験をするためにクリアしなければならない絶対条件。そのため0.1でも下回っていれば受験資格はありません。
万が一、何らかの手違いで高校から推薦してもらえることになっても、大学側の審査で基本的には落ちてしまうので注意が必要です。
後から気付いても手遅れなので、自分の評定平均や計算の対象となる期間などは事前にしっかり確認しておきましょう。
ギリギリのスコアで指定校推薦を受ける際の注意点
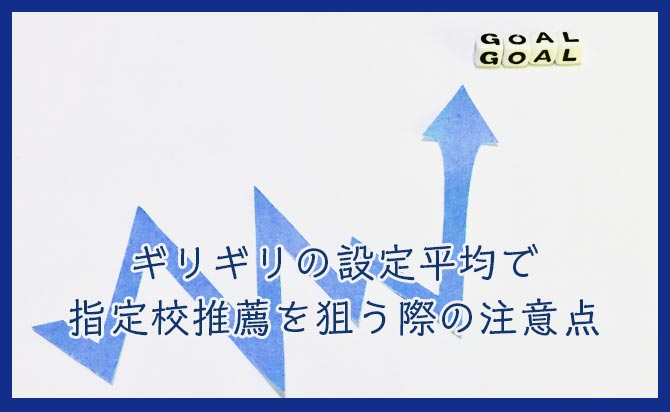
次にギリギリのスコアで指定校推薦を受ける際の注意点について説明します。
指定校推薦が使えるに越したことはありませんが、もしもの場合を考慮してほかの選択肢も用意しておくと安心です。
校内のライバル次第では出願校を変える
自分よりも明らかに優れていると分かる人が同じ大学を受けようとしている場合は、受かる見込みはかなり低いと考えるのが普通。
ここで無謀な勝負に挑むぐらいなら、ほかに指定校推薦の枠がある大学に出願先を変えるのも手です。
腹の探り合いのようであまりいい気分にはならないかもしれませんが、周囲の人たちがどこに出願しようとしているのかをリサーチしておくと役に立つかもしれません。
一般入試や総合型選抜や公募推薦の準備もする
校内選考があるにもかかわらず、指定校推薦を利用することだけを見据えて受験の準備をするのは危険です。
校内選考で落ちることは割とあるので、落ちたときのことも想定し、その後の動きを考えておきましょう。
ちなみに指定校推薦がダメだった場合は、
- 一般入試を受ける
- 総合型選抜(旧AO入試)を受ける
- 公募推薦を受ける
のいずれの選択肢の中からどれかを選ぶのが一般的。
特に総合型選抜(旧AO入試)や公募推薦は、評定平均や課外活動の実績といった指定校推薦の校内推薦の評価項目がそのまま評価されます。
そこで指定校推薦に落ちた後には総合型選抜(旧AO入試)への乗り換えや公募推薦の利用を考えたいですね。総合型選抜(旧AO入試)と公募推薦の特徴と相違点については以下のページでまとめております。
ちなみに一般入試に関しては学力さえあれば誰でも受けられる反面、それなりの勉強が必要なので注意が必要です。
校内選考の突破後も評定を落とさないようにする
たとえ校内選考に通ったとしても、3年生の1学期までの評定平均がギリギリの場合は注意が必要。
2学期の評定平均が悪いと、3年間全体での評定平均が基準を下回ってしまう恐れがあるためです。
あまり想像したくないかもしれませんが、仮に下回ると大学から合格を取り消される場合あります。
合格後の取り消しを防ぐためにも、校内選考が終わった後も今の評定を落とさないくらいの勉強はしておきましょう。
このページのまとめ

指定校推薦と評定平均の関係について理解していただけたでしょうか?
最後にこれまでの内容の確認も含めて、指定校推薦に挑戦する際に、評定平均関連で特に押さえておきたい4つのポイントを列挙してみました。
- 評定平均が低いと校内選考で不利になる
- 高校3年生の1学期(前期)までの評定平均が基準となる
- ライバルの状況を見て出願先の変更を検討してみる
- 一般入試やAO入試の利用も考えておく
以上のことを考慮した上で、どのような形で指定校推薦に臨むのが1番よいのか、今一度考えてみましょう。
最後に今回の内容と併せて目を通していただきたいページをご紹介します。
⇒校内選抜で落選する主な原因と落選後の選択肢
この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。
過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。
昨年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。

ホワイトアカデミー高等部とは?
総合型選抜・公募推薦入試に特化した専門塾。
プロ講師が活動実績作りから小論文・面接まで、
マンツーマンで徹底サポート。
- カリキュラム修了者の合格率98%※1
- 上智大学合格率83%(2025年度)※2
- 小論文・書類すべて添削無制限
- 全授業が社会人のプロ講師による1対1形式
- カリキュラム修了者には合格保証制度を提供

※2 上智大学合格率83%は2025年度入試における上智大学受験者が母数です。