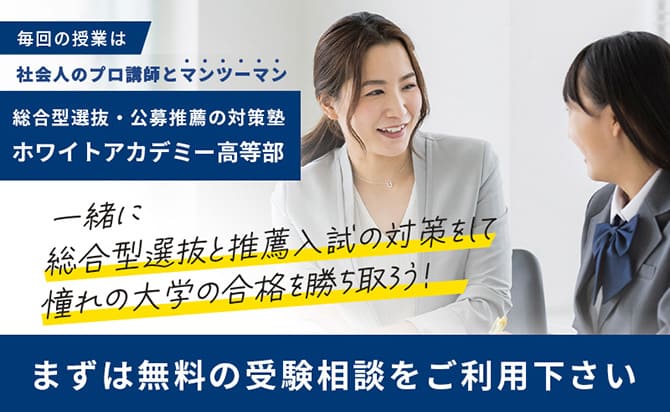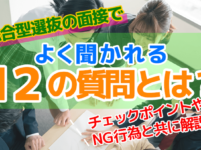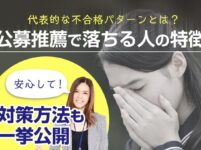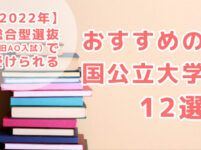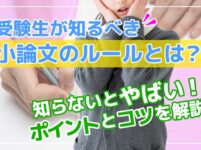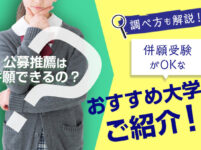BLOG

- 「活動報告書の書き方が分からない」
- 「部活の内容は活動報告書に書けるの?」
このようなお悩みを抱えている高校生は少なくありません。それにもしかしたらあなたもその一人かもしれません。
そこで今回は、活動報告書の重要性や記述することになる主な内容、書き方や例文などについて解説します。
活動報告書に何を書くか迷っている方も、これさえ読めば活動報告書の作成に困らないので、ぜひ最後までお付き合いください。
なお、今すぐにでも活動報告書をプロにチェックしてもらいたい方や、活動報告書の書き方をいちから学びたい方は、ホワイトアカデミー高等部にお任せください。総合型選抜・公募推薦の対策に精通したプロの講師が、あなたの志望校に合わせて適切な活動報告書の作り方をお教えします。
活動報告書はもちろん志望理由書などの書類作成もサポートしますので、ご興味のある方はまず無料の受験相談会に参加してみてください。↓
この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。
自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。
高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。
倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。
目次
大学入試の活動報告書に部活の内容は使えるのか?

活動報告書とは、自身の経験や経歴を記載したものです。
学生時代にしていたスポーツや文化活動、ボランティア活動などを通じて、自身が得たものを紹介します。大学に評価される活動報告書を作成するには、活動報告書に関する正しい知識が不可欠です。
そこでここからは活動報告書の特徴や重要性について詳しく解説しています。
総合型選抜(旧AO入試)や公募推薦に合格するには活動報告書が重要
総合型選抜(旧AO入試)や公募推薦の合格を目指す上で活動報告書は非常に重要な要素です。
なぜなら、活動報告書は総合型選抜や公募推薦の出願時に提出を求められ、一次選考では志望理由書や調査書とともに審査されるからです。審査対象の出願資料である以上、活動報告書の充実度合いは合否判定の1つの要素になる点は認識しておきたいですね。
それに、「とりあえず書類だけ用意しておけばいいだろう」といい加減に書かれた活動報告書では、一次選考で落ちる可能性もあります。
そのため、自分がこれまでに積み重ねてきたものが大学側に伝わるように、客観的かつ説得力のある文章を書く事を心がけましょう。
活動報告書には3つのタイプがある
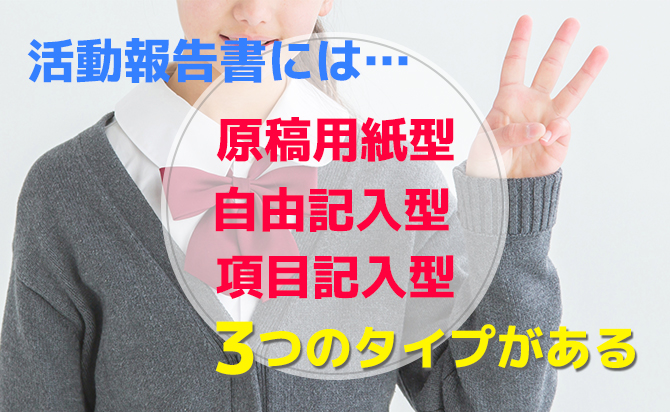
一般的な活動報告書は以下の3つの形式に大別することができます。
- 原稿用紙型
- 自由記入型
- 項目記入型
今取り上げた3種類の形式の特徴についてはこれからご紹介します。
原稿用紙型
原稿用紙型は、文字通り原稿用紙形式で活動報告書を作成する形式です。このタイプは大学側から「〇〇字以内で記入してください」といった文字数の指定があります。
自由記入型
自由記入型は、白紙に記入する形式の活動報告書です。「用紙1枚に記入してください」とざっくりとした指定が多く、一般的に600字~800字程度が収まるスペースの場合が多くなっています。
項目記入型
項目記入型は、大学が指定した項目ごとに記入していく形式です。何を書くのかを大学側から細かく指示されるので、この中では最も書きやすい形式と言えます。
大学によって形式は異なるので、出願要項を確認して、どのようなタイプの活動報告書なのかチェックしておきましょう。
活動報告書には部活の内容が使える
活動報告書と聞くと、ボランティア活動や課外活動について書いたものを想像する方が多いかも知れません。
しかし、実際には部活動の内容も活動報告書に使えます。
なぜなら活動報告書では自身が意欲的に取り組んだものについて書くので、スポーツ系・文化系問わず部活を題材とした活動報告書の作成が可能になるためです。
「自分は学生時代に特別なことに取り組んだことがないから活動報告書を書けない」と考えてしまう学生の方も、自分の部活動のことについて書けば大丈夫です。
活動報告書に書くために部活の大きな実績は必要ない
活動報告書を書くにあたって、部活の大きな実績は必要ありません。
大会で優勝した経験やコンクールで入賞した経験など、目立った実績がなくても、活動報告書に部活動のことを書くことができます。なぜならば、大事なのは「目立った実績の有無ではなく、部活の活動を通じてどのような経験をして成長できたか」だからです。
「活動報告書に書くような経験をしていない」という学生の方は、自身でハードルを上げ過ぎずに、一度、部活動に関するエピソードをリストアップしてみましょう。可能であれば、周りの人間にアドバイスをもらうのもおすすめです。
参考記事:十分な実績がない時の出願書類の作り方
部活の内容を使って活動報告書を書く4つのステップを紹介

部活の内容を使って活動報告書を書く際は、次の4つのステップを意識することが大切です。
- 自分の部活動の内容を掘り下げる
- 活動報告書の構成を考える
- 活動報告書の下書きを作成する
- 下書きを修正し活動報告書に記入する
自分の部活動の内容を掘り下げる
活動報告書を書く前に、自分の部活動での出来事を紙に書き出し、それぞれを掘り下げましょう。
紙に書き出すことで頭を整理でき、自己アピールにつながるエピソードを見つけられます。
掘り下げのコツは、その活動で得られたことや、その活動のために努力したことに焦点を当てて考えることです。
加えて大会での勝ち負けなどの実績やコンクールでの入選など、結果に対しての掘り下げだけではやや不十分です。
出来ればどのような工夫をして部活動に励んだか、監督・顧問、先輩、同級生、後輩とどのように関わったかなどの視点でも掘り下げてみるとあなたの個性に気づきやすくなります。
加えて上記の掘り下げを行う際にはあなたの行動だけでなく感情にも注目してみると良いでしょう。
活動報告書の構成を考える
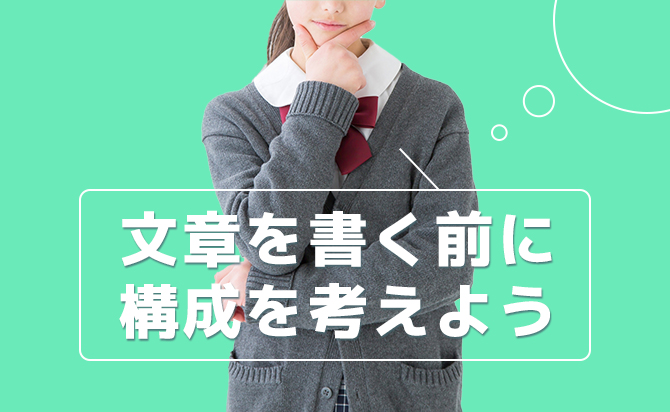
活動報告書に書く部活の内容が決まったら、構成を考えます。実は文章を書く前に構成を考えるというのは本当に大切です。
なぜなら、構成無しで書き始めると、何を伝えたいのか分からない文章になってしまう場合があるからです。そこでおすすめしたいのはこれからご紹介する流れで構成の作成に取り組むことです。
- 書きたい部活動のエピソードを示す
- エピソード内の自分の役割を示す
- エピソードで自分が努力した内容を示す
(具体的に何に取り組んだのか明確にする) - 結果として自分が何を得て何を学んだのか示す
特に重要なのが、あなたが部活で取り組んだことを明確にすることです。あなたが取り組んだ事があいまいな場合、大学側にあなたが部活で何をやったのかが伝わりません。
活動報告書の下書きを作成する
活動報告書の構成が完成したら、下書きを作成します。
下書きをせずに活動報告書を作成すると、誤字脱字の修正など、余分な手間がかかってしまいます。本番の用紙に記入する前に、下書きしておきましょう。
加えて下書きを作成する際に意識しておきたい点としては以下があります。
- 指定の文字数を守っているか
- 文体は一貫しているか(敬体・常体のいずれかで統一されているか)
- 構成の流れが前後していないか
- 冒頭で示した流れから論点がずれていないか
下書きを修正し活動報告書に記入する
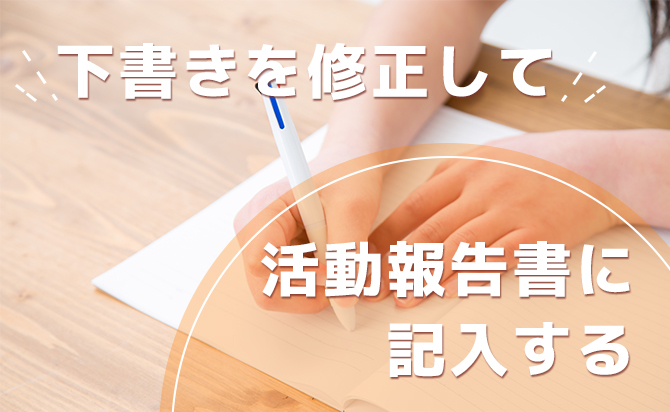
下書きが完了したら、活動報告書に記入する前に最終チェックを行いましょう。
自分でどれだけチェックしても、文法の誤りや誤字・脱字に気づかない場合があります。可能であれば、家族か友人、高校の先生にチェックしてもらうのがおすすめです。
下書きの修正が完了したら、活動報告書に記入します。誤字・脱字のないよう、下書きをよく見ながら記入しましょう。
活動報告書を書くときの3つのポイントを解説

活動報告書を書くときは、次の3つのポイントを守ることが重要です。
自分の活動をなるべく具体的に書く
活動報告書は、自分の活動内容を具体的に評価して記入しましょう。
例えば、スポーツ系の部活なら「大会に向けて練習を頑張った」と書くのではなく、「大会で地区予選ベスト16という結果を出した」という形で書きましょう。
上記のように具体的な記述をすれば大学側にどんな活動をしたのかがはっきりと伝わります。
志望する大学の学部や学科が求めている学生像に合わせて書く
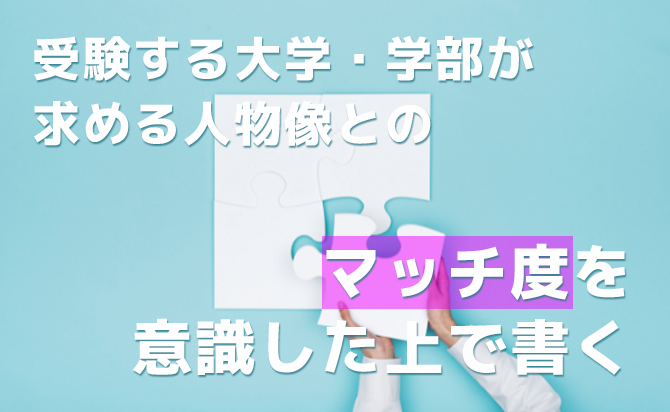
活動報告書は、志望する大学の学部や学科が求めている学生像に沿って書くことが大切です。
志望校の募集要項やアドミッション・ポリシーを確認して、その大学が求めている学生像を分析してください。他にも大学のホームページやパンフレットを確認をすれば大学が学生に求めている要素が分かります。
真面目な学生や元気な学生、自立心のある学生など、大学側が求めている要素をアピールするように活動報告書を書くことが大切です。
参考記事:アドミッションポリシーの特集ページ
活動中の失敗経験も書く
活動報告書には失敗経験を書くのもおすすめです。
どのような失敗をして、そこから何を学び、どう活かしたのかを具体的に書くことで、説得力のある活動報告書を書けます。
「どうしても活動報告書に書く内容が見つからない」という方でも、自身の失敗談は見つかるのではないでしょうか。それを深堀りし、失敗を糧に成長したといった内容で活動報告書を書きましょう。
【400字】で例文を作成
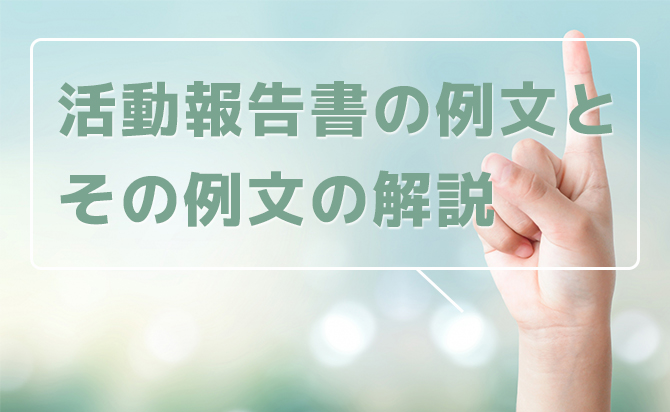
次に部活の内容を使った活動報告書の例文を紹介します。例文はそのまま引用するのではなく、書き方や構成の参考にするようにしてください。
400字以内、原稿用紙型の例文
残念ながらレギュラーにはなれませんでしたが、グラウンドの整備や道具の手入れなどを率先して担当し、チームが戦いやすくなるように努力しました。
高校3年次には地方予選で1勝を目標に定め、勝てるチーム作りのために、部員一人一人と向き合い、信頼関係を向上させる努力をしました。
例として、練習後のミーティングでは積極的に発言するようになり、初心者の部員の基礎練習に混ざってアドバイスをするようになりました。
初めはまとまりがなく、チームに協調性が感じられませんでしたが、徐々にお互いを信頼するようになり、試合中のプレイにもそれが現れるようになりました。
結果は、惜しくも1勝はできませんでしたが、一つの目標に向けて努力し、話し合いや行動ができるようになりました。また、これらの行動が集団での信頼関係を築くために大切なことを学びました。
確認すべきポイント
上記の例文で特に見てほしいのが、部活動で何を行ったのかを具体的に記述している点です。
例えば、「チームが勝てるように努力した」という部位は以下のような具体的な記述があるのであなたがやったことが良く分かると思います。
- 「練習後のミーティングでは積極的に発言するようになった」
- 「初心者の部員の基礎練習に混ざりアドバイスをするようになった」
上記のように具体的な記述を心がければあなたが部活動でどんな取り組みをしたのかが良く伝わる文章になります。
部活動の内容を活かして活動報告書を作成しよう
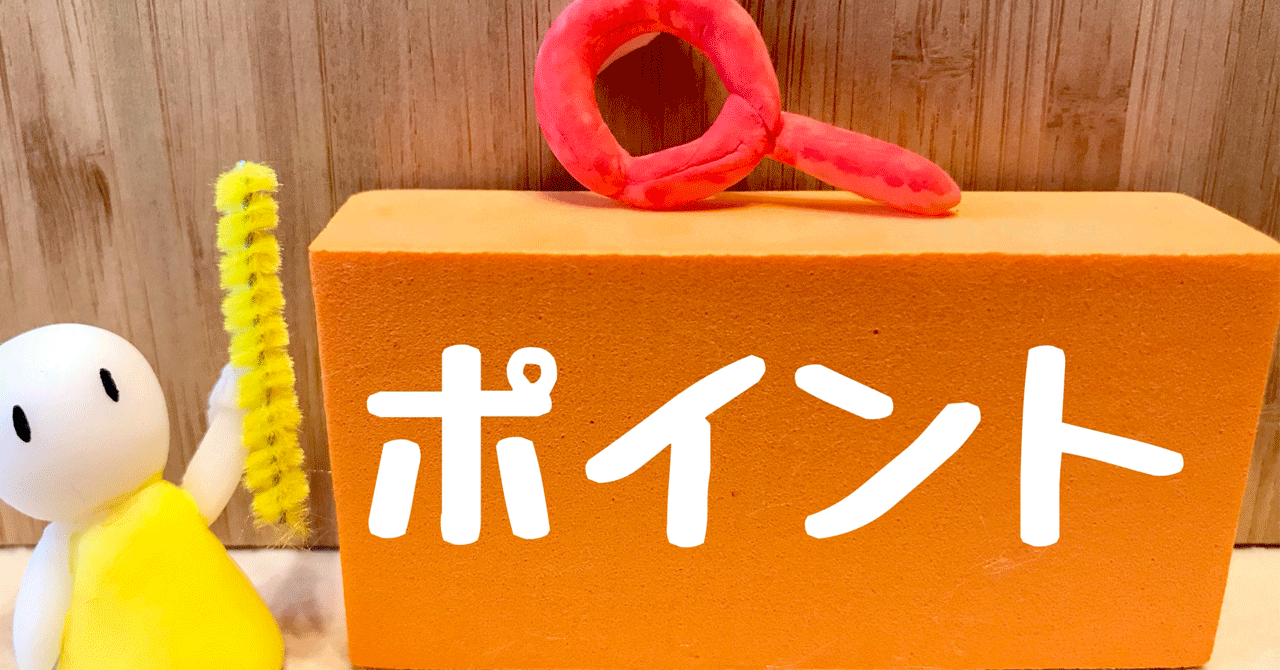
部活動で大きな実績がなくても、部活の経験の深堀りをすれば活動報告書にふさわしいエピソードが見つかります。そのため、まずは部活のエピソードの深掘りに取り組む事をおすすめします。
最後に今回の内容のポイントをまとめましたので、目を通しておいてください。
- 活動報告書の内容として部活動のエピソードが使える
- 記述するエピソードには大きな実績は必要ない
- 質の高い活動報告書を作るためにも部活動のエピソードを深堀りする
- 文章を作成する前に構成を作っておくことが大切
- 活動報告書の下書きは家族や先生にチェックしてもらうのがおすすめ
- 文章はなるべく具体的に書く事を心がけるべき
- 大学が求めている学生像に沿って活動報告書を書くことが大切
- 部活での失敗エピソードも活動報告書には使える
良い活動報告書を書ければ、大学の一次選考を有利に進められます。ぜひ今回の記事の内容を参考に活動報告書を作成し、総合型選抜や公募推薦の合格を目指してください。
最後になりますが、総合型選抜の出願の際には活動報告書と併せて調査書や志望理由書の提出が求められます。特に前者の調査書に関しては基本的に全ての大学が提出を求めるので活動報告書の準備と併せて余裕をもって用意をする事をおすすめします。
なお、本記事を読んで活動報告書を作成できるか不安になった方は、ホワイトアカデミー高等部にお任せください。総合型選抜の合格ノウハウを持つプロの講師が揃っており、あなたの志望校に合わせてより良い活動報告書が書けるようにサポートします。
エピソードの深掘りや大学が求める学生像に沿っているかのチェックなどもカバーしているので、自力での対策が難しいと感じる方はぜひ無料の受験相談会に参加してみてください。↓
無料相談会への参加申し込みはこちらから

ホワイトアカデミー高等部とは?
総合型選抜・公募推薦入試に特化した専門塾。
プロ講師が活動実績作りから小論文・面接まで、
マンツーマンで徹底サポート。
- カリキュラム修了者の合格率98%※1
- 上智大学合格率83%(2025年度)※2
- 小論文・書類すべて添削無制限
- 全授業が社会人のプロ講師による1対1形式
- カリキュラム修了者には合格保証制度を提供

※2 上智大学合格率83%は2025年度入試における上智大学受験者が母数です。
この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。
過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。
昨年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。