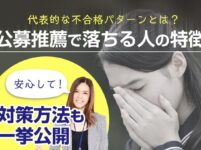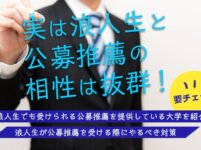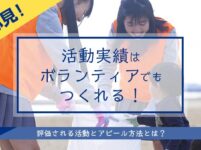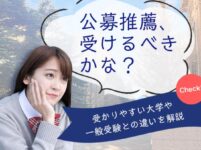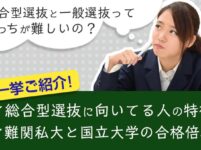BLOG

「総合型選抜(旧AO入試)でプレゼンテーションがあるが、どう対策すれば良いのか分からない」とお悩みの受験生も多いのではないでしょうか。
プレゼンテーションが課される大学・学部の総合型選抜(旧AO入試)において、プレゼンテーションの出来栄えは合否に大きな影響を与えます。
なぜならプレゼンテーションは大学から課されている以上、大学が受験生の合否を決める際の評価項目の対象にしているためです。
しかし普通に高校生活を送るとなかなか人前で何かを準備してプレゼンする機会には恵まれないもの。
そこで本記事では、総合型選抜(旧AO入試)のプレゼンテーションを対策する際のポイントや上手に実演を行うコツ等を解説します。
この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。
自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。
高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。
倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。
目次
総合型選抜(旧AO入試)で課されるプレゼンテーションとは?
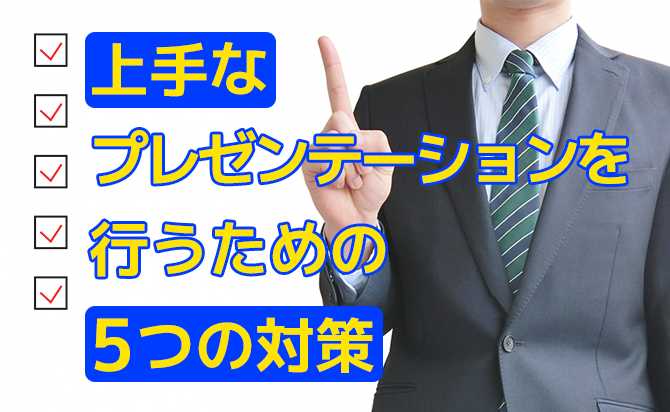 プレゼンの形式や用意する資料の形式は志望する大学・学部次第なので、募集要項を確認しましょう。
プレゼンの形式や用意する資料の形式は志望する大学・学部次第なので、募集要項を確認しましょう。
発表との違い
プレゼンテーションはよく発表と混同されがちですが、両者には大きな違いがあります。
前者の「プレゼンテーション」は、相手の立場に立ち相手にとって有益な情報を伝えるもの。双方のやりとりが可能である点が特徴的で、聞き手は質問や意見を述べられます。
一方後者の「発表」は、自分の考えや調べたことなどを相手に伝えるものです。聞き手からの質問に答える必要はありません。
今取り上げたようにプレゼンテーションと発表は別物なので、両者の根本的な相違点はしっかり押さえておきましょう。
ぜひとも実施したい5つの対策方法
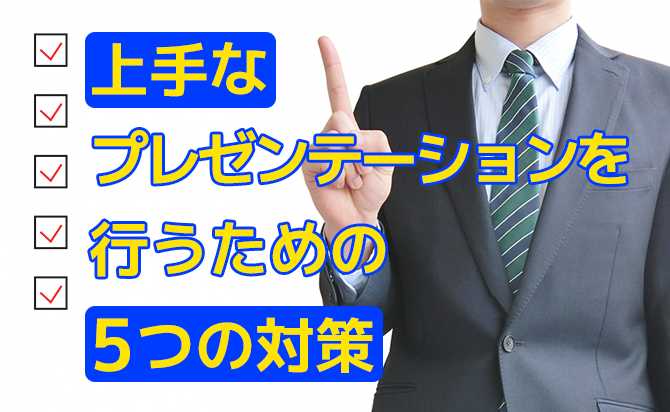
総合型選抜(旧AO入試)のプレゼンテーションは、小論文や面接のように合否を左右します。
そのため、総合型選抜(旧AO入試)で合格を勝ち取るためには、プレゼンテーションの対策が欠かせません。プレゼンテーションの効果的な対策方法については、これから1つずつ解説していきます。
うまい人のやり方を見る
プレゼンテーションの練習をする前に、うまい人のやり方を見るのがおすすめ。どのようなプレゼンテーションが評価されるのかを知らないと、なかなか上達しないためです。
上手なプレゼンテーションを見て、評価されるポイントについて分析してみましょう。分析した中で自分でもできそうなものがあれば練習で真似してみます。最終的には自分のモノにできるでしょう。
話し方だけではなく、ジェスチャーやスライドの使い方などで良いと思う点があれば、積極的に盗むことが大切です。
私が見た中で参考になる動画の一例をご紹介しますのでぜひご覧ください。
3分程度の短時間プレゼンテーションを繰り返す

プレゼンテーションの経験がない人は、3分程度の短いプレゼンテーションの練習を繰り返しましょう。
短時間プレゼンテーションを繰り返すことによって、物事を簡潔かつ分かりやすく伝えられるようになります。
プレゼンテーションは限られた時間の中でいかに自分が伝えたいことを相手に伝えられるかが重要なポイントなので、3分程度の短時間プレゼンテーションは非常に効果的です。
自分の話している様子を録画する
プレゼンテーションの練習に慣れてきたら、自分のプレゼンテーションを録画して振り返りましょう。
自分がどのように話しているのかは、自分ではなかなか分からないものです。話し方で改善できる点はないか、ジェスチャーを取り入れているかなど、自分自身で客観的に評価してみましょう。
録画を観ることで、それまで気付かなかった改善点を見つけられるはずです。
質疑応答の内容を予想する
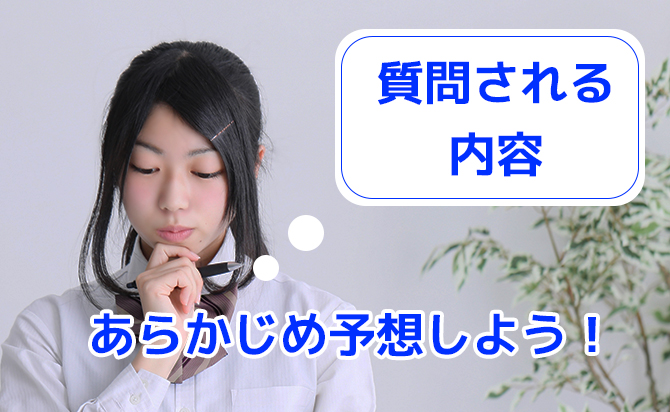
プレゼンテーションが終わると、プレゼンテーションの内容に対して面接官が質問してきます。
質疑応答も重要な採点ポイント。話し方やスライド資料の完成度が高くても、質疑応答がうまくいかないとプレゼンテーション全体の評価は落ちてしまいます。
「こういう質問をされたらこう答えよう」と何度も事前にシミュレーションをしておくと、質疑応答に自信を持って対応できるようになるでしょう。
プロの指導を受ける
どうしても総合型選抜(旧AO入試)で進学したい場合は、専門塾に通いプロの指導を受けましょう。プレゼンテーション力を自力で上げるには、予想以上に時間がかかることが多いためです。
受験対策に費やせる期間は限られているので、総合型選抜(旧AO入試)の対策を効率良く進めるためにもプロの力を借りるのがおすすめです。
専門の対策塾を利用すれば指導を受けられるのはもちろん、自力で調べても出てこなかった志望大学の情報を得られるといったメリットもあります。
プレゼンの原稿を作成する際のポイント
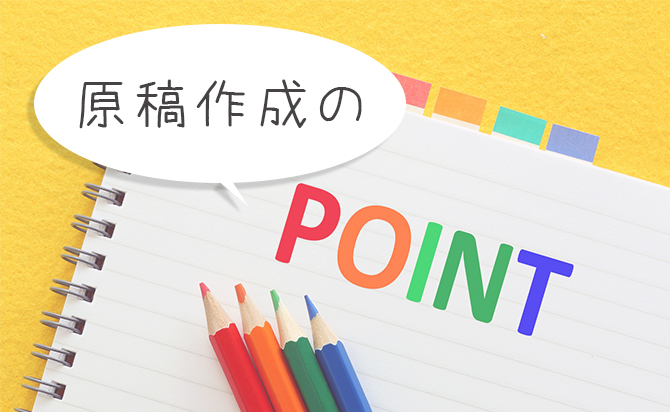
プレゼンテーションを成功させるためには、良い原稿の準備が必要不可欠です。下記で解説する原稿作成時のポイントを押さえて、原稿を書いてみましょう。
目的を明確にする
プレゼンテーションの原稿を書き始める前に、プレゼンテーションを通して面接官に何を伝えたいのかを明確にすることが大切です。目的が曖昧なまま原稿を作成すると、一貫性の無いプレゼンテーションになってしまいます。
プレゼンテーションの軸となる目的を明確にすることで、結論までの展開がスムーズで説得力のあるプレゼンテーションに仕上がります。
目的を明確にするためには、相手が「何を聞きたいか・知りたいか」を整理することが必要です。その上で、自分が一番伝えたいことを20〜30文字でまとめておくと良いでしょう。
代表的なプレゼンの型を使う

ただ言葉を並べるだけでは、面接官を説得させられません。プレゼンテーションの原稿を作成するときには、全体の構成から決めていくことをおすすめします。
プレゼンテーションの代表的な型は3つあるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
PREP法
まずはPREP法。PREP法の4つの構成要素は下記の通りです。
- Point(結論)
- Reason(理由)
- Example(実例)
- Point(結論)
PREP法は最初に結論を述べ、最後にまとめとしてもう一度結論を述べる方法のことです。
最初に話の要点を伝えれば、聞き手は内容を知った上で話を聞けるため、理解しやすくなります。
SDS法
SDS法を構成する3つの要素は以下の通りです。
- Summary(要点)
- Details(詳細)
- Summary(要点)
SDS法は上記の順番の通り、最初に全体の概要を伝えます。そして次に具体的な説明を行い、最後に全体のまとめとして要点を伝えます。
SDS法は、詳細を述べた後に最初に伝えた概要を繰り返すため、聞き手の記憶に残りやすいのが特徴です。
DESC法
DESC法は、問題解決型のプレゼンテーションに有効な方法です。各要素は以下の通りで、D⇒E⇒S⇒Cの順番で進めていきます。
- Describe(描写)
- Express・Explain(表現・説明)
- Suggest・Specify(提案・具体例)
- Choose・Consequence(選択・結論)
最初に状況を客観的に伝え、次に問題点や主観的な意見を述べます。
そして問題点や意見に対する具体的な解決方法を提案し、最後に提案した解決方法による効果や結果を伝えるという流れです。
時間配分を意識する
ほとんどのプレゼンテーションには制限時間があります。プレゼンテーションの完成度がどんなに高くても、制限時間が守れていないと減点の対象になるので注意が必要です。
制限時間を守るためには、プレゼンテーションの練習から時間を意識することが大切です。
ただし10分のプレゼンテーションに対して、10分で収まるように練習していては、本番で時間内に収まらない可能性があります。本番では話が想定外に脇にそれたり、面接官から途中で質問されることがあるためです。
10分のプレゼンテーションの場合は、8分程度に収まるように練習すると良いでしょう。
上記で説明した構成をもとにすると、プレゼンテーション内の時間配分を決めやすくなるはずです。
プレゼンテーション資料の作り方

プレゼンテーションの資料作りに使うアイテムは、パワーポイントやポスターなどさまざま。いずれの場合も、より相手に伝わりやすい内容に作ることが大切です。
パワーポイント
パワーポイントは、資料を1ページずつスライドして見せていくのが特徴。そのため総ページ数が多くなってしまうと、何枚もスライドを変えなければならず、発表する側も聞く側も大変です。
ページをめくりすぎるがあまりに、話の内容が伝わりにくくなる可能性もあるでしょう。1〜2分に1枚スライドするくらいのペースが理想的です。
また色の数や文字の大きさ・フォントにも気を配りましょう。色を増やしすぎないこと、ゴシック体のような見やすいフォントで小さくしすぎないことを意識してみてください。
ポスター
ポスターは遠くから見ても分かりやすくまとめることが大切です。書く見出しごとに分けてまとめ、流れが分かりやすいようなレイアウトを心がけましょう。
文字ばかりだと情報量が多くて見る側が疲れてしまう可能性も。時折図表を入れるなどしてメリハリを付けるのがおすすめです。
あくまでも「見やすさ」を意識し、ダラダラと長文を書くのではなく、内容がひと目見て伝わるよう箇条書きで書くと良いでしょう。
1枚に情報を詰め込みすぎず、ある程度の余白を作ることも大切です。
効果的にプレゼンを行うコツ

プレゼンテーションは決して簡単なものではありませんが、コツを掴むことによって上手にできるようになります。どのようなコツがあるのかそれぞれ見ていきましょう。
大きな声でゆっくりと話す
大きな声でゆっくりと話すことは、プレゼンテーションの基本中の基本です。特に緊張していると、自分が思った以上に早口になっていることが多いので、本番は練習よりも少しゆっくりめに話すように心がけましょう。
またはっきり話すことも大切です。
面接官に自分の伝えたいことが伝わらないと、プレゼンテーションの内容がどんなに良くても評価が低くなります。
話し方に抑揚を付ける

プレゼンテーションではメリハリが大切です。単調にならないよう、一番伝えたいことを話すときは少し強調して話すようにしましょう。また面接官に質問を投げかける際は、少し間を開けてみることをおすすめします。
聞き手が頭の中で答えを考えるようになり、自然とプレゼンテーションに引き込まれていきます。
ただし質問する場合は、聞き手と自分の立場の違いを考慮することが大切です。質問の投げ方によっては、上から目線で不快感を与えてしまう場合があります。
話し言葉を使って語りかけるように話せば、相手に与える印象がより良くなるでしょう。
ジェスチャーを取り入れる
時々ジェスチャーを交えて話すと、内容を相手に印象付けられます。
例えば「2つのポイントがあります」という時には、聞き手が分かりやすいように手で「2つ」を表すと良いでしょう。
ただし終始ジェスチャーを使っていると、ジェスチャーしている動きばかりが気になって、内容が頭に入ってこなくなってしまう恐れがあります。強調したい部分にだけにジェスチャーを使えば効果的です。
相手の目を見て話す

人が話を聞く時は、話している相手の目を見るものです。そのため話し手の視線が動きすぎると、「伝えたい」という気持ちが相手になかなか届きません。
聞き手一人ひとりの目を意識し、1人あたり1〜3秒くらい見るように心がけましょう。
姿勢を正す
良い視線は自信の表れ、また発表者に情熱があるとも感じてもらえるポイントです。猫背にならないよう気を付け、あごを引く・背筋を伸ばす・胸を張るという3つのポイントを意識してみましょう。
無表情ではなく時折笑顔を見せる

笑顔を時々見せることは好感度アップにつながります。好感度が高ければ「この人の話をもっと聞きたい」と相手に思わせることにも。
特に相手に印象付けたい内容の時は「笑顔」を意識してみましょう。
総合型選抜(旧AO入試)でプレゼンテーションを課す主な有名大学
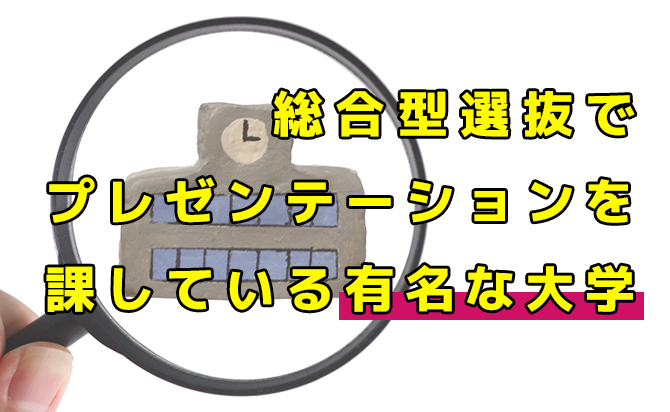
次に総合型選抜(旧AO入試)でプレゼンテーションを課す主な有名大学をプレゼンテーションの内容と併せて紹介します。
私立大学編
| 大学名 (学部) |
プレゼン内容 |
|---|---|
| 立命館大学 (映像学部) (絵コンテ作画型) |
与えられた課題に対する絵コンテを作成し、作成した絵コンテに関する口頭形式でのプレゼンテーションを実施
制限時間:20分程度(質疑応答を含む) |
| 関東学院大学 (比較文化学科) |
これまで行ってきた、異文化理解・多文化共生に関する探究活動や、それらに類する活動を取り上げてプレゼンテーションを行う。 制限時間:10分 以下の準備が必要 |
| 日本大学 (経済学部) |
1次選考で提出した小論文(研究課題)についてプレゼンテーションを行う。
制限時間:20分程度(質疑応答含む) |
プレゼンテーションと一口に言っても内容は大学によって異なるので、志望大学の募集要項をしっかりと確認するようにしましょう。
・参照元:「2025 年度(総合型選抜)AO 選抜入学試験 映像学部「プレゼンテーション方式 (映像撮影型、絵コンテ作画型)」 入学試験要項」立命館大学
・「2025 年度 総合型選抜(9月募集)課題型(プレゼンテーション)」関東学院大学国際文化学部 比較文化学科
・「総合型選抜(プレゼン)」日本大学経済学部
国立大学編
| 大学名 (学部) |
プレゼン内容 |
|---|---|
| 横浜市立大学 (国際商学部) |
「これまでの活動や取り組みで自己評価できるもの」、「志望理由・入学後の目標」をプレゼンする。 制限時間:30分(質疑応答20分) 準備する資料:以下 |
| 東京農工大学 (工学部) |
特別活動レポートの内容に関するプレゼンテーションを行う。 制限時間:受験する学科次第 |
| 都留文科大学 (教養学部 学校教育学科/図画工作系) |
造形活動の内容を発表する。
制限時間:20分 準備する資料:以下のどちらか |
上記のように各大学が求めるプレゼンテーションの内容は変わります。そのため、志望する大学・学部の募集要項についてはきちんと確認しておきましょう。
・参照元:「総合型選抜 2025年度募集概要」横浜市立大学
・「令和6(2024)年度 入学者選抜要項」東京農工大学
・「2024年度 総合型選抜 教養学部 学校教育学科 学生募集要項」都留文科大学
このページのまとめ

ここまで、総合型選抜(旧AO入試)のプレゼンテーション対策法や成功させるコツ等について解説しました。以下は、今回取り上げた内容の中で特に重要なポイントです。
特に重要なポイント一覧
- プレゼン力を上げるためには、練習の積み重ねが大事
- 簡潔に分かりやすく伝えることが重要
- 伝える内容に加えて、質疑応答も評価のポイントになる
- プレゼンテーションの原稿は構成を意識して作成する
総合型選抜(旧AO入試)のプレゼンテーションは、小論文や面接のように合否に大きく影響します。今回の記事を参考にして、総合型選抜(旧AO入試)のプレゼンテーションを成功させましょう。
最後になりますが、当スクール、総合型選抜並びに公募推薦の対策の専門塾ホワイトアカデミー高等部ではプレゼンテーションの対策授業も実施しています。自力でのプレゼンテーションの準備や対策が難しい場合は是非ご利用下さいませ。
この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。
過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。
昨年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。

ホワイトアカデミー高等部とは?
総合型選抜・公募推薦入試に特化した専門塾。
プロ講師が活動実績作りから小論文・面接まで、
マンツーマンで徹底サポート。
- カリキュラム修了者の合格率98%※1
- 上智大学合格率83%(2025年度)※2
- 小論文・書類すべて添削無制限
- 全授業が社会人のプロ講師による1対1形式
- カリキュラム修了者には合格保証制度を提供

※2 上智大学合格率83%は2025年度入試における上智大学受験者が母数です。