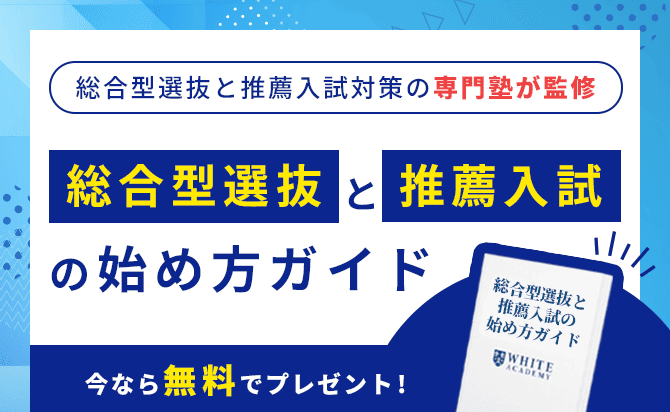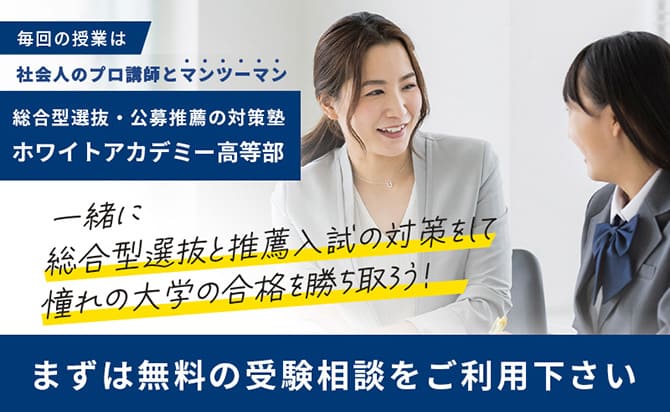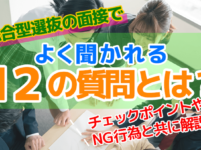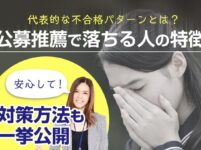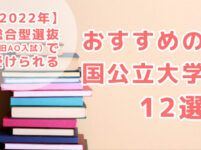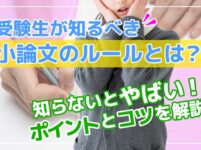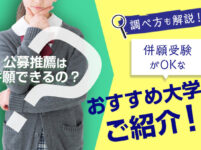BLOG

推薦入試や総合型選抜で受験しようと準備を進めていると、「学修計画書の書き方がわからない」「質の高い学修計画書を作成する方法が知りたい」と悩みますよね。
本記事では「学修計画書とは何なのか」に触れつつ、具体的な書き方や例文、ポイントなどを徹底的に解説していきます。
本題に入る前に、総合型選抜・公募推薦の対策塾ホワイトアカデミー高等部では、プロの講師から総合型選抜・公募推薦の攻略方法について徹底的に学べる特別授業を実施しています。
本記事で紹介する学修計画書の書き方についてもさらに詳しく学ぶことができるため、興味のある人はまずホワイトアカデミー高等部の無料相談会に参加してみてください。↓
当記事を読めば、学修計画書に関する以下のような事を学べます
- そもそも学修計画書とは何か?
- 記載する事になる内容
- 大学側に評価されるポイント
- 学修計画書の具体的な書き方と例文
- 高い評価を受ける学修計画書を作るための手順
この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。
自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。
高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。
倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。
目次
総合型選抜や推薦入試で課される学修計画書について
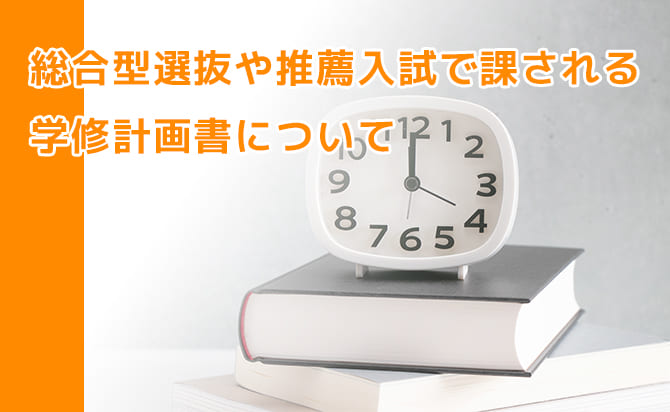
総合型選抜や推薦入試では、学修計画書の提出を条件としている場合があります。下記の流れに沿って、学修計画書の概要を確認していきましょう。
- そもそも学修計画書とは?
- 学修計画書の文字数の目安
- 志望理由書との違い
そもそも学修計画書とは?
学修計画書とは、志望校へ入学した後の学習プランを書く書類です。大学受験においては、総合型選抜や公募推薦を利用する際に出願書類の1つとして大学側から課される事があります。
なお、文部科学省の「35_高等教育の修学支援新制度について」では、学修計画書によって確認すべき項目として以下の3つを取り上げております。
- 学修の目的
- 学修の計画
- 学修継続の意志
つまり、学修計画書は、上記の3点が伝わるように書く事が求められると考えましょう。
学修計画書の文字数の目安
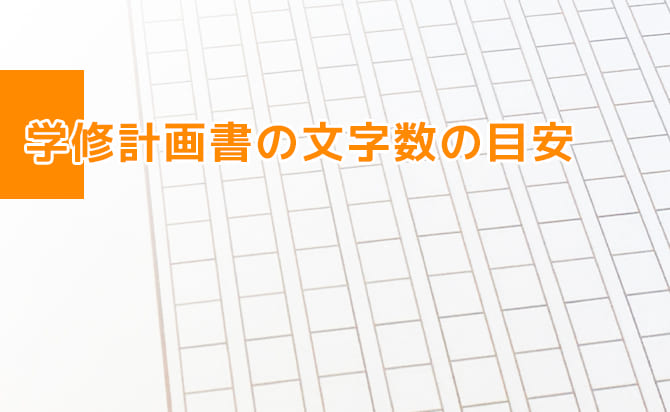
学修計画書は、文字数が指定されたかたちで作成するケースがほとんどです。
文字数の目安は志望校によって異なりますが、「3つの項目を各400字で作成(合計1,200字)」や「全体を1,000字で作成」などの形式が一般的です。
例えば、日本大学の商学部の総合型選抜では、2つの質問項目があり、それぞれが500文字以内で記載する事が求められております。
1.学修の目的
①日本大学商学部で達成したいこと(具体的な目標,特に勉強したい内容・計画を含む)及び将来の夢 (500字以内)
②合格してから入学するまでの学修計画(具体的な目標,特に勉強したい内容・資格等を含む) (500字以内)
上記のように学修計画書では、在学中や卒業後のキャリアについても考える必要があるといえます。将来を見据えて学習に取り組む姿勢をアピールしましょう。
志望理由書との違い
学修計画書とよく似たものに志望理由書があります。両者は似ていますが、以下の点で大きな相違点があります。
| 書類の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 志望理由書 | 志望する大学・学部への入学を希望する理由や入学後に学びたい事を記載する事が求められます。 |
| 学修計画書 | 「志望する大学・学部に入学をした後の学びの目的を明確にする。特に、卒業後の展望は具体的に書く。それを実現するために何をどのように学び研究する予定なのかについての履修計画やゼミ・研究室の希望等を書く。意欲のアピールも重要となる。 |
上記のように志望理由書では、志望する大学・学部に入学したいと思う動機や入学後にやりたい事の方向性の記載が求めれます。
一方で学修計画書の場合、大学に入学後の学修の計画や卒業後の展望を具体的に書く必要があるので、単なる方向性ではなく具体的な計画にまで落とし込む事が求められます。
そのため、志望理由書と学修計画書は一見すると似ているかもしれませんが、求められる記載内容が異なる事は押さえておきましょう。
作成時に記載が求められる主な3つの内容

学修計画書に記載する事になる項目は大きく分けると以下の3つになります。
- 学修の目的(なぜ学びたいのか)
- 学修の計画(どのように学ぶのか)
- 学修継続の意志(卒業まで学び続けられるのか)
なお、文部科学省の「35_高等教育の修学支援新制度について(P5)」において、学修計画書に記載する内容は以下のように定義されています。
① 学修の目的(将来の展望を含む)
「学修計画書」により確認すべき項目
次の観点のいずれかが述べられているかを確認
・学修の目的が明確に述べられているか
・学修の目的を自身の言葉で表現できているか
・卒業後の将来の展望が述べられているか
・社会で自立し、活躍できるようになることが期待できるか② 学修の計画
次の観点が述べられているかを確認
上記の学修の目的を踏まえ、これまでに何を学び、今後、何を
どのように学びたいか等が自分の言葉で述べられているか③ 学修継続の意志
次の観点のいずれかが述べられているかを確認
・卒業まで学修を全うしようとする意志があるか
・しっかり学ぼうとする意欲があるか
・その他、学修の意欲が十分にあると認められるか参考元:|「35_高等教育の修学支援新制度について(P5)」
各記載内容について詳しく解説していきます。
学修の目的|なぜ学びたいのかを書く
学修計画書を作成する際は、学修の目的を志望校に伝えるためにも、「他の大学ではなく、志望校で学びたい理由」を記載しましょう。
なぜなら、志望校側は「卒業後の将来展望を見据えて進学を検討している人材なのか」を知りたいからです。
例えば、「国語教員になるために教育学部への進学を希望する」と表現してしまうと、志望校側は「教育学部なら、どの大学でも良いのではないか」と考えてしまいます。
そのため、志望理由を書くときは「カリキュラムが充実している」や「◯◯教授のゼミに参画したい」など、「志望校でなくては進学の意味がない」という内容を含めることが有効です。
こうした内容を入れられると説得力が増し、印象に残る学修計画書になります。ぜひ具体性を意識した「学修の目的」の作成を意識しましょう。
学修の計画|どのように学ぶのかを書く
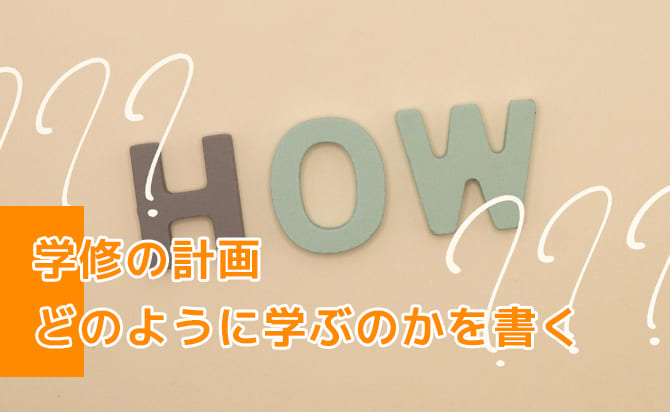
学修計画書を作成する際は、学修の計画である「目的達成のためのプロセス」について論述しましょう。
この理由は、志望校側が受験生の学習意欲・積極性を知りたいと考えているからです。
例えば、国際的に活躍するエンジニアを目標にし、工学部への進学を希望する学生を想定します。
この場合、機械の設計に携わる場面が想定されるため、物理の知識に加えて、外国語の習得が必要です。
複数の必要なスキルや知識、資格を習得するために「◯年後には△△を達成している」と、段階的なプロセスを考える必要もあります。
将来的な目的達成を実現する計画性が問われることを念頭において、学修計画書の作成に取り組みましょう。
学修継続の意思|卒業まで学び続けられるのかを書く
学修計画書を作成する際は、学修継続の意志として「卒業まで学び続ける姿勢」をアピールすることも大切です。
なぜなら、大学側は「卒業まで学修に取り組んでくれる」事が期待できる受験生の進学を求めているからです。
学修継続の意志の例としては、学業に専念する熱意や、幅広く教養を深める探究心などが挙げられます。
現状の学習レベルに満足せずに向上心を持って卒業まで学び続ける意志があることをアピールしましょう。
特に「学修継続の意志」は、学修計画書のまとめに関わる大切な要素です。
大学生活の4年間で学習に取り組む姿勢を強調して、試験官が納得できる学修計画書を作成しましょう。
大学側が評価する主な3つのポイント
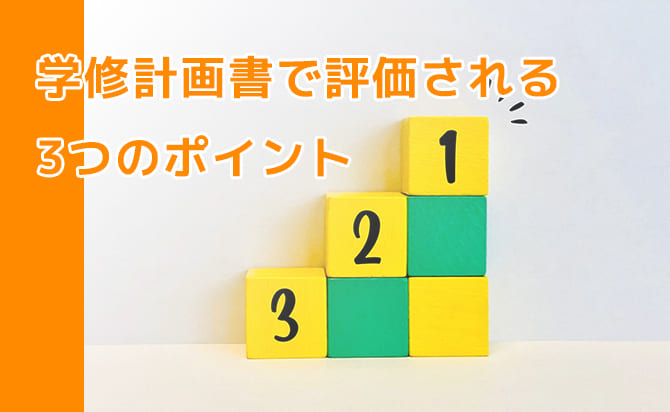
「学修計画書の目的」において、大学側が評価する主な3つのポイントは以下の通りです。
- 具体的な目標が掲げられているか
- 綿密な計画が組まれているか
- 学ぶ意欲を感じられるか
学修計画書の作成に行き詰まっている方は、上記3つの内容を順番に確認していきましょう。
具体的な目標が掲げられているか
学修計画書で評価されるためには、大学在学中から卒業後にかけて目指すキャリアを具体的に掲げる必要があります。
なぜなら大学は学問を学ぶ場である以上、大学側としては、将来的なキャリアを見据えて前向きに学習に取り組める学生に好感を持つためです。
そのため、下記の内容に触れるかたちで文章の構成を考える事をおすすめします。
- 将来どのような職業に就きたいのか
- 社会に出て○○として活躍し、・・・な人を助けたい
- 社会でどのように貢献していくのか
なお、学修の目的は「将来の夢を抱いた理由や目標とする職業になぜつきたいのか」という点に対するストーリーをわかりやすく伝えるのが重要になります。あなた自身の言葉を使って、端的にまとめることを意識しましょう。
綿密な計画が組まれているか

学修計画書が評価されるポイントには「在学中から卒業後にかけて、目標達成のための計画が組まれているか」が重要になります。
そのため、将来の夢や就きたい仕事に就くために、入学後に具体的に何をする計画なのかを書くようにしましょう。一例として書いておきたい項目は以下の通りです。
- ○○な授業の履修をしたい
- ○○を研究できるゼミや研究室に入る
- ゼミ・研究室に入った後の研究予定の内容
- 学校が用意している留学プログラムや資格取得プログラムの利用
上記のような志望する大学・学部・学科が提供している環境と併せて将来の目標や目指す夢の実現に繋がる行動計画を伝えることが重要になります。
学ぶ意欲を感じられるか
学修計画書は「学ぶ意欲を感じられるか」という点で評価されるのもポイントです。
これは「学修継続の意志」に該当する部分であり、卒業まで続けられるかが問われます。
学ぶ意欲をアピールする際は、熱意をもって過去の経験や意志の強さを説明するのが有効です。
これまで長期にわたって物事に打ち込んだ経験があるなら、それを具体例として継続の意志をしっかり持っていることを示しましょう。
過去の経験を踏まえた学修計画書は、他の受験生との差別化にも繋がるため、試験官の目にも留まりやすくなります。
学修計画書の具体的な書き方と例文

続いては、学修計画書の具体的な書き方と例文を下記の流れで紹介していきます。
- 学修の目的の書き方と例文
- 学修の計画の書き方と例文
- 学修継続の意思の書き方と例文
なお、紹介する各例文は、高校生の将来の夢ランキングで男女1位(参照元)の「公務員」を目指す高校生を想定して作成しています。
ただ例文には公務員以外を目指す方が活用できる内容もたくさんあるので、ぜひ参考にしてみてください。
学修の目的の書き方と例文
学修計画書における「学修の目的」の例文は下記の通りです。
ここでは、「公務員になり、地域防災に関する体制を整える人材として貢献する将来を描いている学生」を想定した例を紹介します。
◯◯市は観光地として名の知れた地域ですが、○年の大規模な災害によって、観光客が減少している現状です。
災害を完全に防ぐことは不可能ですが、被害を最小限に抑え、1日でも早く復興するには住民や行政などの連携が欠かせません。
私は公務員となり、住民一人ひとりの防災力アップに尽力していきたいです。
貴学では環境デザイン学科を専攻し、防災の観点から安全な地域づくりについて学びたいと考えています。
上記の例文では「公務員として、地域の連携を強化し、防災力アップに貢献する」という将来像を明記しています。
そして、学修の目的である「デザイン分野を専攻したい」という内容で締めています。
学修の計画の書き方と例文
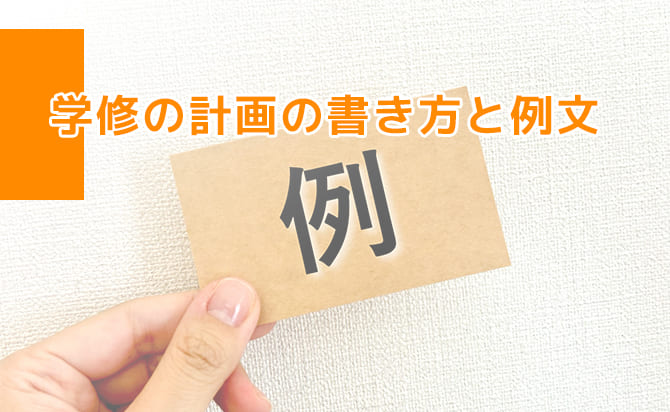
学修計画書における「学修の計画」は、下記の例文を参考にしてみましょう。
ここでは、「公務員になり、子育て支援に関するサービスにしたいと考えている学生」を想定した例を紹介します。
私はそんな環境で4年間学ぶ事を通して、○○市が抱える子育てに関する課題を見つけ、子どもたちが豊かに育つ方策に貢献できる力を身につけたいと考えています。
まず1年次では、児童教育に関する知識の習得に尽力したいです。
2年次以降は、資格の取得やボランティア活動に注力し、蓄積した知識のアウトプットを通じて、私の実現したいことの核心である子育て支援への理解を深めます。
4年次は△△教授のゼミで○○市の特性にマッチした子育て支援の構築を学びたいです。
上記では、学修の目的を実現するために必要な知識が、志望校で得られると記しています。
また、1〜4年次で段階を踏んでスキルアップしていく計画も明記しています。
学修継続の意志の書き方と例文
学修計画書における「学修継続の意志」に関する例文は、下記の通りです。
ここでは、「公務員として社会へ貢献することを考えている学生」を想定した例を紹介していきます。
座学はもちろん、ボランティア活動やインターンシップにも参加し、大学内外の人々との繋がりを構築し、感性を養っていく予定です。
インプットとアウトプットを繰り返し、卒業までにさまざまな経験を積んでいこうと考えています。
上記では、学修に対する意欲を主張し「○○大学で学びたい」「在学中、努力し続ける」という意気込みも記しています。
評価の高い学修計画書を作成するための8つのSTEP

高評価に繋がる学修計画書を作成する手順は、8つのステップに分けられます。
- ①自分の将来について考える
- ②大学入学後に学びたい学問や研究内容を明確にする
- ③大学入学後に学びたい学問や研究内容を明確にする
- ④志望する大学・学部のカリキュラムやアドミッションポリシーを確認する
- ⑤志望大学に入学した後の学習計画や目標を明確にする
- ⑥上記の5つの内容を踏まえて下書きを作成する
- ⑦でき上がった学修計画書を周りの人に見てもらう
- ⑧提出用の学修計画書は丁寧に濃く書く
志望校への進学を実現するために、1つずつ確認していきましょう。
①自分の将来について考える
学修計画書の作成においては、自分の将来の夢や目標を明確にすることが大切です。
「卒業後、どのような職業に就職したいか」「どのように社会へ貢献したいか」などを考えましょう。
ポイントは、10年後・20年後の姿に触れて、長期的なビジョンを明確にすることです。
大学を卒業して数年のビジョンに限らず「どのような立場でどのような仕事をしているのか」を説明しましょう。
学修計画書に記載する将来設計は、一貫性を意識して作成することが重要です。
②大学入学後に学びたい学問や研究内容を明確にする
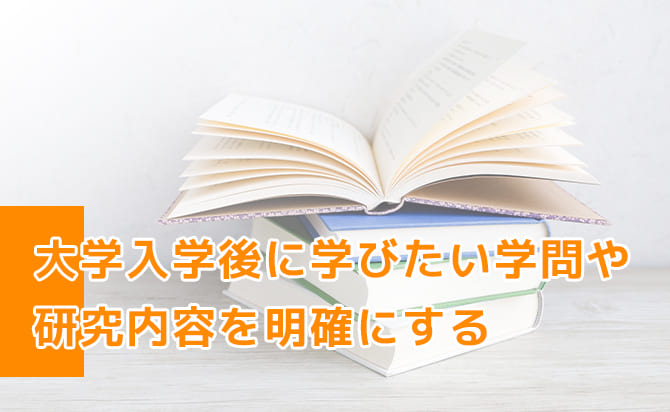
学修計画書を作成する際は、将来の方向性をベースにした上で大学に入学した後に学んでおきたい学問ジャンルや研究テーマを明確にすることが欠かせません。
なぜなら、あなたが将来目指す方向と大学に入学した後の学びをリンクさせる事ができれば、あなた自身も前向きに学問に取り組める上に、大学側にも学ぶ意欲の高さをアピールできるためです。
そのためにもまずはあなたが目指す将来の方向に役に立つ学問は何であり、純粋に学びを深めたい学問ジャンルが何なのかを調べてみましょう。
無事に調べる事ができれば、どんな学部・学科に行くのが最も望ましいのかが分かります。そうなれば、あとは志望する学部・学科の中で最もあなたにピッタリな大学を探す事になります。
②で明確にした分野を学び、研究できるゼミや研究室が志望する大学・学部・学科にあることを確認する
志望する大学・学部・学科には、②で明確した分野を学べたり、研究できるゼミや研究室があるかどうかを確認しましょう。
なぜなら、大学入学後に学びたい学問や研究したい内容と関われる環境がある事が分かれば、あなたと志望校のマッチ度の高さが分かるためです。
それに、志望する大学・学部・学科に入学した後にはどんなゼミに入ったり、どんな授業を履修するがよいのかもある程度イメージできるはずです。
そのため、志望する大学・学部・学科にあなたが学びたい学問ジャンルや研究したい研究テーマと関われるゼミや研究室があるのかは確認しましょう。
確認の結果、万が一志望する大学・学部・学科にはその分野に関するゼミ・研究室がない場合、志望大学を変更するか大学入学後に学びたい分野そのものを変更する必要が生じます。
④志望する大学・学部のカリキュラムやアドミッションポリシーを確認する
学修計画書の質を上げるためには、志望する大学・学部のカリキュラムやアドミッションポリシーの確認が欠かせません。
なぜなら「○○大学に進学しなくては意味がない」という具体性や説得力に関わるからです。
なお、学修計画書を作成する際に活用したい情報は下記の通りです。
- シラバス
- 公式サイト
- カリキュラム
- カリキュラム・ポリシー
- アドミッション・ポリシー
これらの書類では、講義の内容やスケジュール、目標などが公開されており、学修計画を立てる際に役立ちます。
なお、配属を希望する研究室やゼミが決まっている方は、各研究室の情報も確認しておきましょう。
取り扱っている研究テーマや実績を把握し、学修の目的を設定するのもおすすめです。
⑤志望大学に入学した後の学習計画や目標を明確にする

学修計画書を作成するにあたって、志望校のカリキュラムやアドミッションポリシーで得た結果をもとに、学習計画や目標を明確に記載しましょう。
なぜなら、カリキュラムなどを参考にすることで説得力や具体性を強固した唯一無二の学修計画書を作成できるからです。
例えば、知識・スキルの定着をアピールする場合は「○○を履修し、学修に専念する」と明記するのをおすすめします。
また、就職成功を実現する目標を説明するなら「○○研究室(ゼミ)への入室を希望し、△△の研究を通じて理解を深める」と説明してみましょう。
このように書くと志望校側からも「我が校について入念に調査している」「進学する意思が強い」と見られ、目に留まりやすくなる可能性があります。
「志望校への進学を強く希望している」という姿勢を伝えるためにも、上記の内容を意識して学修計画書を作り込みましょう。
⑥上記の5つの内容を踏まえて下書きを作成する
学修計画書の情報収集として明確にしたビジョンや目標をもとに、下書きを作成してみましょう。
下書きを作成する事を推奨する理由は、最初から完璧な書類を作るとなかなか筆が進まないためです。
一方で雑でも良いのでまずは下書きを作ってみようと考えれば、自ずと作成が進みます。
作成した下書きを何度も修正・加筆を繰り返せば、自ずと内容は良くなりますし、最終的には良質な学修計画書の完成に繋がるはずです。
⑦出来上がった学修計画書を周りの人に見てもらう

学修計画書の下書きが作成できた方は、信頼できる知人や家族、学校・塾の先生などに確認してもらいましょう。
これは、第三者にチェックしてもらうことで、自分では気づけなかった文章の間違いや改善点の発見に繋がるからです。
あなたの性格や経歴を把握している方の意見なら、客観的なアドバイスとして捉えられるため、より質の高い書類作成を実現できます。
学修計画書は、考えた内容を下書きし、添削を通してブラッシュアップする工程を繰り返す必要があります。
自分だけで作り上げるのではなく、周りの人のサポートも踏まえて、良質な学修計画書を作成しましょう。
なお、総合型選抜の専門塾なら、より専門的なアドバイスを貰いながら学修計画書を作成できます。気になる方はぜひ利用してみてください。
参考記事:おすすめの総合型選抜の専門塾を一覧で紹介
⑧提出用の学修計画書は丁寧に濃く書く
学修計画書の下書きが完了した方は、提出用の学修計画書の作成に移りましょう。
提出用の学修計画書を作成する際のポイントは、ボールペンで文字を濃くかつ、丁寧に書くことです。
なぜなら、書類に書かれた文字に課題が多いとどんなに頑張って学修計画書を作ってもきちんと評価されない事があるためです。
例えば、筆圧が弱い文字や小さい文字、達筆すぎる文字で書いてある学修計画書は、本気度が低いと思われる事があります。
それに、読みにくい文字で書かれている場合、読み手は無意識に「この人の学修計画書は読みたくない」と思ってしまう事があります。
マイナスな印象を抱かせないためにもボールペンで文字を濃くかつ、丁寧に書くことは心がけましょう。
なお、提出用の学修計画書を作成する中で誤字・脱字が見つかった場合は、修正液や修正テープを使うのではなく、きちんと1から書き直しましょう。
学修計画書に関するよくある質問3選
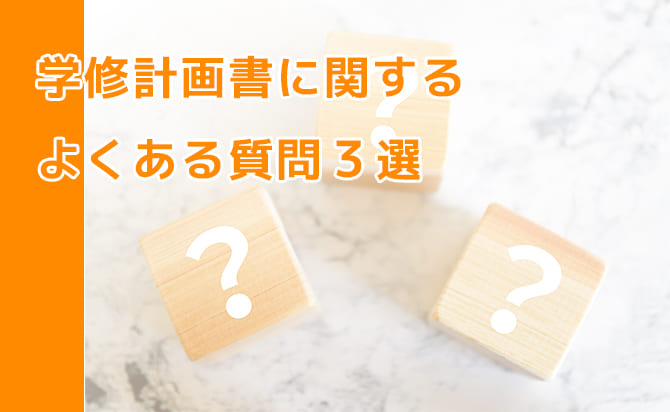
最後に、学修計画書に関する質問を紹介します。
下記2つの質問について回答していますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 学修計画書はですます調で書いた方がいいですか?
- 将来の夢がないときはどうしたらいいですか?
学修計画書はですます調で書いた方がいいですか?
学修計画書は「です・ます調」でも「だ・である調」でも問題はありません。ただし、文章全体で統一することが重要です。
なぜなら、口調が統一されていない場合は「読みにくい」と感じられてしまうのです。
それに読み手によっては「統一性の低い文章を書く人だ」と評価をし、内容以外のところでマイナスの評価をする事もあります。
そのため、「です・ます」であろうと「だ・である調」であろうと統一性を出す事が重要になります。
将来の夢がないときはどうしたらいいですか?
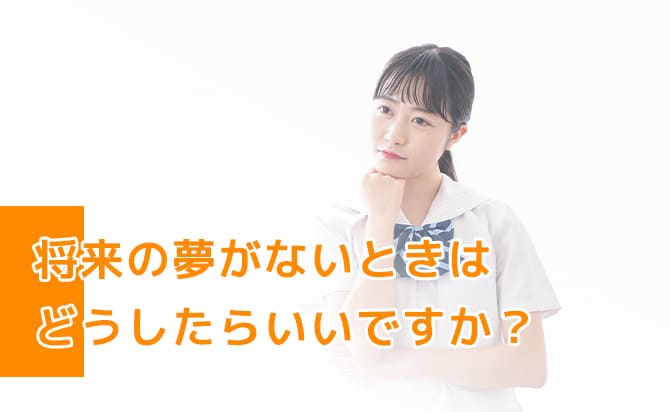
学修計画書に記載できる将来の夢がない方でも、無理に記載しようとする必要はありません。
現時点での将来に関する考えや目的を説明しましょう。
なお、詳しい書き方については、「学修計画書の具体的な書き方と例文」の項目で取り上げた内容を改めて参考にしてみてください。
今回の内容のまとめ

本記事では、学修計画書で書く内容やポイント、よくある質問について解説してきました。
最後に取り上げた内容について、再度確認していきましょう。
今回のポイント
- 学修計画書は入学した後のプランを記載した書類
- 指定された文字数に沿って作成するケースがある
- 志望理由書と学修計画書の違いは具体的な計画の記載が求めるか否か
- 学修計画書に書く内容は主に「目標」「計画」「継続の意志」の3つ
- 学修計画書は「ですます調」や「だ・である調」に統一する
- 将来の夢がない場合は現時点での考えや目的を記載する
- 学修計画書には嘘の情報を記載しない
総合型選抜や推薦入試で学修計画書を作成する必要がある場合は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
なお、一人で学修計画書を作成する自信がない方は、ホワイトアカデミー高等部のような総合型選抜や公募推薦のサポートに特化した塾の利用を検討してみましょう。
ホワイトアカデミー高等部では無料の相談会も実施しておりますので、まずは気になる点や疑問点を気軽に相談してみてください。

ホワイトアカデミー高等部とは?
総合型選抜・公募推薦入試に特化した専門塾。
プロ講師が活動実績作りから小論文・面接まで、
マンツーマンで徹底サポート。
- カリキュラム修了者の合格率98%※1
- 上智大学合格率83%(2025年度)※2
- 小論文・書類すべて添削無制限
- 全授業が社会人のプロ講師による1対1形式
- カリキュラム修了者には合格保証制度を提供

※2 上智大学合格率83%は2025年度入試における上智大学受験者が母数です。
この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。
過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。
昨年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。