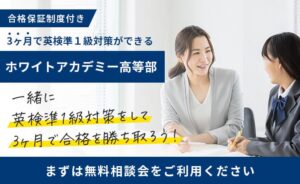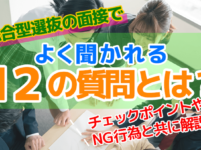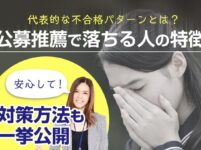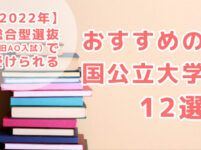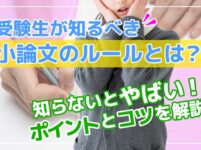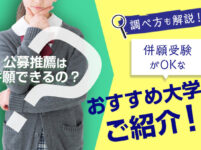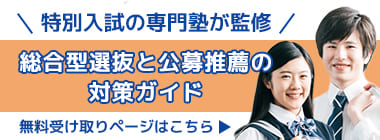BLOG

「英検準1級リーディングの長文が難しくて読めない」
「長文読解の効率的な勉強法やコツを教えてほしい」
英検準1級の対策をしている方でこのようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、そのような方に向けて英検準1級の長文問題で高得点を取るためのコツや対策法について解説します。
リーディング問題が苦手という方や効率的に対策をしたいという方はぜひ最後までお読みください。
本題に移る前に、ホワイトアカデミー高等部では英検準一級対策に向けた無料相談会を実施しています。
英検準1級の取得に少しでも不安があるという方は、ぜひ一度無料相談会にお越しくださいませ。
英検準1級に合格するための無料相談会の予約はこちらから
この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。
自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。
高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。
倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。
英検準1級リーディング問題の概要
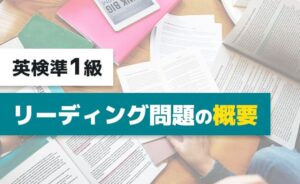
英検準1級のリーディングセクションは、受験者の語彙力、読解力、そして批判的思考能力を評価するために設計されています。このセクションは、3つの大問で構成されています。
大問1では、短い文章や段落の中から文脈に合った単語を選ぶ、ボキャブラリー問題が出題されます。問題数は18問であり、純粋な単語・熟語の知識が問われます。
大問2では、空欄補充問題が出ます。ここでは、250語程度の長文を読み、文中の空欄に当てはまる適切な語句を選択するという問題が出題されます。
長文が2つにそれぞれ3問の設問が与えられるので、問題数は合計6問となっています。
大問3では、内容一致問題が出題されます。ここでは400〜500語の長文を読み、長文の内容に関する設問に解答するという問題が出題されます。
長文は2つ与えられ、1つ目には3つの設問、2つ目には4つの設問があり合計問題数は7問です。
このように英検準1級のリーディング問題は、大問3つの合計31問で構成されています。
大問1は純粋な語彙力を図る問題ですので、ここでは長文読解問題である大問2と3についてより詳細に解説していきます。
英検準1級リーディング大問2の内容
リーディングセクションの大問2では、250語程度の文章を読み、文中の空欄に当てはまる語句を解答するという問題が出題されます。出題される文章は、説明文または評論文となっています。
説明文とは、その名の通りあるテーマに対して順序立ててわかりやすく説明する文章です。
評論文は、あるテーマについての筆者の主張を根拠とともにまとめている文章のことです。そのため、他人の主張への批判やテーマに対するメリットやデメリットの対比などがよく用いられます。
設問で求められる解答には、適切な論述となるように最適な語句を選ぶものが多いですが、純粋な接続詞を選択する問題もほぼ必ず出題されます。
文脈や文法的整合性を見極める力が求められる問題となっています。
英検準1級リーディング大問3の内容

リーディングセクションの大問3では、400〜500語程度の長文が2つ与えられ、長文の内容に対する設問に解答するという問題が出題されます。大問2と同様に、設問文または評論文が出題されます。
設問の内容は、長文の内容に対する質問への適切な解答を選択する問題や長文の内容に一致するように文章を完成させる穴埋め問題などがあります。
解答につながる箇所を素早く見つけ出す速読力が求められる問題となっています。
長文問題でよく出題されるテーマ
英検準1級の長文問題が難しいと感じる理由は、出題されるトピックの専門性にあります。
専門的なトピックであるため、英語力と合わせてトピックに対する知識を有しているほうが圧倒的に読みやすくなります。
以下に、英検準1級の長文でよく出題されるテーマについてまとめました。
| テーマ | 出題されやすい分野 |
|---|---|
| 自然・環境 | ・ある動物や植物の生態などの「生物学」 ・地質や天文学、気象などの「地学」 ・代替エネルギーや地球温暖化、海洋プラスチックなどの「SDGs」 |
| 医療・テクノロジー | ・アレルギーや治療法などの「医学」 ・抗生物質や化学物質などの「薬学」 ・予防や健康、生活習慣などの「衛生学」 ・遺伝子組み換え技術などの「遺伝子工学」 ・AIやドローン、宇宙開発などの「工学」 |
| 文化・歴史 | ・遺跡や遺物調査などの「考古学」 ・戦争や侵略などの「世界史」 ・絵画や音楽などの「芸術」 ・人々の日常生活から文化や社会を理解する「文化人類学や民俗学」 ・信仰や儀式などの「宗教」 ・消滅危機言語や言葉の使い方などの「言語学」 |
| 教育・心理 | ・PBLやSTEAMなどの「新しい教育手法」 ・うつ病や心の発達などの「心理学」 ・スマートフォンと学力の関係などの「テクノロジー×教育」 ・経済と学力の関係などの「教育経済学」 |
| 社会・ビジネス | ・ 政治体制や国家間対立、貧困や格差、テロや犯罪、少子高齢化、難民などの「社会問題」 ・注目されている新しい技術を取り入れた「事業・ビジネス」 |
これらのテーマについて、日頃からニュースや新聞記事などで情報収集を行なっておくことで、長文問題が読み解きやすくなります。
また、専門用語の英単語なども合わせて覚えておくと良いでしょう。
このように、英語力と合わせて出題されやすいテーマについて知識をつけていくことも英検準1級の長文対策に求められます。
英検準1級長文問題の解答のコツ

次に、英検準1級の長文問題で高得点を取るための解答のコツについて紹介します。
英検準1級の長文問題は、専門的なトピックであることに加えて、新形式となり要約問題が増えたことから短時間での解答が求められています。
そのため、いかに効率的に設問に解答していくかが問われます。
解答のコツについて、大問2、大問3のそれぞれに分けて解説します。
大問2:空欄補充問題の解答のコツ
大問2は空欄補充問題です。求められる解答は、前後の文だけで判断できるものもあれば、適切な接続詞を入れるものなどの全体の流れや文脈から判断するものもあります。
大問2の空欄補充問題の解答のコツは以下の流れに沿って解答することです。
- タイトルを読み内容を予測する
- 設問を簡単に確認し文章を読み解答する
- 設問の確認と読解を繰り返す
それぞれ解説します。
タイトルを読み内容を予測する
まず重要になるのは、タイトルから話の構成や流れを予測することです。「タイトル」とは文字通りその文章のお題を端的に表したものです。
つまり、タイトルは文章全体の主題や方向性を示唆しており、それを理解することで本文の意図を把握しやすくなります。
タイトルを通じて、どのようなテーマやトピックが扱われているのかを予測し、その予測をもとに本文を読み進めることで、内容の理解がスムーズになります。
例えば、「The Importnce of Insects(昆虫の重要性)」というタイトルであれば、「一般的に嫌いな人が多い昆虫には意外な側面があり、その重要性について述べられる」というような予測が立ちます。
すると、おそらく第1段落の導入において「昆虫は一般的には苦手な人が多いが、〜において重要である」というような話が述べられ、第2、第3段落で「その重要な特徴の詳細や研究結果について」述べられるのではないかというような予測を立てることができます。
また、タイトルに「Insects」と入っているため、万が一「cockroaches」という固有名詞がわからなかった場合でも、「昆虫の一種である」ということは理解できます。
※「cockroach」とはゴキブリです。
このように、予測を立てることで話の流れを理解しやすくなったり、わからない単語の推論をしたりすることが可能になります。
英検準1級の長文問題では、情報が専門的であり、単語も難しい場合が多いため、タイトルを基にした内容の予測が有効です。これによりリーディングのスピードを上げるだけでなく、正確に内容を捉えることができます。
さらに、タイトルから得た予測が本文を読み進める中でどのように展開されるかを意識することで、筆者の意図や論旨の流れを理解することができます。
これらのことから、英検準1級の長文問題を解く際には、いきなり本文を読むのではなく、タイトルをしっかりと確認し、その内容を予測することが重要です。
設問を簡単に確認し文章を読み解答する
タイトルを読み、内容を予測した後は1つ目の設問を簡単に確認しましょう。
なぜなら、設問の解答を簡単に確認することで、どこに注目して読み進める必要があるのかを理解することができるからです。
例えば、設問が接続詞を解答するものであれば空欄の前後の話の流れやディスコースマーカーについて注意しながら文章を読み進めることができます。
また、設問の動詞の時制や目的語からも話の流れのヒントや注目すべき単語などを得ることができます。
このように、文章を読み進める前に簡単に設問に目を通すだけで文章が読み進めやすくなります。タイトルを確認した後はいきなり文章を読むのではなく、設問を簡単に確認してから読み進めましょう。
そして、空欄まで読み進めたら再度設問を確認し、解答しましょう。
この時、選択肢同士の違いに注意してください。意味やニュアンスが似ている選択肢も混在していることがあります。
具体的な英単語の意味、コロケーション(どんな単語と一緒に使われやすいか)などをしっかり把握しておきましょう。
なお、空欄の前部分だけでは解答できない場合は、空欄の後ろの文章についても2文ほど読むと解答できるでしょう。
設問の確認と読解を繰り返す
1つ目の設問に解答した後は、2つ目の設問を簡単に確認し次の空欄まで文章を読み進めましょう。そして、2つ目の設問に解答したら、3つ目の設問を確認し次の空欄まで文章を読み解答しましょう。
このように、いきなり文章を読み進め解答するよりも、タイトルや設問から情報を収集してから文章を読み進めることで、文章の理解がしやすくなり、早く問題を解くことができます。
英検準1級の長文問題は難解な内容が多いため、この流れに沿って解答することが高得点をとるコツとなっています。
大問3:内容一致問題の解答のコツ
大問3は、内容一致問題となっています。英検準1級では、トピックも専門的なテーマとなり、文章の語数も400〜500語と多くなるため、苦手な人は多いのではないでしょうか。
そんな英検準1級リーディングセクション大問3の解答のコツは以下の通りです。
- タイトルを読み内容を予測する
- 設問を読み注目すべき情報を理解する
- 1つの段落を読み1つの設問に解答する
- 設問の確認と読解を繰り返す
基本的な解答のコツは、大問2の空欄補充問題と同じです。一方で、大問3は、内容一致問題であるため、必ず設問の中に本文の内容をまとめたものが含まれているということが重要です。
よって、大問2よりも大問3の方が設問を読み注目すべき情報を理解することの重要性が増します。
また、英検準1級の長文問題では、必ず設問1つに対して段落1つであり、設問と段落は上から順になっています。
つまり、1つ目の設問は必ず第1段落について問われています。これらを踏まえた上で、解答のコツについて解説していきます。
タイトルを読み内容を予測する
大問3においても大問2と同様に、タイトルから文章の内容を予測しましょう。
英検準1級では長文のトピックが専門的になるため、タイトルから話の流れや注目すべき単語を予測するだけで格段に理解しやすくなります。
そのため、タイトルは確実に読み話の流れを予測してください。
設問を読み注目するべき情報を理解する
タイトルを読み、内容を推測した後は設問を読んでください。
なぜなら、大問3では内容一致問題が問われるため、設問の解答に必ず本文中で述べられる内容が含まれているからです。
また誤っている解答も解答者を困らせるために近い内容について述べられることが多いです。
例えば、AはBより大きいと本文で述べられているが、設問ではAはBより小さいと書かれている、というような状況です。
この場合、AとBの大きさについて比較しているかもしれないという情報やAとBの比較が行われることが理解できます。
また、設問の問題文を読むことで注目するべきポイントが理解できます。
例えば、問題文で「According to the first paragraph, what is true about “A”」と書かれている場合、「A」という固有名詞について注目しながら読む必要があることがわかります。
このように、設問の問題文と解答を先に読むことで、文章の内容を理解する助けとなる情報や解答するために必要な情報を集めることができます。
これにより、「文章を読み理解する」という問題から「文章中から解答となる箇所を探し出す」という問題に変わります。
1つの段落を読み1つの設問に解答する
タイトルと設問から情報を収集したら、文章を読み進めましょう。英検準1級の長文問題では、1つの設問に対し、問われる段落は必ず1つとなっています。
さらに、設問の順序と段落の順序も一致しているため、1つ目の設問を読み第1段落を読み進めましょう。設問の確認で得た、注目するべき固有名詞などに注目し解答に必要な情報を見つけましょう。
頭から全てを訳し理解しようとするのではなく、答えになる箇所を探すように読むことで短時間での解答が可能になります。
英検準1級の長文で高得点をとるために必ずしも全文を理解する必要はないということです。
解答の際には、「部分的な正解」に惑わされないように気をつけましょう。
英検準1級では、選択肢に「本文に書かれているが答えではない情報」や「一部は正しいが全体としては誤り」という紛らわしい内容が含まれることがあります。
本文全体の論旨と合致するかを見極めましょう。
設問の確認と読解を繰り返す
1つ目の設問に解答したら、次の設問を確認しましょう。そして、2つ目、3つ目の設問についてもこれまでと同様に解答していきましょう。
また、設問に出てくる固有名詞が複数あったり、覚えづらい単語であったりした時は、⚪︎や△などの記号に置き換えることも有効です。従来型の会場形式であれば、文章に書き込みができるため固有名詞が出てくるたびに記号を書き入れると良いです。
このように、大問3では、大問2よりも問題文が長くなるため、タイトルと設問から情報を得ることがより重要になります。
なお、設問の解答は本文の文章をそのまま書いていることは滅多にありません。基本的にパラフレーズ(言い換え)されていることに留意して、情報を集めましょう。
英検準1級長文対策のおすすめの勉強法
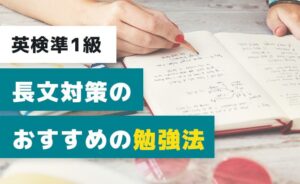
英検準1級の長文対策において、効果的な勉強法は以下の3つです。
- 単語量を増やす
- 日本語で知識を入れる
- じっくり1回ではなく素早く3回読む
それぞれの勉強法について解説します。
おすすめの勉強法①:単語量を増やす
当然ですが、長文対策において最も重要となるのは単語力です。
英語の文章を正しく理解するためには、文章全体で知らない単語が2%以下であることが望ましいとされています。
5%程度であれば推論を活用しながら概ねの理解が可能であり、10%を超えてくると、文章の正確な理解に支障が生まれます。
そして、20%を超えると文章を読むことが困難になります。
参照元:Hu, M., & Nation, P. (2000). Unknown vocabulary density and reading comprehension.
英検準1級の長文で8割の点数を取ることを目指すのであれば、文章全体の概ねの理解ができるレベルには持っていきたいところです。
つまり、文章全体で知らない単語が10%以下を目指す必要があります。
これは、おおよそ1文に知らない単語が1つ程度の単語力を表します。よって、過去問を解き、知らない単語がこれよりも多い割合である場合は、単語力の強化を図りましょう。
単語学習においては、類義語や派生語をまとめて覚えたり、文章を何度も読む中で覚えたりすることが有効です。
特に、英検準1級では、専門的なトピックが扱われるため専門用語の理解が必要です。
テーマ別の英単語帳を活用したり、英字新聞を活用したりすると良いでしょう。
また、過去問を解いたり、練習問題を解いたりする中でわからなかった単語をまとめて、オリジナルの単語帳を作成することも有効です。
英検準1級対策に向けた効率的な単語学習方法については以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
参考:英検準1級単語学習法
おすすめの勉強法②:日本語で知識を入れる
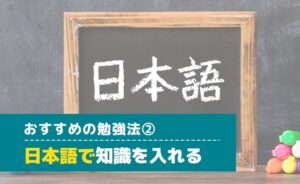
2つ目の英検準1級の長文対策におすすめの勉強法は日本語で知識を入れることです。出題されるテーマに対する背景知識があるだけで、格段に読解がしやすくなるだけでなく、単語の意味の推論もしやすくなります。
そのため、新聞や雑誌、図書館にある本などを活用し出題されやすいトピックについての知識を習得していきましょう。
おすすめの勉強法①で解説した、テーマ別の単語帳や英字新聞の活用は専門用語の英単語と専門知識を合わせて習得することができます。
例えば、BBCは英語での記事と日本語での記事がありますので、これらを合わせて読むことが有効です。
このように、試験でよく出題されるテーマの幅広いトピックに触れ、知識を習得しましょう。
おすすめの勉強法③:じっくり1回ではなく素早く3回読む
3つ目の長文対策におすすめの勉強法は、じっくり1回ではなく素早く3回読むことです。具体的には以下のように読むことです。
| 回 | 読み方 |
|---|---|
| 1 | ザッと全体の流れを把握(スキミング) |
| 2 | 設問を意識しながら、キーワードを探すように読む |
| 3 | 大切な部分を再確認しながら、解答を確定する |
このように読むべき理由は2つあります。
1つ目は、英検準1級のリーディングセクションで高得点を取るためには必ずしも全文を理解する必要がないからです。
特に、大問3の内容一致問題は全文を理解することよりも、解答となり箇所を探しだすことが求められます。
つまり、一文一文を正確に訳さなくても解答することができるのです。
2つ目は、英検準1級のリーディングセクションの時間が極めてタイトであるこからです。英検が新形式となり要約問題が追加されたこともあり、リーディングセクションがより短時間で解答することが求められています。
そのため、全文を全て訳し理解する癖をつけてしまうと、時間内に解ききれなくなる可能性が高いです。
これらの理由から、日頃から一文一文をじっくり読むのではなく、素早く何度も読むことを心がけましょう。
特に、慣れないうちはわからない単語が出てきた時についつい止まってしまいがちです。
わからない単語が出てきても止まらず読み進め、問題文と設問を何度も読み直し解答する癖をつけましょう。
読解力を高める読み方のコツ
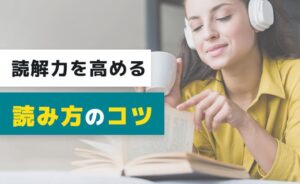
英文の読解力を高めるための効果的な読み方にはいくつかのコツがあります。このコツを押さえるだけで、文章が読みやすくなり、理解が深まります。
読解力を高める読み方のコツは以下の通りです。
- 英文の文章構造を理解する
- ディスコースマーカーに注意する
- スキミングとスキャニングを使い分ける
それぞれのコツについて解説します。
読み方のコツ①:英文の文章構造を理解する
まず1つ目の読み方のコツは、英文の基本的な文章構造を理解することです。
英文の基本構造を理解していれば、話の流れがスムーズに理解でき、注意して読むべきポイントとそうでないポイントを見分けることもできます。
英語の文章は、序論(Introduction)→本論(Body)→結論(Conclusion)の3部構成となっています。
それぞれで述べられる内容について解説します。
序論(Introduction)
序論では、文章全体のテーマや主張、問題提起を述べます。その上で、必要な事前知識や背景の情報について記載されます。
文章全体で述べることになるトピックになるため、最も重要なパートであると言えます。
本論(Body)
本論では、主張やテーマを補足するための具体的な内容について記載されます。
本論では、以下のような論理展開が行われます。
| 論理展開 | 説明 |
|---|---|
| 原因と結果 | ある事象の原因と、その結果を説明する |
| 問題と解決策 | 問題点を提示し、その解決策を提案する |
| 対比・比較 | 2つ以上の対象を比較し、類似点や違いを説明する |
| 列挙 | 複数のポイントや種類、特徴などを順番に説明する |
| 例示 | 主張を具体例で補強する |
| 譲歩・逆説 | 主張に対する反対意見を提示しそれに反論することで主張を補強する |
| 定義 | 文章のテーマとなるトピックの定義付けをし読み手の理解を促進する |
このような論理展開が本論では繰り広げられます。
結論(Conclusion)
結論では、主張の再確認やトピックの要約が行われます。ここまで述べてきた内容のポイントをまとめながら文章全体の主張やテーマについておさらいします。
また、今後の展望や読み手に向けた提案などが行われることもしばしばあります。
このような文章の基本構造を理解することで、文章全体の理解がしやすくなります。
読み方のコツ②:ディスコースマーカーに注意する
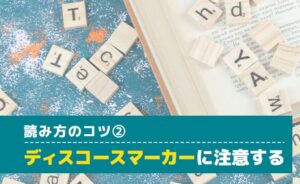
英文読解において、ディスコースマーカーに注意することは極めて重要です。
なぜなら、ディスコースマーカーとは論理表現を表す語句であるため、文章構造や流れを理解するために重要となるからです。
特に、コツ①に出てきた論理展開を表すディスコースマーカーは重要です。
以下に主なディスコースマーカーをまとめましたので、確認してください。
| 論理展開 | ディスコースマーカー |
|---|---|
| 原因と結果 | because, due to, as a result, therefore, thus |
| 問題と解決策 | the issue is, one way to solve this is, a possible solution is |
| 対比・比較 | on the other hand, similarly, in contrast, whereas |
| 列挙 | first, second, in addition, finally |
| 例示 | for example, such as, to illustrate |
| 譲歩 | though, although, even if, in spite of, regardless of |
| 逆説 | but, however, yet, nevertheless |
読み方のコツ③:スキミングとスキャニングを使い分ける
読解力を高める読み方の3つ目のコツは、スキミングとスキャニングを使い分けるということです。
スキミングとは、英文の概要を理解するための読み方で、文の要点や概要をおさらいしながら情報をすくいとって読む方法です。英語のskim(すくい取る)に由来する言葉です。
スキャニングとは、特定の情報や該当する箇所を探しだすための読み方です。英語のscan(精査する)に由来する言葉です。
これら二つの読み方を問題に合わせて使い分けを行いましょう。
例えば、大問3の内容一致問題であれば、設問で問われている箇所に該当するものを探しだす必要があるため、スキャニングで読みます。つまり、該当する固有名詞などを探しながら読みます。
一方で、接続詞を答える問題や段落全体から推測して答えるような問題であれば、スキミングでパラグラフの概要や文章の流れを理解しながら読む必要があります。
このように、問題に合わせて読み方を変えることで効率的に読解することができます。過去問などを活用し勉強を行う際に意識をすることで、これらの読み方の使い分けができるようになるでしょう。
よくある質問
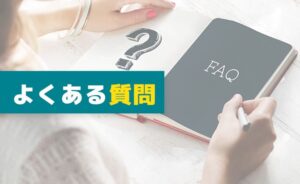
続いて、英検準1級リーディングセクションの長文問題に関するよくある質問に回答していきます。
時間配分はどうすればいいですか?
英検準1級の長文問題の理想的な時間配分は、大問2で15分、大問3で25分です。つまり、リーディングセクションの長文問題を40分解答することを目指しましょう。
英検準1級では、リーディングとライティングを合わせて90分で解答することになっています。配点の大きいライティングに十分な時間(約30分)を確保するためには、リーディングセクションを60分で終わらせる必要があります。
長文問題を40分で解答することで、大問1の語彙問題合計18問を1問1分で解答する余裕が生まれます。
このように、ライティングに必要な時間に個人差はあるものの、長文問題にかける時間は40分が好ましいでしょう。
英検準1級に合格するための長文問題の目標点数は?

英検準1級のリーディングセクションでの目標点数は、個々の英語力や学習進度によってかなり異なります。一般的に英検準1級の合格基準は、総合得点で約70%とされています。
4技能全てでバランスよく点をとる場合は、70%程度の正答率、すなわち長文問題13問のうち9〜10問の正解を目指しましょう。
もちろん、リスニングやライティングが苦手だという方であれば、それを補うために90%程度の正答率を目指す必要がありますし、リスニングやライティングが得意な方であれば50%程度の正答率でも問題ないでしょう。
このように、リーディングだけでなくリスニングやライティングなどの他の技能の得意不得意と合わせて目標点数を設定し対策を行いましょう。
長文対策は同じ問題を何度も解く?新しい問題を多く解く?
問題については、同じ問題を完璧になるまで何度も解くことが好ましいです。
一方で、新しい知識や表現に触れるために、新しい英文を多く読むことも重要です。
それぞれの使い分けについて解説します。
同じ問題を何度も解く
過去問などの長文問題を何度も解き直すことは有効な勉強法です。単に問題に正解したかどうかではなく、わからなかった単語のおさらいやなぜその解答が正しいのかまで説明できるようにしましょう。
これにより、自身が間違えやすい問題や覚えていない単語の復習などを行うことができます。
また、過去問であれば本番形式の文章となっているため、何度も繰り返し読むことで、英検準1級の長文の文章構造や文章の流れについても理解できるようになるでしょう。
このように、同じ問題を完璧になるまで何度も解き直すことは極めて重要な勉強法です。
新しい問題を多く解く
しかし、同じ問題や英文のみであれば知識やトピックの幅に限界がありますし、すでに完璧になった英文を何度解き直しても効得られるものは薄いと言わざるを得ません。
新しい問題や英文に多く触れることは、新しい単語やトピックに触れられたり、本番の初見問題への対応力を身につけたりすることに役立ちます。
一方で、新しい問題や英文に多く触れるために参考書を多く買うことは、すべてを使いきれなかったり、金銭的な負担になったりします。
そこで、英字新聞などを活用し新しい英文に多く触れることが良いでしょう。
参考書などの問題については、同じものを何度も解き直し、完璧にしましょう。その上で、英字新聞などを活用し新しい英文にもどんどん触れることが良いでしょう。
まとめ:英検準1級長文対策

本記事では、英検準1級リーディングセクションの長文問題対策について解説してきました。
最後にここまで解説した中で特に重要なポイントについてまとめますので、ご確認してください。
特に重要なポイント一覧
- 英検準1級の長文問題は空欄補充問題と内容一致問題が出題される
- 英検準1級の長文問題で出題されやすいテーマは、自然、環境、医療、テクノロジー、文化、歴史、教育、心理、社会、ビジネスである
- 長文問題を解答する際のコツはタイトルから内容を予測することと、設問から解答のヒントとなる情報を得ることである
- 英検準1級長文対策におすすめの勉強法は、単語力を上げること、出題されやすいテーマについて日本語で知識を入れること、素早く何度も読む癖をつけることである
- 英語長文の読み方のコツは、英文の基本構造を理解すること、ディスコースマーカーに注目すること、スキミングとスキャニングを使い分けることである
- 英検準1級の長文問題は40分で解くことを目標とし、目標点数は他の技能の得意不得意に合わせて設定する必要がある
本記事を通じて、英検準1級の長文対策への理解が深まり対策の参考になれば幸いです。
最後になりますが、英検準1級対策が難しく、一人では難しいと感じられた方は専門塾を利用することも検討してみてください。以下のページにて、英検対策専門塾についてまとめておりますので、ぜひご覧ください。
この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。
過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。
昨年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。